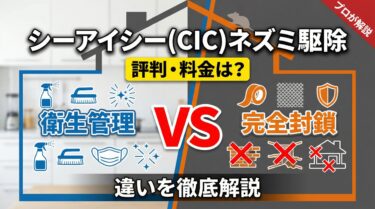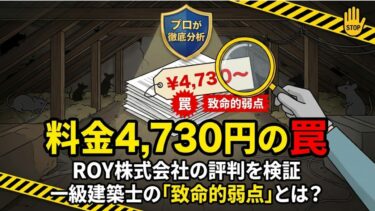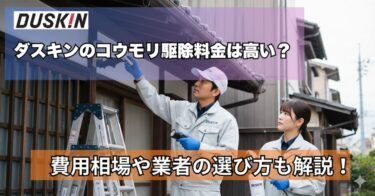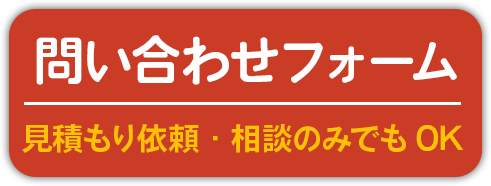タヌキを放置すると、農作物の被害や家庭菜園への侵入、屋根裏や軒下への巣作りなど、人間の生活に問題を引き起こすことがあります。
こうした被害が発生すると、なるべく早くタヌキを駆除したいですよね。
そこで本記事では、タヌキ駆除に関する正しい知識を害獣駆除のプロがわかりやすく解説します。
さらにタヌキが引き起こす被害や似ている動物、駆除する際の注意点や流れも紹介しますので、タヌキ被害に困っている場合はぜひ参考にしてください。
タヌキが引き起こす4つの深刻な被害

タヌキの被害を放置すると、下記4つの被害を引き起こす可能性があります。
- 騒音による睡眠不足やストレス
- 糞尿による悪臭・建物の腐食
- 人やペットへの健康被害
- 庭や家庭菜園の食害
具体的にどのような危険があるのか、以下でそれぞれ詳しく解説しますのでぜひご参考ください。
騒音による睡眠不足やストレス
タヌキは夜行性の動物です。
そのため、私たちが寝静まった深夜に活動を始めます。
この状態が続けば、日中の集中力低下はもちろん、深刻な精神的ストレスへと発展する恐れがあります。
糞尿による悪臭・建物の腐食
タヌキには、同じ場所にフンを繰り返す「ため糞」という習性があります。
参考:
タヌキのうんこの話|オフィシャルブログ – 東山動植物園
さらに、溜まった糞尿の水分やアンモニアは、天井のシミや建材の腐食を引き起こし、最悪の場合、天井が抜け落ちるなど家屋の資産価値を著しく低下させる原因となります。
人やペットへの健康被害
タヌキのフンや体には、人やペットに感染する病原菌や寄生虫が潜んでいる可能性があります。
特に、「ヒゼンダニ」が寄生して起こる「疥癬(かいせん)」という皮膚病は、激しいかゆみを引き起こします。
フンを処理する際や、タヌキに接近する際には、決して素手で触らないようにしてください。
参考:
疥癬(かいせん)にかかったタヌキを見つけたらどうしたらいい?(専門家が解説)
庭や家庭菜園の食害
タヌキは雑食性で、庭の果樹や家庭菜園の野菜、スイカなどを食い荒らす被害も多く報告されています。
エサ場として認識されると、繰り返し敷地内に侵入するようになり、他の害獣を呼び寄せてしまう原因にもなりかねません。
その被害、本当にタヌキ?似ている動物との見分け方

天井裏の物音や庭のフン…など。
害獣の気配を感じたとき、「タヌキかもしれない」と思う方もいらっしゃると思います。
しかし、被害をもたらす動物はタヌキだけではありません。
アライグマやハクビシンなど、よく似た動物も同じような被害を引き起こします。
対策を間違えると効果がないばかりか、法律に違反する可能性もあるため、まずは被害の原因となっている動物を正しく特定することが重要です。
タヌキが近くにいる3つのサイン
まずは、タヌキ特有の痕跡(サイン)がないかチェックしてみましょう。
| タヌキ特有のサイン | 詳細 |
| 鳴き声 | タヌキは基本的にあまり鳴きませんが、威嚇やケンカの際には「ウー」「クゥーン」といった低い声を出します。嬉しいときや楽しいときには鳴かない、感情をあまり表に出さない動物です。 |
| 足跡 | 足跡の大きさは約3~4cm。指の跡(指球)が4つと、その先に小さな爪の跡が残るのが特徴です。指が4本でない場合や、大きさが明らかに違う場合は他の動物の可能性があります。 |
| フン | 約2~3cmの楕円形で、同じ場所にフンを繰り返す「溜めフン」という習性があります。そのため、5cm以上の塊で見つかることも多いです。雑食性なので、フンの中に木の実の種や昆虫の羽などが混じっていることも特徴です。 |
写真で比較!アライグマ・アナグマ・ハクビシンとの違い

タヌキとよく間違えられる動物との違いを表にまとめました。
| 動物 | 見た目の特徴 | 足跡の特徴 |
|---|---|---|
| タヌキ | ・犬に近い丸い体つき ・目の周りの黒い模様は左右で独立 ・耳は丸い | ・指は4本 ・爪跡がつく ・サイズは約3~4cm |
| アライグマ | ・しっぽに5~7本のしま模様 ・目の周りの黒い模様はつながっている ・耳は白く縁取られ、とがっている | ・指は5本 ・爪跡がくっきりつく ・サイズは約4~5cm |
| アナグマ | ・鼻が長く、ブタに似た顔つき ・体は横に平たく、足が太い ・しっぽは短い | ・指は5本 ・長い爪跡がつく ・サイズは約4~5cm |
| ハクビシン | ・額から鼻先にかけて一本の白い線 ・胴が長く、しっぽも長い ・猫に似たしなやかな体つき | ・指は5本 ・爪跡はつかないことが多い ・サイズは約3~4cm |
特にタヌキとアライグマはよく間違える傾向があるので注意しましょう。
タヌキとアライグマの見分け方について詳しく知りたい方はこちら>>
上記の動物どれにも当てはまらないけど、家屋内で悪臭や騒音などの被害に悩まされている方はプロの害獣駆除業者へ現地調査を依頼し特定してもらいましょう。
プロの害獣駆除業者「ハウスプロテクト」では、通話料をはじめ、現地調査も無料で承っておりますのでぜひお気軽にお問い合わせください。
\相談のみOK!/
【法律違反に注意】タヌキを自分で駆除する際の3つの注意点

被害の正体がタヌキだとわかっても、すぐに行動に移すのは危険です。
自分で駆除する場合、法律や安全面で必ず守るべき注意点があります。
これらを知らないと、思わぬトラブルに発展しかねませんのでぜひご参考ください。
【注意点①】許可なく捕獲・殺傷してはいけない(鳥獣保護管理法)
最も気をつけるべき注意点は、許可なくタヌキを捕獲したり、傷つけたり、殺したりしてはいけないことです。
この法律に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
ご自身の敷地内であっても、無許可で捕獲してはいけません。
そのため、基本的には「追い出す」ことのみが許可なくできる対策だと覚えておきましょう。
【注意点②】直接触れない
タヌキは野生動物であり、どのような病原菌や寄生虫を持っているかわかりません。
フンを処理する際はもちろん、絶対に直接タヌキに触れないでください。
また、むやみに近づくことも避けましょう。
【注意点③】追い詰めると攻撃されるリスクがある
タヌキは本来臆病な動物ですが、追い詰められたり、子育て中であったりすると、自分や子どもを守るために攻撃的になることがあります。
「タヌキに攻撃されたらどうしよう…」と不安に感じる方は、タヌキ駆除の専門業者に対応してもらいましょう。
プロの害獣駆除業者は、法律に基づいた手順で対応するだけでなく、必要な装備と経験を持っているため、安全かつ確実に駆除してくれます。
害獣駆除業者「ハウスプロテクト」では、Google口コミ業界トップクラスの駆除実績を獲得しています。
通話料をはじめ、現地調査や見積もり作成もすべて無料で承っておりますのでぜひお気軽にお問い合わせください。
\相談のみOK!/
自分で行う!タヌキ駆除の具体的な3ステップ

法律や危険性を理解した上で、ご自身で「追い出し」を行う場合、具体的な手順を3つのステップで解説します。
重要なのは、追い出した後に「二度と入らせない」対策を徹底することです。
以下でそれぞれ解説します。
【手順①】家・敷地から追い出す
まずは、タヌキが嫌がるニオイや光、音を使って家や敷地から追い出します。
具体的な追い出し方法を以下にまとめました。
| 追い出し方法 | 詳細 |
| ニオイ | 木酢液や竹酢液、ハッカ油などの強いニオイを布に染み込ませて置いたり、市販の忌避剤を設置したりするのが効果的です。屋根裏などの閉鎖空間では、害虫駆除用のくん煙剤(バルサンなど)も有効です。 |
| 光 | 夜行性のタヌキは強い光を嫌います。使っていない屋根裏などで、点滅するLEDライト(クリスマス用のイルミネーションなど)を設置すると効果が期待できます。 |
| 音 | タヌキが嫌がる超音波を発生させる装置も市販されています。 |
【手順②】二度と入れないように侵入経路を徹底的に塞ぐ
追い出しに成功したら、時間を置かずにすべての侵入経路を物理的に塞ぎます。
なぜなら、タヌキは帰巣本能が強く、一度塞いでも諦めずに他の隙間から侵入してくるからです。
| 主な侵入経路 | ・床下の通気口 ・壁のひび割れ ・屋根の隙間 ・戸袋 |
| 塞ぐための道具 | ・パンチングメタル ・金網 ・ワイヤーメッシュ |
上記を参考に、家中の隙間を徹底的にチェックして塞ぎましょう。
【手順③】フンを清掃・消毒し、被害の痕跡を消す
最後に、タヌキが残したフンや尿をきれいに清掃・消毒します。
清掃時に準備するものや清掃の手順を以下にまとめましたのでぜひご参考ください。
| 準備するもの | マスク、ゴーグル、ゴム手袋、長袖の服を必ず着用し、肌の露出を避けてください。 |
| 清掃の手順 | フンをほうきとちりとりで取り除き、次亜塩素酸ナトリウム系の消毒液やエタノールなどでフンのあった場所をしっかりと拭き上げ、消毒します。 |
二度と寄せ付けない!タヌキ被害の根本的な再発防止策
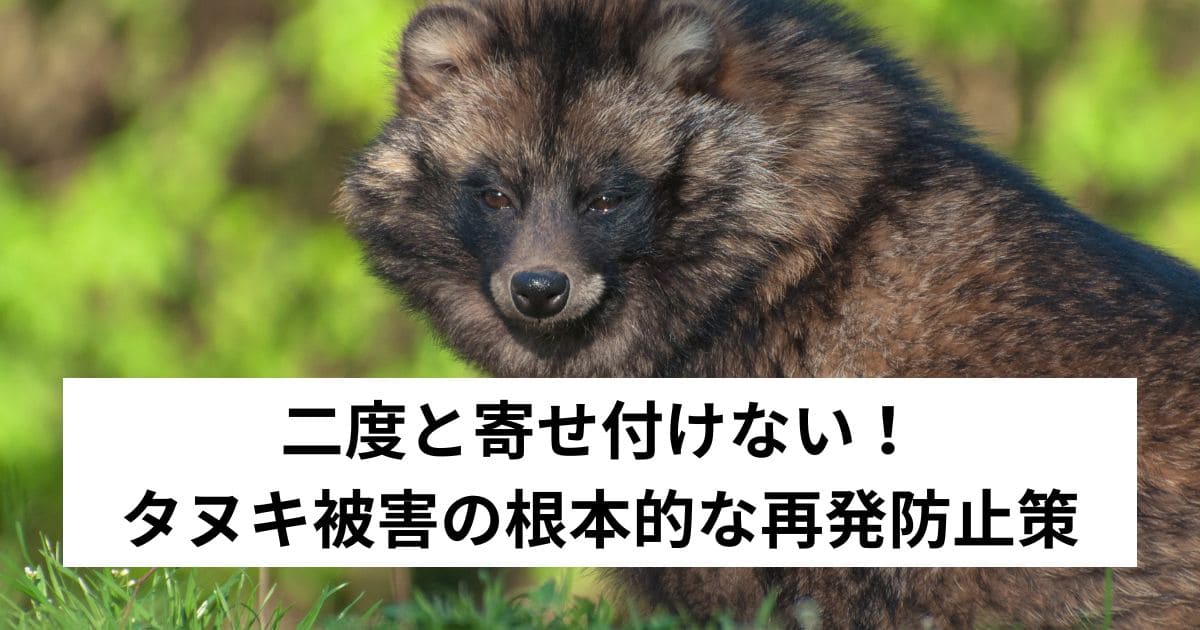
一度タヌキを追い出しても、そこが「住みやすい場所」である限り、再び戻ってきてしまう可能性があります。
被害の再発を防ぐためには、タヌキにとって魅力のない環境を作ることが不可欠です。
エサになるものを徹底的に管理する
タヌキを寄せ付けないための最も重要な対策は、「エサを与えない」ことです。
具体的な対策を以下にまとめました。
| 対策 | 詳細 |
| 生ゴミの管理 | ゴミは収集日の朝に出すことを徹底しましょう。蓋付きのポリバケツに入れるなど、簡単に荒らされない工夫も有効です。 |
| ペットフードの管理 | 屋外でペットを飼っている場合、エサの残りを放置しないようにしてください。ペットフードの香りはタヌキにとって非常に魅力的です。室内で保管する場合も、密閉容器に入れましょう。 |
| 庭の果実 | 収穫しない果物は、そのまま放置せず早めに処分しましょう。地面に落ちた果実もタヌキのエサになります。 |
庭木を剪定し、隠れ家をなくす
タヌキは警戒心が強く、身を隠せる場所を好みます。
具体的な対策は以下のとおりです。
| 対策 | 詳細 |
| 庭木や雑草の手入れ | 庭木が鬱蒼と茂っていたり、雑草が生い茂っていたりすると、タヌキの絶好の隠れ場所になります。定期的に剪定や草むしりを行い、見通しの良い環境を保ちましょう。 |
| 縁の下や物置の確認 | 使っていない物置や、家の縁の下などもタヌキが巣作りしやすい場所です。侵入できそうな隙間があれば、金網などで塞ぎましょう。 |
タヌキ駆除にかかる費用|DIYと業者の比較

タヌキ駆除を考えたとき、多くの方が気になるのが費用でしょう。
ここでは、ご自身で対策する場合(DIY)と、プロの業者に依頼する場合の費用やメリット・デメリットを比較します。
自分で駆除する場合の費用とリスク
ご自身で駆除を行う場合、費用は忌避剤や金網など、数千円~数万円ほどの材料費がかかります。
これらはプロの害獣駆除業者に依頼する場合と比べ、コストを抑えられるのが最大のメリットですが、以下のようなリスクやデメリットも伴います。
- 追い出しや侵入経路の封鎖が不完全で被害が再発する可能性がある。
- 高所での作業や、タヌキに遭遇した際に怪我をする危険性がある。
- 清掃や消毒が不十分で、衛生的な問題が残る可能性がある。
プロの害獣駆除業者に依頼する場合の費用とメリット
プロに依頼する場合の費用相場は、被害状況や建物の構造によって異なりますが、一般的に5万円~30万円程度です。
自力で駆除する場合と比べると費用はかかりますが、それを上回る大きなメリットがあります。
- 専門的な知識と技術で、被害の根本原因から確実に駆除してくれる。
- 駆除から清掃・消毒、再発防止策まで一貫して任せられるため、安全で手間がかからない。
- 多くの業者では再発保証を設けており、万が一の際も安心できる。
費用だけで判断せず、確実性や安全性を考慮して、信頼できる業者に相談することをお勧めします。
また複数の業者から事前に相見積もりを取り、サービス内容や料金に納得したうえで依頼することで、安心して駆除を任せられます。
プロの害獣駆除業者「ハウスプロテクト」では、通話料をはじめ、現地調査や見積もり作成もすべて無料で承っておりますのでぜひお気軽にお問い合わせください。
\相談のみOK!/
タヌキ駆除はプロの害獣駆除業者への相談が確実!
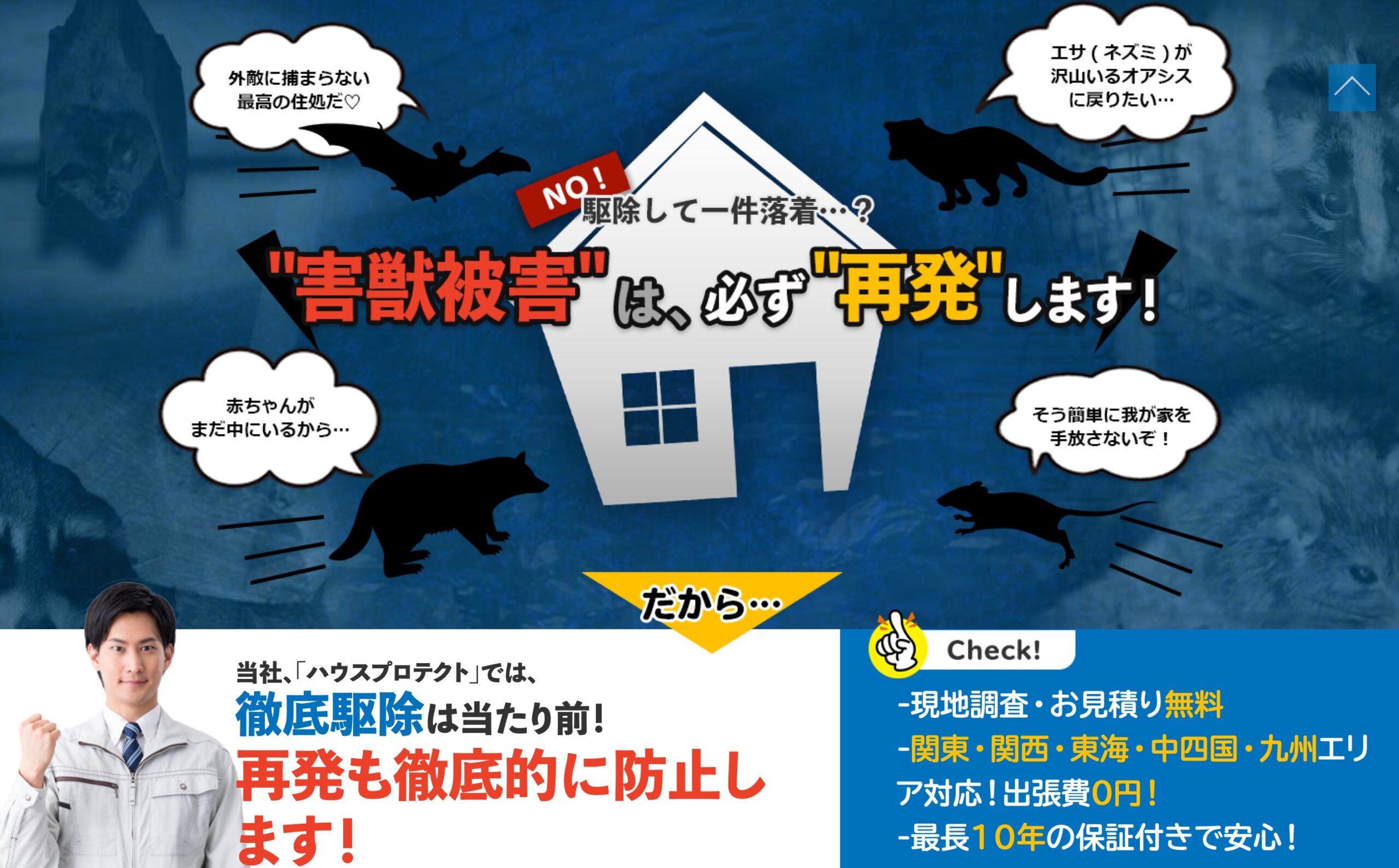
タヌキは一度追い払っても、再び戻ってきてしまう帰巣本能の強い生き物です。
そのため、タヌキ駆除は安全かつ確実な方法で対処しなければなりません。
しかし、「どの業者に頼めばいいかわからない…」「費用が心配…」という方も多いのではないでしょうか?
プロの害獣駆除業者「ハウスプロテクト」では、再発防止を徹底し、タヌキを駆除するプロフェッショナルです。
Google口コミ評価で業界トップクラスの実績があるため、初めて駆除依頼する方におすすめの業者といえます。
そんなハウスプロテクトをおすすめする主な3つの理由は下記のとおりです。
- 侵入口の封鎖など再発予防を徹底して行う
- 最長10年間の無料保証が付いている
- ご相談・現地調査・お見積もりまですべて無料
「タヌキを身近で見かけて不安を感じている」「すでに被害が発生し困っている」という方は、ぜひ一度ハウスプロテクトにご相談ください!
ハウスプロテクトのリアルな口コミ・評判を知りたい方はこちら>>
\相談のみOK!/
タヌキ駆除に関するよくある質問【Q&A】
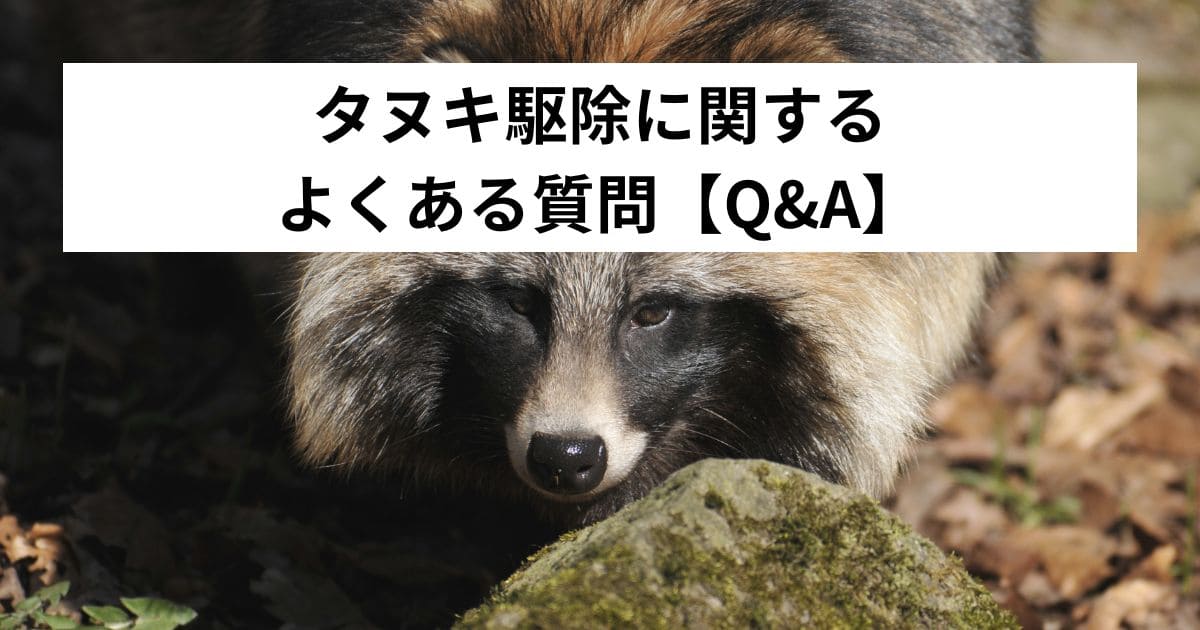
ここでは、タヌキ駆除に関する次の3つの疑問についてお答えします。
- 威嚇してきたり、攻撃してきたりしますか?
- 自治体は駆除してくれますか?補助金はありますか?
- 屋根裏で赤ちゃんを産んでいるようなのですが、どうすればいいですか?
上記と同じ質問をお持ちの方はもちろん、似ている疑問を抱えている方はぜひご確認ください。
以下でそれぞれ解説します。
威嚇してきたり、攻撃してきたりしますか?
基本的にタヌキは臆病な性格のため、人間と遭遇すると自ら逃げていくことがほとんどです。
しかし、追い詰められたり、子育て中で神経質になっていたりする場合には、自分や子どもを守るために威嚇したり、攻撃してきたりする可能性もゼロではありません。
むやみに近づいたり、刺激したりしないようにしましょう。
自治体は駆除してくれますか?補助金はありますか?
結論から言うと、ほとんどの自治体で個人の敷地内のタヌキを直接駆除してくれることはありません。
自治体の対応は、主に以下のような支援にとどまります。
- 被害に関する相談対応やアドバイス
- 専門の駆除業者の紹介
- 捕獲器の貸し出し ※
害獣駆除に関する補助金制度も、その多くが農作物への被害を対象としており、個人の住宅を対象とするケースは稀です。
まずは、環境課や農政課などお住まいの自治体の役所に問い合わせて、どのような支援が受けられるか確認してみましょう。
屋根裏で赤ちゃんを産んでいるようなのですが、どうすればいいですか?
春から夏にかけてはタヌキの繁殖期にあたり、屋根裏で出産するケースも少なくありません。
子育て中の親ダヌキは非常に警戒心が強く、攻撃的になることがあるため、ご自身で対処するのは大変危険です。
また鳥獣保護管理法により、許可なく捕獲してはいけません。
そのため、タヌキがいる場合は、絶対に手を出さず、速やかにプロの害獣駆除業者に相談しましょう。
まとめ
タヌキ駆除は、まず家や敷地から追い出し、侵入経路を封鎖し、その後に清掃を行うという流れで進めるのが基本です。
しかし、タヌキは帰巣本能が強く、確実に駆除しないと再び戻ってきて被害を繰り返す可能性があります。
タヌキによる被害は、農作物を食い荒らすだけでなく、騒音や悪臭、健康被害など多岐にわたります。
愛らしい見た目に油断せず、早急に対応することが大切です。
被害を根本的に解決し、再発を防ぐためには、プロの害獣駆除業者に依頼するのがおすすめです。
Googleクチコミ業界トップクラス「ハウスプロテクト」では、駆除をはじめ、再発させない施工に定評があります。
通話料をはじめ、現地調査や見積もり作成もすべて無料で承っておりますのでぜひお気軽にお問い合わせください。
\お問い合わせフォーム入力は1分で完了/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。