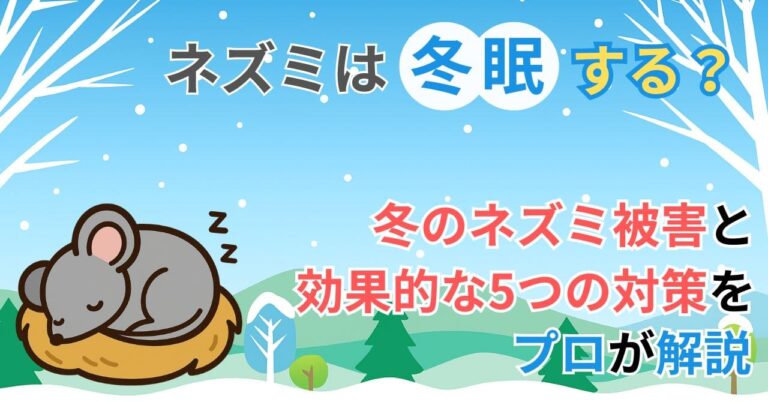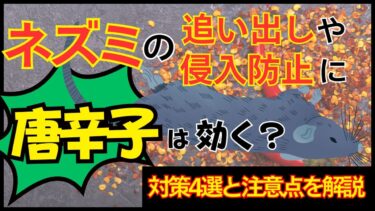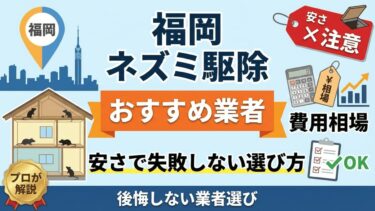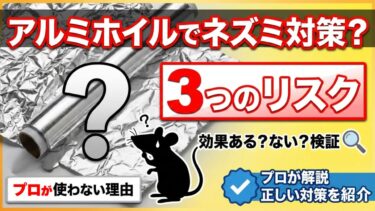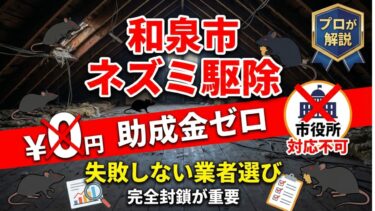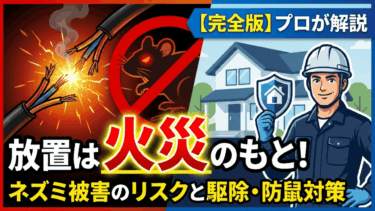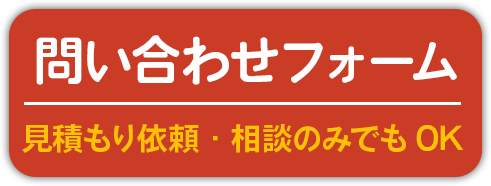冬になると、ネズミは冬眠すると思い、安心していませんか?
実は、家の中に侵入してくるネズミは冬眠しません。それどころか、冬になると暖かく、エサのある場所を求めて、積極的に建物へ侵入してきます。
また屋根裏や床下に巣を作り、春先に一機に繁殖して被害が拡大する恐れがあります。
さらに冬場は、ネズミが電気配線をかじり、漏電火災のリスクが飛躍的に高まるため早めに駆除した方が良いでしょう。
そこで本記事では、ネズミが冬眠しない理由をはじめ、冬にいなくなったと感じる理由や被害例を害獣駆除のプロが解説!
冬に駆除すべき理由や行うべき5つの対策も分かりやすく解説してまいりますので、ぜひ参考にしてみてください。
春先にネズミ被害に困らないよう冬の間に対策しておきましょう!
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
ネズミが冬眠しない理由

私たちの住宅に侵入し、様々な被害をもたらす家ネズミ(イエネズミ)は、一切冬眠しません。
ちなみに家ネズミは、次の3種類を指します。
- ドブネズミ
- クマネズミ
- ハツカネズミ
これらの家ネズミが冬眠しない理由は、住宅のように暖かい環境で年中活動できるからです。
ネズミは寒さや飢えに弱く、冬を越すのが苦手な動物です。そのため、寒くなるとエサのある暖かい場所を求めて、建物に侵入してきます。
特にクマネズミは寒さに弱いため、屋根裏や天井といった高所へ侵入してくる傾向があります。
実際、秋から冬にかけてクマネズミによる被害数は増えているので注意しなければなりません。
参考:東京都保健医療局|令和4年度ねずみ・衛生害虫等被害発生・相談件数
冬にネズミがいなくなったと感じる理由
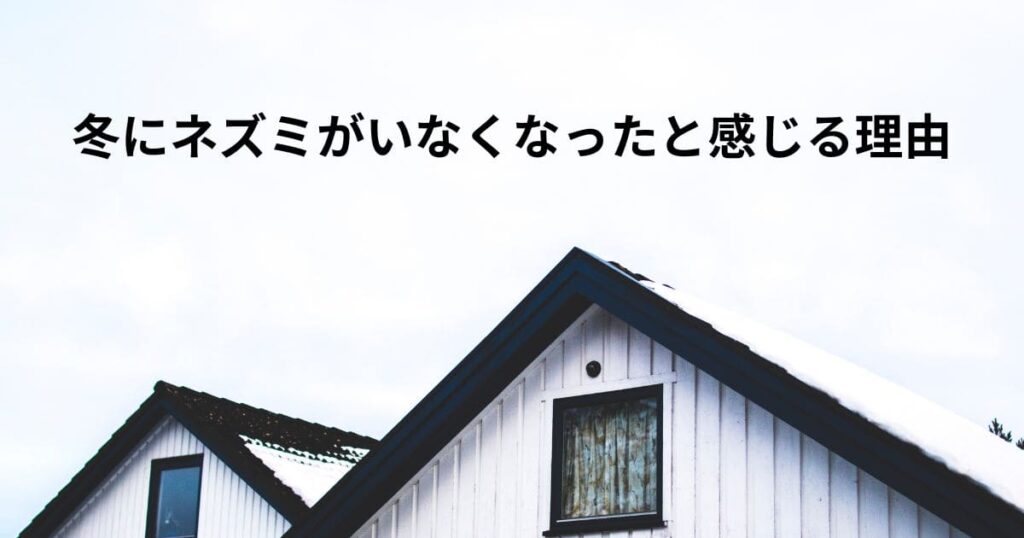
家に住み着くネズミは冬眠しないため、一年中、人や建物に被害をもたらす害獣です。
そんなネズミが冬にいなくなったと感じる場合、次の4つが考えられます。
- 寒さで活動が鈍くなった
- エサが無くて死んでしまった
- 他の害獣に捕食された
- 別の場所に移動した
ネズミの気配がなくなっても水面下で被害が悪化している可能性もあるので油断は禁物です。
以下で詳しく見ていきましょう!
理由1:寒さで活動が鈍くなった
ネズミは寒さに弱く、10℃を下回ると活動量が少なくなります。
これまで走り回っていた音が聞こえなくなり、「いなくなった」と錯覚してしまうかもしれませんが、これは一時的な活動低下に過ぎません。
実際には、暖房配管の近くや断熱材の中、電化製品の裏などに移動して体力を温存している可能性があります。
また気配がなくても、フンや尿をし、住宅を汚していることも考えられます。
理由2:エサが無くて死んでしまった
ネズミは、1日に自分の体重の3分の1から4分の1のエサを必要とします。
エサがなくなると、寒い時期には1日、暖かい時期でも4~5日程度で餓死してしまいます。
ネズミは雑食性ですが、冬は昆虫や植物の実などエサが減るため、命を落とす個体も少なくありません。
天井裏や壁の中など、人の目が届かない場所で死んでしまった場合、その死骸が腐敗し、強烈な悪臭やウジ虫などの害虫を発生させる二次被害につながる恐れがあり、より深刻な状況を招きます。
理由3:他の害獣に捕食された
イタチ、ヘビ、フクロウといったネズミの天敵となる動物が家に侵入し、ネズミを捕食したことで静かになる可能性もゼロではありません。
しかし、これは「ネズミがいなくなった代わりに、別の大型の害獣が住み着いた」という、さらに厄介な状況に陥ったことを意味します。
イタチなどの害獣は、ネズミ以上の騒音やフン尿による悪臭、建物の破壊といった甚大な被害をもたらす可能性があります。
問題が解決するどころか、より複雑化してしまったケースと言えるでしょう。
「冬のイタチ対策を知りたい!」という方は以下の記事を参考にしてみて下さい。
近年、イタチが原因による、住宅の被害が報告されています。 イタチは、フェレットに似た可愛い見た目とは異なり、とても凶暴な害獣です。また、イタチは帰巣本能が強く、鳥獣保護管理法により保護されているため、無許可での捕獲・駆除は禁止されてい[…]
理由4:別の場所に移動した
「一時的にエサがなくなった」あるいは「天敵が現れた」といった理由で、ネズミはより快適な環境を求めて移動することもあります。
しかしネズミは、一度安全だと認識した場所には、再び戻ってくる可能性が非常に高いです。
また、移動したのは群れの一部だけで、巣には子ネズミが残っているケースも少なくありません。
ネズミが別の場所に移動しても、侵入経路が塞がれていない限り、被害は再発する可能性が高いです。
冬眠しないネズミが引き起こす冬の被害

家ネズミは冬眠しないため、冬場に対策しないと被害が拡大する恐れがあります。
主な被害は以下の通りです。
| ネズミの被害 | 詳細 |
| 精神的被害 | ・ネズミの足音や物音による不快感 ・夜間の騒音による不眠 |
| 衛生的被害 | ・ネズミに噛まれることで感染する鼠咬症(そこうしょう) ・フンや尿を介した食中毒などの感染症 ・ネズミに寄生するダニやノミが媒介する感染症(ツツガムシ病など) |
| 経済的被害 | ・衣類や家具など家財のかじり被害 ・貯蔵している食品の食害 ・住宅設備の破損 ・家庭菜園などへの食害 |
これらの被害の中で、特に注意が必要なのが住宅設備の破損です。
ネズミが屋根裏や壁の内部に侵入し、ガス管や電気配線をかじることで損傷させ、漏電による火災といった重大な事故につながる危険があります。
特に冬の時期は空気が乾燥しているため、火事が起こりやすい傾向があります。
参考:ネズミが配線をかじって漏電し火事に ネズミ被害の対策を聞く
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
冬にネズミがいるか確かめる方法
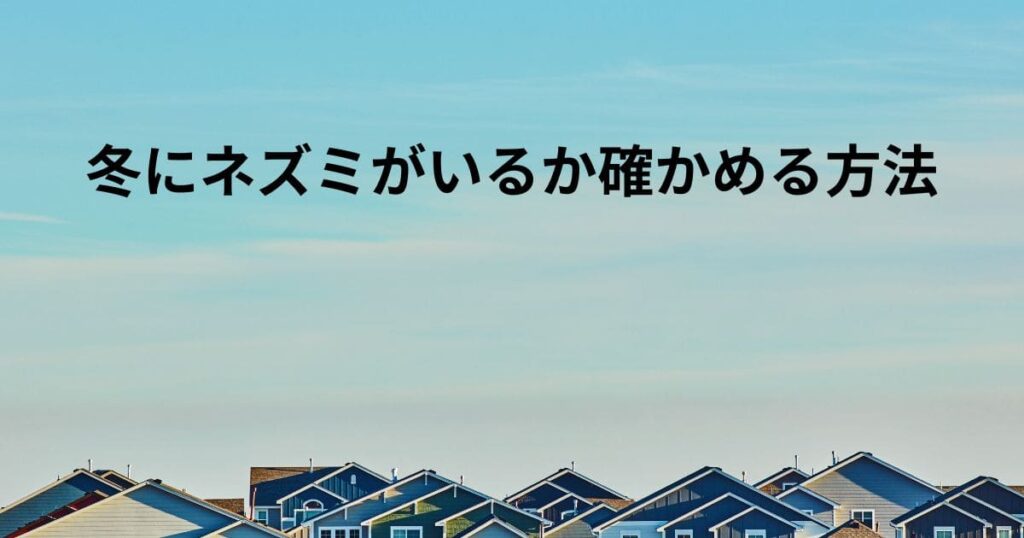
物音がしなくなった冬の時期だからこそ、本当にネズミがいなくなったのか、それともまだ潜んでいるのかを確かめる必要があります
特にネズミは警戒心が強いため、人が活動している時間帯に姿を見せません。
しかし、ネズミは必ず「ラットサイン」と呼ばれる痕跡を残します。
以下では、代表的な3つのラットサインを紹介しますので、ご自宅の中にないか確認してみましょう。
フンがある
ネズミがいる最も確実な証拠がフンです。
ネズミは移動しながらフンをする習性があるため、通り道や巣の近くには必ずフンが落ちています。
家ネズミが落とすフンの特徴は以下の通りです。
| 家ネズミの種類 | フンの特徴・大きさ | 好む場所 |
| クマネズミ | ・6~10mm程度 ・細長く、広範囲に散らばっている | 天井裏 |
| ドブネズミ | ・10~20mm程度 ・太く丸みがあり、一箇所にまとまっていることが多い | 湿った場所 |
| ハツカネズミ | ・4~7mm程度 ・米粒ほどで両端が尖っている。 | 物置など |
黒くてツヤがあるフンがあれば、まだ日が新しいため、住宅の中で間違いなく活動しています。
具体的には、次のような場所に落ちている傾向があります。
- キッチンの隅
- 冷蔵庫や棚の裏
- シンクの下
- 天井裏
- 床下収納
- 配管の周り など
フンを見つけた場合は、決して触ってはいけません。
なぜなら、ネズミのフンにはサルモネラ菌などの病原菌が含まれているため、健康被害に遭うリスクがあるからです。
ネズミのフンを掃除する際は、必ず手袋やマスクを着け、直接触れないよう注意しましょう。
家の中にネズミのフンのようなものを見つけたら、本当にネズミのフンなのか気になりますよね。 ネズミのフンだと思っていても、実は違う動物のフンの場合もあるかもしれません。 また、フンには病原菌などが潜んでいるおそれもゼロではなく、正[…]
黒く擦った跡がある
ネズミの体は油とホコリで汚れており、何度も同じ場所を通ることで壁や柱に黒い汚れの跡を残します。
これを専門用語で「ラットサイン」と呼びます。
次のような部分に手でこすったような、線状の黒い汚れがないか確認してみてください。
- 壁
- 柱の角
- 配管の近く
この跡が濃く残っている場所は、頻繁にネズミが通っている証拠といえます。
自宅の天井の四隅や通気口の側などをよく見ると、その部分が黒ずんでいることがあります。 一見すると、風の通り道やホコリやで汚れていると思うかもしれませんが、ネズミが棲み着いている痕跡である「ラットサイン」の可能性もあります。 もしラット[…]
かじった跡がある
ネズミの歯は一生伸び続けるため、常に硬いものをかじって歯を削る習性があります。
家の中でかじり跡がないか確認しましょう。
代表的なかじり跡がある箇所は以下の通りです。
- 柱
- 壁
- 家具
- 食品の袋
- 石鹸
- 電気コード
- ガスホース
特に注意が必要なのが電気コードやガスホースです。
配線類のかじり跡は、漏電による火災のリスクに直結するため、非常に危険なサインと言えます。
冬眠しないネズミを冬に駆除すべき4つの理由

冬になりネズミの気配が消えると、被害が落ち着いたと安心してしまいがちです。
しかし、ネズミを放置したまま春を迎えると、繁殖期に入ってしまい、被害が手に負えなくなる可能性があります。
以下では、冬のうちにネズミを駆除すべき4つの理由を、分かりやすく解説していきます。
理由1:火災が発生しやすいから
冬は暖房器具の使用により、家庭での電力消費量が多くなる季節です。
そんな電気系統に負荷がかかっている状況で、もしネズミが電気コードをかじり、銅線を露出させていたらどうなるでしょうか。
そこにホコリが溜まれば、発火する危険性が飛躍的に高まります。
さらに空気が乾燥している冬は、一度火が出ると燃え広がりやすく、大惨事につながりかねません。
理由2:春になると爆発的に繁殖するから
ネズミの繁殖力は凄まじく、1回に5~10匹もの子どもを産みます。さらに、生まれた子ネズミは生後3~4か月で繁殖できます。
冬の間に家屋に侵入した、つがいのネズミを放置すると、春までに数十匹の子ネズミが生まれ、被害が爆発的に拡大します。
繁殖のピークは春(3〜5月)と秋(10〜11月)で、特に春先は被害が広がりやすい時期です。
そのため、冬の寒い時期に駆除しておくことは、春と秋の繁殖シーズンの被害を未然に防ぐことができるでしょう。
理由3:罠にかかりやすいから
冬は屋外の食料が枯渇し、ネズミは常に飢えています。
エサに飢えたネズミは、普段なら警戒して近寄らないような毒餌や罠に仕掛けたエサにも空腹に耐えかねて食いつきやすくなるのです。
特にキッチンや食品を保管している倉庫、ゴミ置き場などに粘着シートや捕獲カゴ、毒餌といった罠を仕掛けることで、効果的に駆除・捕獲しやすくなるでしょう。
理由4:死骸が腐敗しにくいから
万が一、毒餌を食べたネズミが壁の中や天井裏など、目の届かない場所で死んでしまった場合、夏場であれば死骸は数日で腐敗し、強烈な悪臭とウジ虫などの害虫を発生させます。
しかし、気温の低い冬であれば、腐敗の進行が比較的緩やかです。
悪臭や衛生被害のリスクを減らせるのは、冬にネズミを駆除する大きなメリットといえるでしょう。
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
自力で行える冬のネズミ対策は5つ

ネズミの活動量が落ちている冬こそ、効果的にネズミを駆除できる時期です。
春以降にネズミの被害を大きくしないためにも、冬のうちにできる5つの対策を解説します。
まずは自分で対策してみたい方はぜひ参考にしてみてください。
対策1:食料品を管理する
ネズミは雑食性の害獣であり、人間の食べ物のほとんどをエサにします。そのため、キッチンやリビングに食品が放置されていると、そのニオイに誘われて家屋に侵入してくる可能性があります。
ビニール袋や紙の箱は容易に食い破られるため、食材の保管にはガラスや硬質プラスチック製の密閉容器を使用することをおすすめします。
また、ペットフードやお仏壇のお供え物を放置しない、生ゴミを室内にため込まない、といった基本的な対策も徹底することも重要です。
対策2:毒餌・粘着シートを設置する
市販の毒餌や粘着シートは、個人で行える駆除方法の一つです。
毒餌には「即効性タイプ」と「遅効性タイプ」があります。
どちらを使用する場合も、子どもやペットが誤って口にしないよう設置場所には注意しましょう。
一方、粘着シートは、ネズミが通りそうな壁際や物陰に複数枚を設置することで捕獲率を高めます。
捕獲したネズミの死骸は不衛生なため、放置せずに処分してください。
また死骸には病原菌が付着している可能性があるため、処理の際は必ずゴム手袋を着用し、速やかに行いましょう。
どちらも生きているネズミや死骸をご自身で処分しなければならないため、かわいそうに感じる方にはおすすめできません。
対策3:忌避剤で追い出す
忌避剤は、ネズミが嫌がるニオイを利用して家の中から追い出す方法です。
主なタイプと特徴は以下の通りです。
| 忌避剤のタイプ | 特徴 |
| スプレータイプ | ネズミの通り道や侵入口に直接吹きかけて使用します。即効性があるのが特徴です。 |
| くん煙タイプ | 煙を部屋全体に行き渡らせることで、物陰に隠れたネズミを追い出します。 |
| 設置タイプ | 特定の場所に置くことで、効果が一定期間持続します |
ただし、忌避剤の効果は長続きせず、ニオイに慣れてしまうと再び戻ってくるため、根本的な解決にはなりません。
そのため、他の対策と組み合わせる補助的な手段と考えましょう。
対策4:巣材を撤去する
ネズミは巣を作るために、様々な材料を集めます。
そのため、巣の材料となりそうなものをなくすことでネズミが住み着きにくい環境が作れます。
巣材を撤去する方法は以下の通りです。
室内を整理する
押し入れや物置に長期間保管している新聞紙、布、ビニール、段ボールなどは、ネズミの巣材になります。
不要なものは処分し、室内を整理しましょう。
巣を撤去する
ネズミの巣を発見した場合、病原菌が付着している可能性があるため、安全に注意して処分しなければなりません。
巣を撤去する際は、必ずマスクとゴム手袋を着用し、巣をビニール袋で密閉してから可燃ゴミとして処分してください。
作業後は、巣があった場所の周辺をアルコールなどで消毒しましょう。
対策5:侵入口・経路を封鎖する
ネズミは、わずかな隙間があれば建物に侵入できます。
子ネズミの場合、1.5cm〜2cm程度、大人のネズミでも2.5cm程度の隙間があれば侵入できるため、ネズミの被害に再び遭わないためには、侵入経路を徹底的に封鎖しなければなりません。
代表的な侵入経路は以下の通りです。
- エアコンの配管周り
- 換気扇
- 建物の亀裂
- 通気口 など
これらの箇所を点検し、家屋内外の隙間が侵入経路になっていないか確認してみてください。
侵入経路を発見した隙間は、金網や防鼠パテなどネズミがかじって壊すことができない素材で塞ぐ必要があります。
ただし、侵入経路の封鎖は、建物内のネズミを完全に駆除した後に行ってください。
なぜなら、先に塞いでしまうと、ネズミを屋内に閉じ込めてしまうからです。
自力で冬のネズミ対策を完璧に行うのは難しい
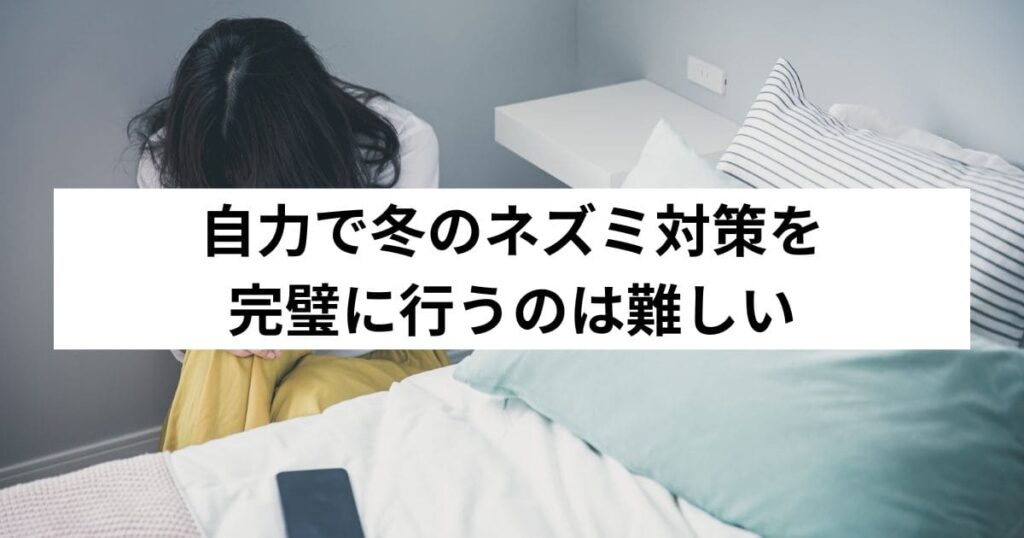
ここまで自力での対策方法を解説してきましたが、一般の方がネズミを完全に駆除し、被害の再発を防ぐのは極めて困難です。
以下で詳しく説明しますので、自力でネズミ対策を検討している方はぜひ確認してみてください。
侵入経路をすべて特定できない
ネズミは、建物のあらゆる隙間から侵入してきます。
主な侵入経路は以下の通りです。
- 配管の隙間
- 屋根裏
- 通気口
- エアコンの配管穴
- 戸袋
- 壁や屋根の隙間
- 床下 など
これらの高所や狭い場所を点検する場合、専門知識がなければ確認すらできない箇所が無数に存在します。
目立つ隙間をいくつか塞ぐだけでは不十分であり、ネズミは別の経路を見つけて再び侵入します。
建物の構造を熟知した専門家でなければ、すべての侵入経路を特定し、完全に封鎖することは極めて困難です。
健康被害に遭う可能性がある
ネズミのフンや尿、そして死骸には様々な病原菌や寄生虫が潜んでいます。
知識のないまま清掃や処分作業を行うと、フンを乾燥させて菌を空気中に飛散させてしまったり、ダニに刺されたりして、「サルモネラ症」や「ハンタウイルス感染症」といった深刻な健康被害に遭う危険があります。
これらの健康被害に遭う可能性があるため、自力でネズミ対策を行うのは避けたほうが良いでしょう。
冬のネズミ駆除はハウスプロテクトに相談してみよう!
「ハウスプロテクト」では、まずネズミの巣や侵入経路を特定し、独自開発の人体に無害な薬剤でネズミを完全に追い出します。
またリフォーム会社が母体となっているため、住宅の資産価値を落とさない施工を行うことも可能です。
さらに最長10年以上の保証期間を設けているので、万が一、被害が再発した場合は無償で対応するアフターフォローも用意しています。
実際にGoogleクチコミ評価では、業界トップクラスの高評価をいただいているため、安心して相談できる専門業者と言えるでしょう!
相談はもちろん、現地調査や見積もり作成は無料で行っており、専門スタッフが状況に合わせた最適なプランを提案します。
どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
実際にハウスプロテクトを利用した方々の口コミ・評判が気になる方はこちら>>
冬のネズミ対策によくある質問【Q&A】

こちらでは、冬のネズミ対策によくある質問に回答してまいります。
- ネズミは寒さに弱いですか?
- ネズミは寒くなるとどうなりますか?
- 北海道のような寒い地域でもネズミは出ますか?
- 業者に依頼すると、費用はどれくらいかかりますか?
気になる質問がある方はぜひご確認ください。
以下で1つずつ回答していきます。
Q1. ネズミは寒さに弱いですか?
A1. はい、寒さ自体は苦手です。
だからこそ、寒さをしのぐために暖かく、エサも豊富な人間の家に侵入してきます。
家の中はネズミにとって快適な環境なため、冬でも活動が鈍ることはありません。
Q2. ネズミは寒くなるとどうなりますか?
A2. 屋外のネズミは活動が鈍ったり、別の場所に移動したりしますが、家の中に侵入したネズミは、暖房の効いた快適な環境で活発に活動を続けます。
特に天井裏や壁の中など、暖かい巣で繁殖活動を行うため、冬に被害が拡大するケースが多く見られます。
Q3. 北海道のような寒い地域でもネズミは出ますか?
A3. はい、地域に関係なく発生します。
北海道のように冬の寒さが厳しい地域ほど、ネズミは越冬のために住宅へ侵入する傾向が強くなります。
断熱材が豊富な現代の住宅は、ネズミにとって格好の隠れ家となるため、冬の時期も油断できません。
Q4. 業者に依頼すると、費用はどれくらいかかりますか?
A4. ネズミの駆除費用は、被害の状況、建物の構造、駆除・施工の範囲によって費用は変動します。
そのため、必ず現地調査を行った上で納得いく詳細なお見積もりを提示してくれる専門業者に相談しましょう。
また現地調査や見積もり作成は無料で行ってくれる業者に依頼することをおすすめします。
まとめ
今回は、冬のネズミの生態と危険性、そして正しい対策について解説しました。
家ネズミは冬眠せず、冬にこそ家屋への侵入と活動が活発になります。
特に冬は火災リスクが高まる一方、駆除には最適な時期でもあります。
しかし、自力での対策には限界があり、健康リスクや再発の可能性が残るため、ネズミを完全に駆除し、安心して暮らせる生活を取り戻すには、プロによる侵入経路の徹底封鎖が不可欠です。
冬に活動量が落ちているネズミは、春の大量繁殖に向けた準備を着々と進めている可能性があります。
被害が手遅れになり、多大な修繕費用や健康被害に悩まされる前に、まずは一度、プロの専門業者に相談してみてください。
「ハウスプロテクト」では、相談をはじめ、現地調査や見積もり作成もすべて無料で承っております。
些細な相談事でもかまいませんので、お気軽にお問い合わせください。
ハウスプロテクトが安心して生活できる日々を取り戻すためにサポートします!
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。