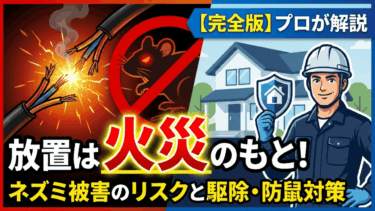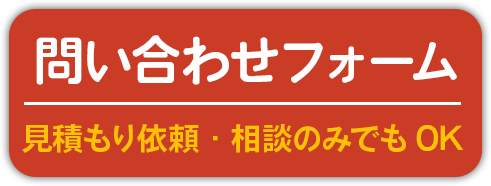ネズミは放置すると被害が広がりやすく、家屋の損壊や衛生面のリスクが高まります。
しかし、「どんな駆除剤を選べばいいのか」「殺鼠剤と忌避剤はどう違うのか」といった疑問を感じる方も多いでしょう。
本記事では、ネズミの駆除剤について特徴や効果的な使い方を詳しく解説します。
さらに、再発防止のためのポイントも紹介します。
ネズミ被害でお悩みの方や、今まさに駆除を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。
ネズミの駆除剤について基本を知ろう

ここでは、ネズミ駆除剤と呼ばれる製品の種類や、そもそも駆除剤で何ができるのかを解説します。
殺鼠剤や忌避剤など、名称や成分もいろいろあり、初めての方には分かりづらい部分があるかもしれません。
まずは基礎を押さえておきましょう。
ネズミ用の駆除剤とは?
ネズミ駆除剤とは、文字通りネズミを駆除する目的で使われる製品を指します。
大きく分けると、毒エサタイプの「殺鼠剤」と、ネズミが嫌がる匂いや成分で追い払う「忌避剤」の二種類があります。
殺鼠剤は、ネズミに食べさせることで内臓出血などを起こし、最終的に駆除を目指す方法です。
一方、忌避剤はネズミをその場から退散させたり、侵入を抑制したりする仕組みをもつ薬剤になります。
どちらも市販で手に入れやすく、ドラッグストアやホームセンター、ネット通販などで購入できるため、個人で簡単に導入できるメリットがあります。
ただし、ネズミの被害状況や生息場所によって効果が異なるため、正しい製品選びと配置が大切です。
駆除剤の種類と特徴
ネズミに効く駆除剤には、大きく「殺鼠剤」と「忌避剤」があります。
殺鼠剤
ワルファリンなどの抗凝血成分を含み、ネズミが数日かけて体内に毒を溜め込み、最終的に致死量に達するタイプが一般的です。
- メリット:繁殖力の高いネズミを確実に減らしやすい。
- デメリット:ネズミが死ぬ場所を特定しづらく、屋根裏や壁の中で死骸が放置され悪臭の原因になるリスクがあります。
忌避剤
匂い型はハッカやハーブ、唐辛子成分を利用して、ネズミにとって不快な臭いを出します。
超音波型はネズミが嫌がる周波数の音を発する装置もあります。
- 利点:ネズミを殺さずに追い出せるため、死骸処理の必要がありません。
- 欠点:根本的に住み着いたネズミには効きにくく、効果が一時的な場合も多いです。
どちらも一長一短があるため、状況や目的に応じて使い分けることが重要です。
参考:名古屋市「ネズミ -家の中でみかけたことはありませんか-」
駆除剤の正しい使い方と選び方

この章では、殺鼠剤や忌避剤を使う際に押さえておきたいポイントを解説します。
効率良く効果を発揮させるには、ネズミの行動特性や設置場所のコツを知ることが大切です。
あわせて、使用時の注意点や安全対策についても触れていきます。
殺鼠剤を使う際の注意点
殺鼠剤は、ネズミを直接駆除するための強力な手段です。
しかし、子供やペットが誤って口にしないよう、十分な配慮が必要となります。
- 設置場所:ネズミの通り道となる壁際や隅、物陰などに少量ずつ置きましょう。
- 補充頻度:数日経っても食べられていない場合は場所を変えたり、エサを交換することを検討します。
- 死骸処理:ネズミがどこで死ぬか分からないため、悪臭やハエの発生を招くリスクがあります。
死骸を見つけたら、ゴム手袋やマスクを装着し、一般ごみとして袋二重などでしっかり密封してください。
忌避剤を使う際の注意点
忌避剤は、「追い出す・寄せ付けない」方法です。
殺鼠剤のようにネズミを殺さないため、死骸処理の手間がなく、小さなお子様がいる家庭で人気があります。
- 匂い型:粒状タイプやスプレータイプなどさまざまです。
粒状タイプは置くだけなので簡単ですが、ネズミが慣れると効果が薄れることもあります。 - 超音波型:置くだけで稼働し続けますが、壁や家具が音を遮ると効果範囲が限られます。
また、一度住み着いたネズミには忌避剤だけでは十分な効果を得られないケースもあるため、侵入口の封鎖や掃除との併用が欠かせません。
駆除剤の効果を高めるポイント
「殺鼠剤を置いたのに効かない」「忌避剤を使ってもネズミがいなくならない」といった声をよく聞きます。
ここでは、駆除剤の効果を最大化するためのポイントや、そもそもなぜ効かないのかという原因を解説します。
ネズミの習性を理解しよう
ネズミは警戒心が強く、警戒した環境下では餌を食べずに逃げてしまいます。
また、餌を少量ずつ食べて安全か確認する「偏食行動」があるため、毒エサを一度に大量に食べない場合も少なくありません。
忌避剤の場合も、匂いの濃さや配置場所が不適切だと効果が限られます。
そのため、まずはネズミの通り道や生息場所をしっかり把握し、最適なポイントに駆除剤を設置することが大切です。
複数の対策を組み合わせる
駆除剤だけに頼らず、粘着シートや捕獲器、超音波装置などを併用すると、より効果的です。
例えば、毒エサを食べて弱ったネズミを粘着シートで捕獲できるようにすると、取り逃しを減らすことができます。
また、忌避剤で追い出しながら侵入口をふさいでしまえば、再侵入を大幅に抑えられます。
ネズミが増えすぎる前に、複数の手法を組み合わせた総合的なアプローチが理想的です。
参考:横浜市「ネズミについて」
再発防止策が重要
駆除剤でネズミをある程度減らしても、そのまま放置すれば再び侵入されるリスクがあります。
特に、古い家屋は床下や壁に隙間が多く、食料品の保管方法も甘いと、ネズミにとって快適な環境が残ったままです。
最終的には、以下のような環境改善策が欠かせません。
- 隙間や穴をすべて塞ぐ。
- 食品を密閉容器や冷蔵庫に収納する。
- ゴミはこまめに処分し、ニオイを残さない。
- 糞や巣跡を見つけたら、消毒液を使ってしっかり清掃する。
駆除剤についてよくある質問
ここでは、駆除剤についてよくある質問に答えていきます。
初めて駆除剤を使う方、何を買えばいいか分からない方の参考になれば幸いです。
Q1. バルサンや正露丸はネズミに効きますか?
A. 残念ながら、いずれもネズミの駆除にはほとんど効果がありません。
バルサンは殺虫成分が主体の燻煙剤であり、哺乳類であるネズミには効きにくいといわれます。
正露丸も強い匂いがありますが、ネズミを追い出すほどの忌避効果は期待できません。
Q2. 忌避剤は何日くらいで効果が切れますか?
A. 製品によって異なりますが、匂い型の多くは2~4週間程度で匂いが薄れます。
記載されている期間を目安に新しいものと交換しましょう。
Q3. 駆除剤だけで完全にネズミを根絶できますか?
A. ネズミが少数なら可能性はありますが、繁殖して多数いる場合や古い家屋の場合は、他の手法(粘着シートや捕獲器)や侵入経路封鎖なども組み合わせるのが望ましいです。
自力駆除が難しいと感じたら専門業者へ
ネズミの被害が大きくなると、駆除剤の使用だけでは対応しきれない場合があります。
天井裏に大量のネズミが巣を作っていたり、毒エサを設置してもすべて食べられずに残っている場合は、すでにネズミの数が多い可能性が高いです。
そんな時は、専門業者に依頼して早期に解決するのがおすすめです。
専門業者に依頼するメリット
- 確実な駆除:被害状況を調査し、必要な場所に粘着シートや殺鼠剤、捕獲器などを的確に使い分けてくれます。
- 再発防止施工:侵入口の塞ぎや断熱材の修繕など、再侵入を防ぐ工事もまとめて行うことができます。
- 時間と手間の節約:自力で試行錯誤するより短期間で成果を出しやすいです。
費用はかかりますが、長期的に見れば被害の拡大を防ぎ、住環境を守るための有効な選択肢といえます。
本格的なネズミの追い出しや駆除は専門家まで
駆除剤の効果についてお伝えしてきましたが、可能なら本格的なネズミの追い出しや駆除は、専門家に依頼すべきでしょう。
なぜなら、駆除剤でネズミを一時的に追い出せたとしても、侵入経路対策を徹底的に行わなければ、ネズミ被害はいくらでも再発してしまうからです。
そして、この侵入経路対策が専門家以外には難易度が高く、家中の1~1.5cm程度の隙間をすべて塞がなければネズミの侵入を防ぐことができません。
手軽さゆえに忌避剤を試してみたくなる気持は理解できますが、対策に時間を費やして被害が拡大してしまう前に、専門家に依頼してしまう方が確実でしょう。
ハウスプロテクトは、ネズミ駆除の専門家であり、忌避剤だけでなく様々な方法を用いてネズミを追い出したうえで、家中の侵入経路対策を徹底して行います。また、万が一の再発時にも、最長10年間は無料でアフターフォロー対応を行わせて頂きます。
現地調査や見積は無料で行わせて頂きますので、本格的なネズミ対策を行いたい方は、お気軽にご相談ください。
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
まとめ
ネズミの駆除剤には、大きく分けて殺鼠剤と忌避剤があり、それぞれ効果や使い勝手が異なります。
毒エサ型の殺鼠剤はネズミを直接駆除できる半面、誤食事故のリスクや死骸処理の手間があるため、安全対策が必要です。
忌避剤はネズミを追い払う方法として有効ですが、すでに住み着いている場合には十分な効果を発揮しにくいこともあります。
いずれの方法も、ネズミの通り道を正確に把握し、複数の対策を組み合わせ、侵入経路を塞ぐなどの再発防止策を徹底することで、はじめて効果が出やすくなります。
古い家屋にお住まいの方で、既に被害が深刻な場合や駆除剤だけでは対処しきれないと思われる場合は、専門業者へ依頼するのも一つの方法です。