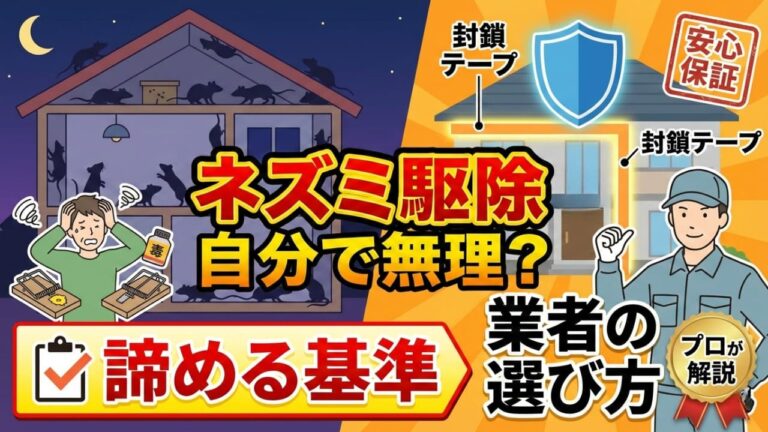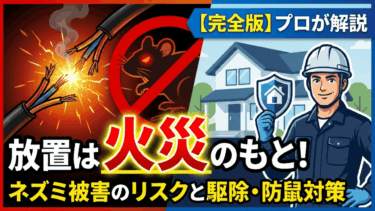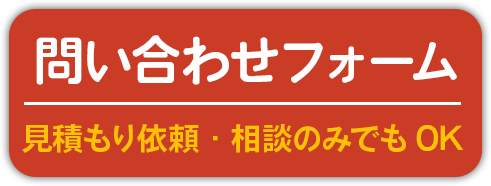ネズミ駆除は、プロでも苦戦するくらい難易度が高い分野の一つです。
特に、天井裏や壁の中に潜んでいるネズミを相手にする場合、市販のグッズだけで完全駆除するのは、ほぼ不可能と言っても過言ではありません。
「業者に頼むと高額請求されそう」「まだ自分でできるはず」と自力で対策し続けていると、被害も費用も何倍にも膨れ上がってしまいます。
そこで本記事では、「自分で駆除するのは無理」と判断すべき基準をプロが解説!
「自分でネズミ駆除を続けるリスク」や「失敗しない業者を選ぶ方法」も紹介しますので、ぜひご確認ください。
自分でネズミ駆除できるかどうかの判断基準

以下の項目に1つでも当てはまる場合、自力でのネズミ駆除は極めて困難です。
- 天井裏や壁の中から音がする
- ラットサインが特定できない
- 死骸や生きたネズミを処理できない
- 市販のグッズを使っても効果がない
- 築年数が20年以上、または増改築をしている
無駄な時間とお金を使う前に、プロへの相談を検討しましょう!
以下でそれぞれ解説します。
天井裏や壁の中から音がする
夜中に天井裏から「ドタドタ」「カサカサ」と音が聞こえる場合、ネズミがすでに建物の構造内部に巣を作っている証拠です。
市販の粘着シートや毒餌は、ネズミが「目に見える場所」を通る場合にしか効果を発揮しません。また天井裏や壁の中など「人間が立ち入れない空間」に潜んでいる場合、そもそも罠を仕掛ける場所すら特定できない問題があります。
さらに、天井裏には断熱材があり、ネズミはそこに巣を作ります。断熱材をボロボロにされると、冷暖房効率が著しく低下し、光熱費が跳ね上がるという二次被害も発生します。
姿が見えないネズミを相手にするには、赤外線カメラや内視鏡を使った調査、天井裏に入っての捕獲作業が必要です。これは素人では不可能な領域です。
ラットサインが特定できない
ネズミは警戒心が強く、壁際や隅を通る習性があります。同じルートを何度も通るため、体についた油や汚れで黒ずんだ跡、いわゆる「ラットサイン」が残ります。
このラットサインを見つけられるかどうかが、駆除成功の分かれ目です。
ラットサインが残っている場所があれば、そこに粘着シートを設置することで捕獲できる可能性があります。しかし、「ネズミがいるのはわかるけど、どこを通っているかわからない」という状態では、罠を設置する場所が定まりません。
プロは長年の経験から、「この家の構造なら、ここを通るはず」という予測ができます。また、侵入経路となりやすい床下換気口、配管貫通部、屋根の隙間なども熟知しています。
そんなラットサインが特定できない場合、ネズミの行動パターンを読めず、的外れな場所に罠を仕掛け続けるだけで終わります。
死骸や生きたネズミを処理できない
粘着シートに捕まったネズミは、まだ生きています。「ビニール袋に入れて窒息死させる」という処理ができない方も少なくありません。
また毒餌を使った場合、ネズミは天井裏や壁の中で死ぬことがあります。死骸を放置すると、腐敗臭が家中に広がり、ウジやハエが大量発生します。
プロは防護服と専用の道具を使い、衛生的に死骸を処理します。さらに、死骸があった場所の消毒・殺菌まで行うため、感染症のリスクもありません。
無理に自分で処理しようとすると、精神的なストレスで夜も眠れなくなります。
市販のグッズを使っても効果がない
ホームセンターで粘着シートを買って設置し、効果がないので場所を変えてもう一度、そんな事を続けて、気づけば○万円も使ったという方も少なくないです。
ネズミは非常に賢い動物で、一度罠を回避したルートは記憶します。粘着シートを見つけると、次からはそこを避けて通るようになります。
1~2回試して効果が無い場合、3回目以降もうまくいく可能性は極めて低いでしょう。
プロは、ネズミの学習を逆手に取った「複数の罠を連動させる配置」や「一度で逃げ場をなくす包囲戦術」を使います。これは知識と経験がなければできない技術です。
1回使ってダメなら、これ以上の自力駆除は「時間とお金の無駄遣い」になります。
築年数が20年以上、または増改築をしている
築年数が経過した建物や増改築を行った建物には、必ず「隙間」が生まれます。
ネズミは、500円玉サイズの隙間があれば侵入できます。特に以下のような隙間は、建築の専門知識がなければ見つけられません。
- 基礎と土台の隙間
- 配管の貫通部
- 増築部分のつなぎ目
仮に運良くネズミを1匹駆除できたとしても、侵入口が開いたままでは、また別のネズミが入ってきます。駆除と侵入が繰り返すため、被害が解決しません。(参考:目黒区|ネズミの被害を防ぐために!)
特に古い家の場合、床下の通気口が破れていたり、屋根の裏側に穴が開いていたりすることもよくあります。これらは屋根に登ったり、床下に潜ったりしないと確認できません。
ちなみにネズミの侵入経路を塞ぐ場合、以下のようなネズミが破れない素材を使う必要があります。
- 金属パンチングメタル
- 防鼠用のブラシ
- 専用のコーキング材 など
市販の隙間テープやアルミテープでは、かじられて数日で破られます。
1つでも当てはまる方は、被害が拡大する前にプロの無料現地調査を受けることを強くおすすめします。
ネズミ駆除業者「ハウスプロテクト」では、出張費をはじめ、現地調査や見積もり作成もすべて無料で行ってくれるため、ぜひこれを機にお問い合わせしてみてください。
\24時間365日受付中!相談のみOK/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
ネズミ駆除は自分で無理と言われる理由
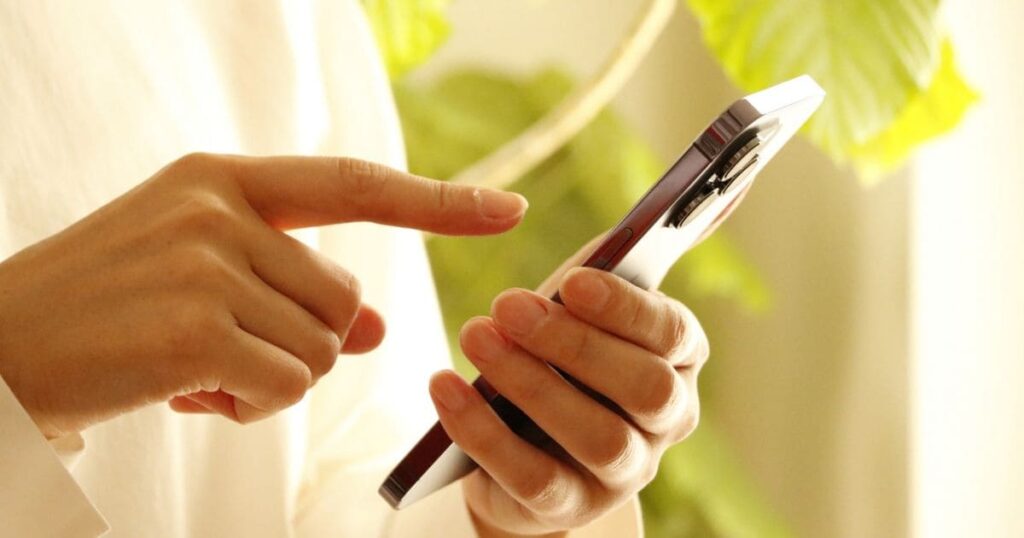
自力でネズミを駆除できない理由をプロの視点から詳しく説明します。
「本当に自分では駆除できないの?」そんな方はぜひご確認ください。
繁殖スピードが駆除を上回るから
「ネズミ算」という言葉があるように、ネズミの繁殖力は驚異的です。
家屋に侵入する代表的なネズミ「クマネズミ」の場合、生後3ヶ月で繁殖可能になり、年に5〜6回出産します。
1回の出産で5〜6匹の子を産むため、理論上は1組のつがいから1年で数十匹に増えます。
仮に粘着シートで1週間に1匹ずつ捕まえられたとしても、その間にメスは妊娠・出産を繰り返しています。駆除のペースが繁殖のペースに追いつかなければ、個体数は減るどころか増え続けます。
プロは、初回の調査で「何匹いるか」「繁殖状況はどうか」を判断し、根本解決する作戦を立てます。
以下のような複数の手法を組み合わせ、短期間で個体数を減らします。
- 粘着シート
- 毒餌
- 捕獲カゴ
- 燻煙剤 など
ご自身で1匹ずつコツコツ捕まえる方法では、繁殖に追いつけません。
500円玉サイズの隙間があれば再侵入されるから
先ほども触れましたが、ネズミは体が柔らかく、頭さえ通れば体も通り抜けられます。
成獣のクマネズミでも、直径約2.5cm(500円玉サイズ)の穴があれば侵入可能です。
多くの方が見落としがちなのが以下のような場所です。
- エアコンの配管穴(壁貫通部の隙間)
- 換気扇のダクト接続部
- 給排水管が通る床下の穴
- 軒天の腐食部分
- 基礎と土台の隙間(経年劣化で開く)
- 増築部分のつなぎ目
これらの隙間を完全に塞ぐには、建物の構造を理解し、適切な材料と工法を選ぶ必要があります。素人がホームセンターの材料で応急処置しても、ネズミはその弱点を見つけて再侵入してきます。
駆除だけしても、侵入口が開いたままでは意味がありません。これが、ネズミ駆除が「一時的な対処」では終わらない理由です。
スーパーラットが増えているから
近年、ワルファリンなど従来の殺鼠剤に対して、抵抗性を持つ「スーパーラット」が都市部を中心に増えています。
これは、殺鼠剤を使い続けたことで薬剤に耐性を持つ個体が生き残り、その遺伝子が広まったためです。市販の毒餌を食べても死なず、逆に「この餌は安全」と学習してしまうケースもあります。
プロは、スーパーラットに対しても効果のある「第二世代抗凝血性殺鼠剤」や「物理的な捕獲」を組み合わせて対応します。また、地域ごとのネズミの種類や耐性状況を把握しているため、効果的な薬剤を選定できます。
ホームセンターで買った毒餌を食べた形跡があるのに、ネズミが減らない場合、スーパーラットの可能性があります。
自力でネズミ駆除を続けるリスク
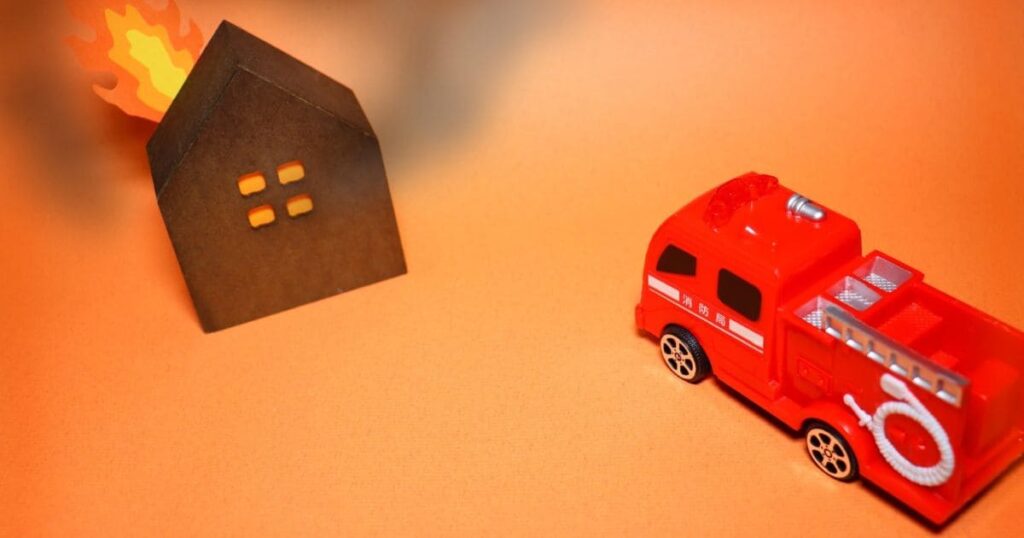
「もう少し頑張れば…」と自力でネズミ駆除を続けた結果、取り返しのつかない被害に発展するケースが後を絶ちません。
以下で詳しく解説します。
ダニ・ノミの大量発生と感染症リスク
ネズミの体には、イエダニやノミが多数寄生しています。ネズミが天井裏や壁の中で死ぬと、寄生していたダニやノミは新しい宿主を求めて人間の生活空間に降りてきます。
朝起きたら腕や足に赤い発疹がたくさんできていた場合、イエダニに刺された典型的な症状です。ダニは夜間に活動し、寝ている間に刺すため、気づいたときには家中に広がっているケースもあります。
さらに深刻なのは、ネズミが媒介する感染症のリスクです。厚生労働省の資料によれば、ネズミは以下のような病気を媒介する可能性があります。
- ハンタウイルス肺症候群
- レプトスピラ症
- サルモネラ症
- 腎症候性出血熱
これらは糞尿に触れたり、乾燥した糞が粉塵となって吸い込むことで感染します。天井裏の掃除を素人が行うと、知らず知らずのうちに病原体の被害に遭うリスクがあります。
電気配線をかじられて火災が発生
ネズミの前歯は一生伸び続けるため、常に何かをかじって歯を削る習性があります。その対象が、壁の中や天井裏を通る電気配線だった場合、極めて危険です。
配線の被覆がかじられると、ショートして火花が散り、火災が発生します。
実際、NITE(製品評価技術基盤機構)では、ネズミによる配線損傷が原因と見られる火災事例が報告されています。
木造住宅の場合、天井裏や壁の中で出火すると、発見が遅れて全焼につながる恐れもあります。
「まだ大丈夫」と放置している間に、配線は少しずつ削られ続けているのです。
ネズミ被害が疑われる場合、電気配線の点検も含めて調査が必要です。
家の資産価値が下がる
ネズミは一日に数十回も排尿し、糞も大量に残します。天井裏や床下に糞尿が蓄積すると、木材が腐敗し、建物の強度に影響を与えます。
特に湿気がこもりやすい床下では、糞尿が原因でカビが繁殖し、シロアリを呼び寄せることもあります。
また、将来的に家を売却する際、「過去にネズミ被害があった」という事実は告知しないといけない可能性があります。適切に駆除・清掃されていない場合、査定額が大幅に下がるリスクもあるため決して放置してはいけません。
被害が拡大すればするほど、修復費用も高額になります。そのため、早期にプロへ依頼することが、結果的に最もコストを抑える方法です。
「あの時、相談していればよかった…」と後悔する前に、まずはプロの現地調査で被害状況を正確に把握しましょう。
ハウスプロテクトでは、出張費をはじめ、現地調査や見積もり作成もすべて無料で行ってくれるのでぜひこれを機にお問い合わせしてみてください。
\24時間365日受付中!相談のみOK/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
ネズミ駆除業者選びで失敗しないための3つの条件

「プロに頼んだ方がいいのは分かったけど、どの業者を選べばいいの?」そんな方もいらっしゃるでしょう。
残念ながら、ネズミ駆除業者の中には悪徳業者も存在します。
下記3つの条件を満たす業者を選べば、失敗するリスクは大幅に減らせます。
- 侵入経路の封鎖が得意
- 見積もりが明確で追加請求がない
- 口コミや実績が豊富にある
以下で詳しく解説します。
条件①侵入経路の封鎖が得意
ネズミ駆除で最も重要なのは、「今いるネズミを減らすこと」ではなく「被害を再発を防ぐこと」です。
駆除だけしても、侵入口が開いたままでは1ヶ月後にまた別のネズミが入ってきます。つまり、業者を選ぶ際は「封鎖工事の技術力」を必ずチェックしてください。
具体的には、以下のような質問をしてみましょう。
- 侵入経路の調査はどこまで行いますか?
- 封鎖にはどんな材料を使いますか?
- 保証期間はありますか?
優良業者は、床下や屋根裏に入って隅々まで調査し、金属製のパンチングメタルや防鼠ブラシなど、ネズミが破れない素材で封鎖します。また、施工後に再発した場合の保証制度も整っています。
逆に、「とりあえず粘着シートを置いておきます」だけで終わる業者は要注意です。
条件②見積もりが明確で、追加請求がない
悪質な業者の典型的な手口が、「現地で不安を煽って高額なオプションを押し売りする」というものです。
一方で優良業者は、現地調査後に「作業内容」と「料金」を明確に提示し、追加料金が発生する場合は事前に説明します。
見積書には、「駆除作業費」「封鎖工事費」「清掃費」など項目ごとに金額が記載されているはずです。また、「無料見積もり後にキャンセルしても、出張料や調査料を請求されない」ことも重要なポイントです。
ネズミ駆除の費用相場を詳しく知りたい方は、以下の記事よりご覧ください。
条件③口コミや実績が豊富にある
実際に依頼した人の声は、業者選びの最も信頼できる情報源です。
- Googleのクチコミ
- 口コミサイトでの評価
- 公式サイトでの施工事例
これらを確認し、「対応が丁寧だった」「説明がわかりやすかった」「再発しなかった」といった具体的な内容があるかチェックしましょう。
逆に、「口コミがほとんどない」「評価が極端に低い」「施工事例が掲載されていない」業者は避けたほうが無難です。
また、創業年数や年間施工件数も判断材料になります。長年続いている業者は、それだけ信頼を積み重ねてきた証拠と言えるでしょう!
ネズミ駆除業者選びに迷ったら「ハウスプロテクト」へ無料相談!
ここまで説明してきた「失敗しない業者の3つの条件」をすべて満たしているのが、ネズミ駆除業者「ハウスプロテクト」です。
以下では、ハウスプロテクトをおすすめする理由を解説します。
「ハウスプロテクトの何がいいの?」と疑問をお持ちの方はぜひご確認ください。
リフォーム会社が母体だからできる封鎖工事
ハウスプロテクトの最大の強みは、リフォーム会社を母体に持つ高い施工技術です。
一般的な駆除業者は「ネズミを捕まえること」を専門にしているため、侵入経路の封鎖となると技術が追いつかないケースがあります。
特に古い家や構造が複雑な建物では、「どこを、どう塞ぐべきか」の判断はかなり難しいと言えるでしょう。
一方、ハウスプロテクトのスタッフは建築知識を持ち、基礎から屋根まで建物全体を「構造」として理解しています。そのため、以下のような素人では気づけない侵入口も見逃しません。
- 配管貫通部の複雑な隙間
- 増築部分のつなぎ目
- 経年劣化で開いた基礎のクラック
- 軒天の見えにくい穴
封鎖には、ネズミがかじり破れない「金属パンチングメタル」や「防鼠用ブラシ」を使用し、建物の美観を損なわないよう丁寧に施工します。
「駆除後、二度とネズミが入ってこないようにしてほしい」といった方は、特におすすめの駆除業者と言えます。
出張費・現地調査・見積もりは完全無料
そんな不安を感じる必要はありません。
ハウスプロテクトでは、出張費をはじめ、現地調査と見積もりが完全無料です。
調査後、見積もり内容に納得できなければ、その場で断っても一切費用は発生しません。出張料や調査料を後から請求されることもありません。
見積もりでは、下記の項目を丁寧に説明してもらえます。
- 現在の被害状況
- ネズミの侵入経路
- 必要な作業内容
- 明確な料金(項目別)
追加料金が発生する可能性がある場合も、事前にしっかり伝えてくれるので、「後から高額請求された」というトラブルはありません。
「まずは被害状況だけでも見てほしい」という気軽な相談も受け付けています。また無料だからこそ、複数の業者と比較検討することも可能です。
実際の利用者の声
ハウスプロテクトを実際に利用した方からは、以下のような声が寄せられています。
「市販のグッズで半年も格闘していましたが、一向に減らず…。ハウスプロテクトさんに依頼したところ、調査の段階で『ここから入ってますね』と侵入口を次々と発見してくれました。封鎖工事後は一度もネズミの音を聞いていません。もっと早く頼めばよかったです。」(東京都・40代女性)
「天井裏で死んだネズミの臭いが取れず、どうしていいかわからず相談しました。死骸の撤去から消臭・除菌まで丁寧にやってくれて、臭いも完全に消えました。作業中も『今ここをやっています』と逐一報告してくれて安心でした。」(神奈川県・50代女性)
「見積もりの時点で、どの隙間をどう塞ぐか、写真や動画を見せながら説明してくれたのが良かったです。料金も最初に提示された金額から一切変わりませんでした。」(埼玉県・30代男性)
参考:ハウスプロテクト|口コミ
こうした口コミから分かるとおり、ハウスプロテクトは、「技術力」「説明の丁寧さ」「料金の透明性」が高く評価されています。
さらに「ハウスプロテクト」は、年間3,000件以上の施工実績を持ち、リフォーム技術を活かした再発防止策にも定評があります。
ぜひこれを機にお問い合わせしてみてください。
\24時間365日受付中!相談のみOK/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
「ハウスプロテクトを利用した方の口コミ・評判をより詳しく知りたい」といった方は、以下の記事よりご覧ください。
ネズミ駆除は自分で無理?によくある質問【Q&A】

ここまで読んで「相談してみようかな」と思っても、まだ少し不安が残っているかもしれません。
実際に多く寄せられる質問にお答えしますので、安心して問い合わせていただければと思います。
Q. 近所の人にネズミ駆除をしているとバレたくないのですが…
A. ご安心ください。プライバシーに配慮した対応が可能です。
ハウスプロテクトでは、ご希望があれば社名が入っていない車両で訪問し、近隣の方に気づかれないよう配慮しています。
また、作業時間帯についても「平日の日中は避けてほしい」といったご要望にも柔軟に対応できます。申込時や現地調査の際に、遠慮なくご相談ください。
「ネズミがいることを知られたくない」というお気持ちは、多くの方が抱える悩みです。恥ずかしいことでは決してありませんが、そうしたデリケートな心情にも寄り添った対応を心がけています。
Q. 小さな子供やペット(犬・猫)がいても薬剤は大丈夫?
A. はい、安全に配慮した施工を行いますのでご安心ください。
薬剤を設置する場所も、天井裏や床下など普段お子様やペットが立ち入らない場所に限定します。
作業前には「ここに薬剤を置きます」と明確に説明しますので、ご家族の生活スタイルに合わせた最適な方法を一緒に考えていきましょう。
小さなお子様やペットがいるご家庭の施工実績も豊富にありますので、安心してお任せください。
Q. 調査に来てもらったら、必ず契約しないといけませんか?
A. いいえ、まったくその必要はありません。調査・見積もり後にお断りいただいても、費用は一切かかりません。
ハウスプロテクトの現地調査と見積もりは完全無料です。調査後、以下のような理由でお断りいただいても、出張料や調査料を請求することは一切ありません。
- 思ったより費用がかかりそうだから、少し考えたい
- 他の業者とも比較してから決めたい
- 今回は見送ります
無理な営業や、その場での契約を迫ることもありませんので、ご安心ください。
調査では、下記の項目を丁寧に説明し、「どんな工事をするのか」「なぜその料金なのか」を納得いただけるまでお伝えします。
- 現在のネズミ被害の状況
- 侵入経路の特定
- 必要な作業内容と明確な料金
「とりあえず被害状況だけでも見てほしい」という気軽なお問い合わせで構いません。
まずは現状を正確に把握することが、解決への第一歩です。
まとめ
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
ネズミは人間よりも遥かに学習能力が高く、繁殖力も強い生き物です。
もし、以下の状況に1つでも当てはまるなら、プロへ相談することをおすすめします。
- 天井裏や壁の中から音がする
- ラットサインが特定できない
- 死骸や生きたネズミを処理する勇気がない
- 市販グッズを3,000円以上使っても効果がない 築年数が20年以上、または増改築をしている
被害を放置すれば、ダニ・ノミの発生、配線火災、感染症、建物の資産価値低下など、取り返しのつかない事態になりかねません。
業者選びで迷ったら、ぜひ一度、ハウスプロテクトへ相談することをおすすめします。
リフォーム技術を持ち、無料調査・明確な見積もり・豊富な実績を兼ね備えているため、安心して任せられます。
「もっと早く相談すればよかった…」と後悔する前に、まずは無料の現地調査で、あなたの家の状況を正確に把握することから始めましょう。
\24時間365日受付中!相談のみOK/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
ハウスプロテクト以外のネズミ駆除業者も知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。