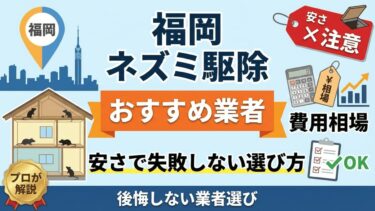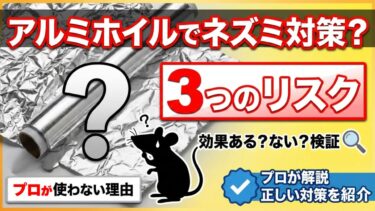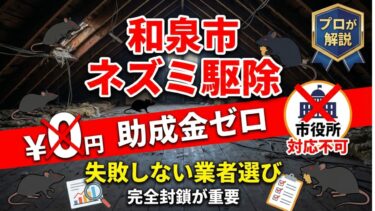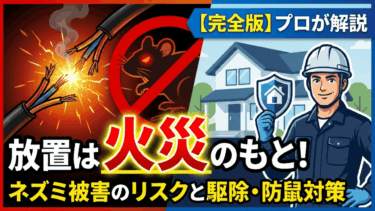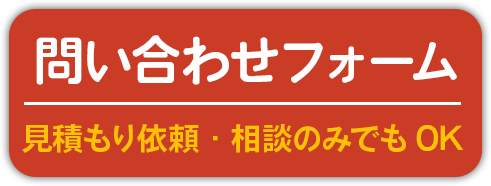家の天井裏から「ゴソゴソ」「カサカサ」という物音が聞こえたり、台所の片隅で黒いフンを見かけたりしていませんか。
その音やフンはネズミが屋根の隙間や壁際から侵入しているサインかもしれません。
ネズミは小さな穴さえあれば家の中に入り込み、食品被害や建物の損傷、さらには病原菌の媒介など、さまざまなリスクをもたらします。
特に古い家屋では、屋根や壁に隙間ができてしまいがちで、そこからネズミが自由に出入りしているケースが少なくありません。
そこで本記事では、屋根や壁、配管周りなどからの侵入を防ぐ方法を解説します。
被害が深刻化する前に、どこをチェックすればいいのか、どうやって塞げばよいのか。
具体的な対策ポイントを表や箇条書きを交えてご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
ネズミの侵入経路に関する基礎知識

ここではまず、「ネズミがどこから侵入してしまうのか」を解説します。
ネズミはとても体が柔軟で、わずか1~2cmほどの穴さえあれば家屋内に侵入するといわれています。
そして、侵入後は天井裏や壁の中、床下などを通って家全体を移動するため、被害があちこちに広がりがちです。
被害を抑えるためにも基本から学んでいきましょう。
ネズミが侵入経路として狙う場所
ネズミが家に入り込む際に多いのが、屋根裏の換気口や外壁と屋根との隙間です。
特に、古い家屋や増改築を繰り返した建物では、屋根の取り合い部分に微妙な段差が生じたり、板金の隙間ができたりしている可能性があります。
また、壁のひび割れや配管まわり、床下の通気口、玄関扉の下部なども油断できません。
一度侵入を許すと、天井裏を通じて台所や押し入れ、さらには壁の内部まで自由に動き回るため、被害が拡大してしまいます。
屋根裏や壁内で発生しやすい被害
ネズミが屋根裏に住み着くと、夜中に物音がするだけでなく、フン尿による悪臭やシミ、ダニ・ノミの発生など衛生上の問題が起こります。
さらに、ネズミは前歯が伸び続けるため、電気コードをかじってしまう危険もあります。
もし配線がショートして火災につながれば甚大な被害となるでしょう。
こうしたリスクを軽減するためにも、侵入経路を特定し早期に塞ぐことが欠かせません。
参考:横浜市「ネズミについて」
屋根から侵入する主なパターンと対策

ここでは、特に多いとされる「屋根周辺」からの侵入パターンを詳しく見ていきます。
屋根の隙間が生じる原因
- 経年劣化:瓦や板金、棟板金などが古くなり、隙間やズレが発生する
- 増改築時の不備:リフォームで増築した部分と既存部分の取り合いに隙間ができる
- 台風などの自然災害:強風や大雨で屋根材が破損し、そこから侵入される
屋根裏にネズミが入り込みやすい理由は、鳥などの外敵から身を守りやすく、比較的静かで暖かい環境だからです。
屋根付近を点検する際のチェックポイント
- 棟板金や雨樋の取り付け部:ゆるんでいる箇所や外れている部分がないか
- 換気扇や換気口の網:破れていないか、穴が開いていないか
- 屋根と外壁の接合部:わずかな隙間でも見逃さないよう、懐中電灯を使って確認
また、屋根からの侵入が疑われる場合は、屋根裏点検口(天井裏の点検口など)からフンやかじり跡、足跡がないかチェックすると良いでしょう。
その他の侵入経路と対策方法を徹底解説
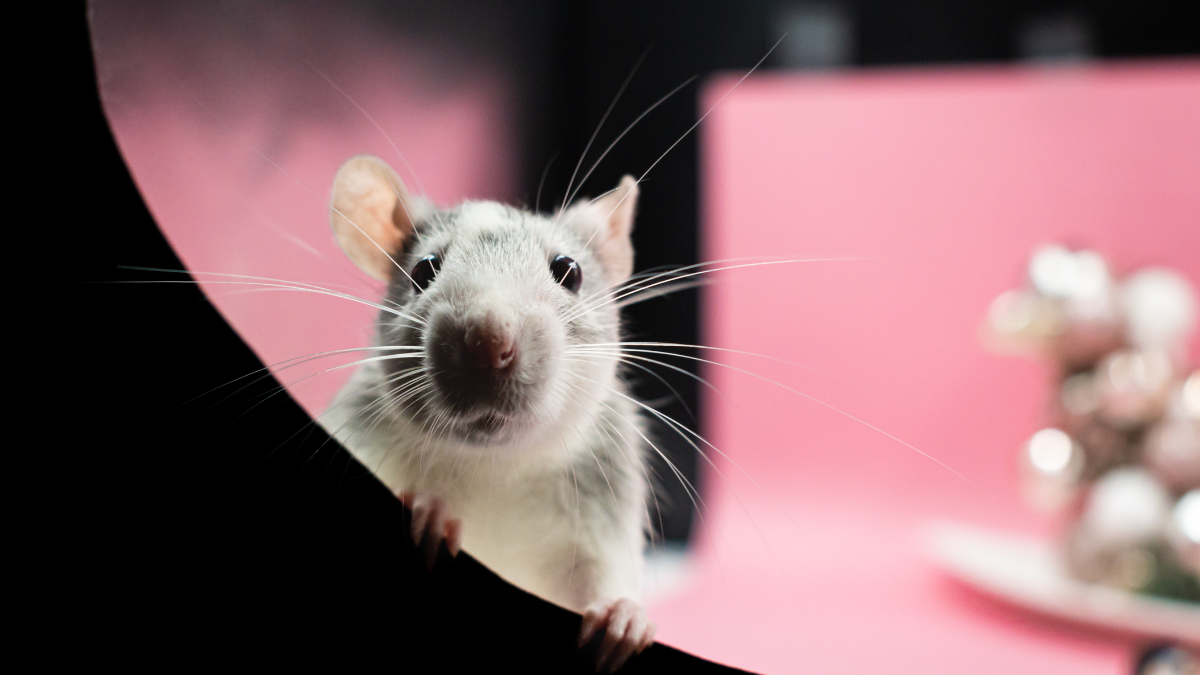
屋根以外にも、ネズミが出入りしやすい場所はたくさんあります。
ここでは、代表的な侵入箇所と、それぞれの対策法を一覧表で整理してみましょう。
| 侵入箇所 | 理由 | 対策案 |
|---|---|---|
| 床下の通気口 | 網が破れている 隙間が大きい | 金網を目の細かいものに交換 破損箇所をパテや鉄板で補強 |
| 配管の導入口(キッチン・洗面所) | パテ処理が不十分 劣化など | 耐火パテや防鼠パテを充填 配管と壁の隙間を塞ぐ |
| 外壁のひび割れ | 経年劣化 地震の影響など | ひび割れをコーキング剤で修復 大きい場合は専門業者に相談 |
| 窓や扉の下部 | 古い家屋で建付けが悪い | 隙間テープや戸当たり材を貼る 修理または建具交換を検討 |
| ベランダやバルコニーの排水口 | 落ち葉やゴミで目詰まり 掃除不足 | 定期的に掃除して排水口カバーを装着 網戸や金網で防御 |
これらの箇所を定期的に点検し、小さな隙間でも見つけたら早めに塞ぐことが大切です。
ネズミは高い壁も軽々と登り、配管を伝うなどして2階や3階部分にも侵入することがあります。
そのため、一階だけでなく上層階のベランダ周りや壁面も見落とさないよう注意しましょう。
参考:名古屋市「ネズミ -家の中でみかけたことはありませんか-」
ネズミ被害を最小限に抑えるための対策
「侵入経路を塞ぐ」ことは根本的な対策ですが、ネズミは既に家に入り込んでいるかもしれません。
ここでは、侵入口の封鎖以外にも必要な総合的な対策を解説します。
エサとなるものを与えない
- 食品は密閉容器に収納する。
- 生ゴミはふた付きのゴミ箱に入れ、こまめに捨てる。
- ペットの餌も食べ残しがないよう注意し、放置しない。
ネズミは食べ物の匂いに敏感で、家の中にエサがある限り、何度でも侵入を試みます。
巣材を減らす
- 古い段ボールや新聞紙などを溜め込まない。
- 布や紙類を押し入れに放置しない。
- 整理整頓を心がけ、ネズミが隠れられる物陰を減らす。
ネズミは紙や布を巣材に使うため、これらを放置しておくと巣を作られてしまいます。
駆除グッズの活用
- 粘着シート:ネズミの通り道に設置し、捕獲を狙う。
- 毒エサ(殺鼠剤):ネズミを直接駆除する。
- 超音波装置:ネズミが嫌がる超音波を発生させるが、慣れられる可能性もある。
侵入口をふさいだうえで、家の中に潜むネズミを捕まえたり、追い払ったりする必要があります。
一種類だけでは警戒される可能性があるため、複数の駆除法を組み合わせると効果的です。
自力で駆除できないネズミは当社にお任せください!

ネズミ駆除を自力で行うのはかなりの高難易度です。
自力での駆除に限界を感じたら、当社「ハウスプロテクト」にお任せください!
ネズミ被害についてもいろいろお伝えできますので、お気軽にご連絡いただければと思います。
当社はお客様のご要望に応じて、細かく作業内容を決めていきます。
「必要のない作業を行われて予想外の費用がかかった」「余計なサービスまで見積りに入っていて断り切れなかった」といったことはありえませんので、ご安心ください。
ご予算の範囲内でのネズミ駆除も承ることができますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
ネズミは自力で駆除しても再発しやすい上に、健康面や衛生面など被害は大きいです。
ぜひ当社に、お客様の安心で安全な暮らしを取り戻すお手伝いをさせてください!
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
当社「ハウスプロテクト」を利用した方々のリアルな口コミ評判を知りたい方はこちら>>
まとめ
ネズミは小さな隙間からでも家に侵入し、さまざまな被害をもたらす厄介な存在です。
侵入経路として最も多いのは屋根裏の換気口や外壁との隙間で、わずか1~2cmの穴でも入り込めるのです。
天井裏や壁の中を自由に移動するネズミは、食品被害だけでなく電気コードのかじりによる火災リスクも引き起こします。
屋根周辺では経年劣化や増改築時の不備が隙間を生み出し、ネズミに絶好の侵入口を提供してしまいます。
床下の通気口や配管の導入口、外壁のひび割れなども見逃せない侵入経路となりますので、定期的な点検が欠かせません。
対策としては侵入経路を塞ぐだけでなく、エサとなる食品の管理や巣材となる紙類の整理も重要です。
自力での駆除が難しい場合は専門業者に相談し、健康や衛生面でのリスクを最小限に抑えましょう。
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。