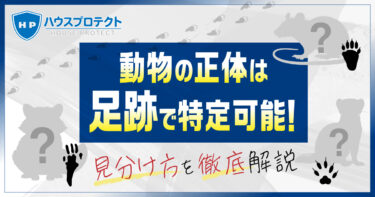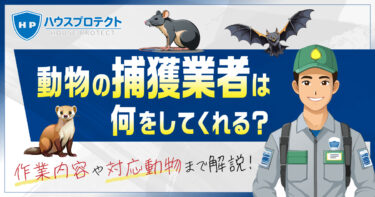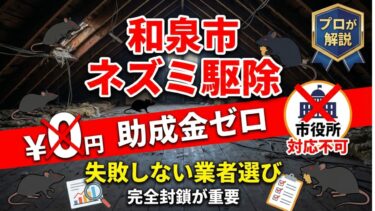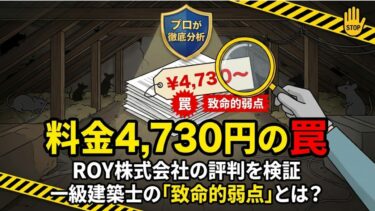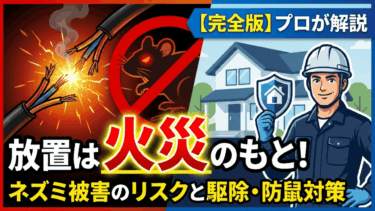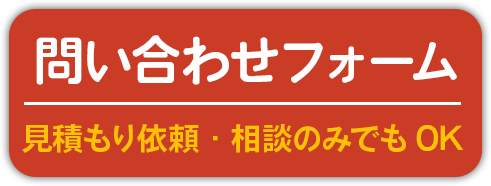「えっ、これって何のフン?」
庭先や屋根裏などで見慣れない細長いフンを見つけると不安になりますよね。
結論からお伝えしますと、細長いフンの正体はネズミやコウモリなどのフンかもしれません。
特にお子さまや高齢者、ペットがいるご家庭では早く対処しないと二次被害が発生する可能性があるため決して放置してはいけません。
そこで本記事では、フンで動物を見分ける方法を紹介!

「早くフンの正体を知りたい」「二次被害に遭いたくない」といった場合は、プロの駆除業者に相談することも検討してみてくださいね。
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
・「細長いフン、これなに…?」と気になっている
・「気持ち悪いから片付けてしまいたい!」と思っている
・「片付けたいけど、普通に掃除して大丈夫?」と気になっている
・「フンくらい放置しても大丈夫?」と思っている
細長いフンは何の動物?フンで動物を見分ける方法
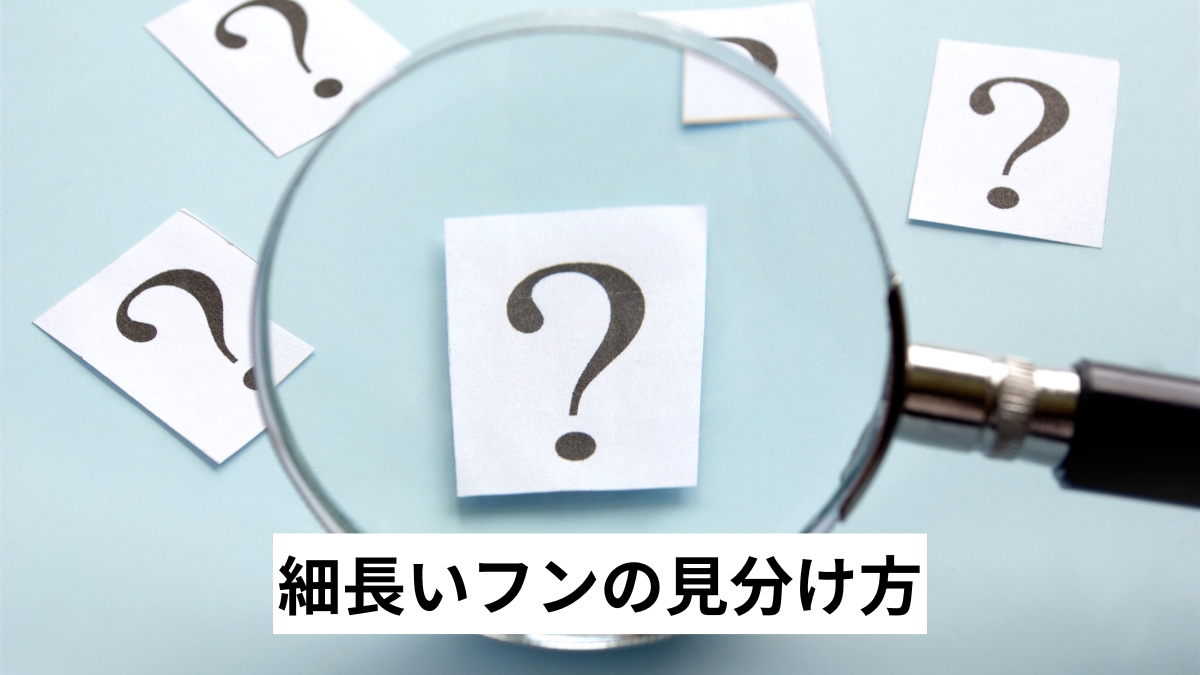
細長いフンの正体を見分ける場合、以下の2点に注目しましょう。
- 大きさ
- 特徴
これらに注目することでフンの落とし主が特定しやすくなります。
以下で詳しく解説しますので、フンを見分けて適切に対処しましょう!
フンが特定できない場合や自分で処理できそうにない場合は、プロの害獣駆除業者へ相談することも検討してみてください。
0.5cmから1cm程度の細長いフンの場合
小さめの細長いフンを見つけた場合は、下記3つの動物の可能性があります。
- ネズミ
- コウモリ
- イタチ
これら動物ごとのフンの大きさや特徴を以下にまとめました。
| 動物名 | 大きさ | 特徴 |
|---|---|---|
| ネズミ | 0.5〜1cm | ・酸っぱいニオイがすることがある ・茶色・灰色・黒色 ・水分を含んでいる ・丸みがある |
| コウモリ | 0.5〜1cm | ・乾燥してパサパサしている ・茶色 ・エサとなる昆虫の残骸が混じっていることがある |
| イタチ | 6mm程度 | ・ニオイがかなり強い ・黒色 ・動物の毛が混在していることがある |
フンの大きさや形状は、どれも似ているため、判別するにはそれぞれの特徴に注目しましょう。
ニオイや触ったときの感触のほうが判断しやすいですが、感染症やアレルギーを引き起こすリスクがあります。
ニオイや感触以外で見分ける場合は、フンの混在物を確認してみてください。
コウモリであれば昆虫の残骸、イタチであれば食べた小動物の毛が含まれていることがあります。
また、ネズミのフンはコウモリやイタチと違い、丸みを帯びている特徴があります。
5cmから15cm程度の細長いフンの場合
5cmから15cm程度のフンは、以下の動物の可能性があります。
- ハクビシン
- アライグマ
これらの動物ごとのフンの大きさや特徴を以下にまとめました。
| 動物名 | 大きさ | 特徴 |
|---|---|---|
| ハクビシン | 5~15cm | ・丸みがある ・果実や野菜を好んで食べるため、フンに種が多く含まれる ・黄土色、こげ茶色 ・甘いニオイがする |
| アライグマ | 5〜15cm | ・動物の骨や昆虫の羽が混じることがある ・強い悪臭 ・黄土色、こげ茶色 ・寄生虫(アライグマ回虫)が潜んでいる可能性がある |
ハクビシンやアライグマのフンの大きさや色は似ているため、混在物やニオイで見分けましょう。
果実や野菜を好んで食べるハクビシンのフンには種が多く見られ、雑食のアライグマのフンには動物の骨や昆虫の羽が見られます。
食べるものの違いはニオイにも影響があり、ハクビシンのフンは甘いニオイがする一方で、アライグマのフンは強い悪臭を放ちます。
自然に感じる程度でも判別できるため無理に嗅ぐ必要はありません。
混在物を確認する際も、直接触れず目視で確認するのが比較的安全です。
「やっぱり、なんのフンかわからない」「自力で処理できそうにない」

累計10,000件以上の駆除実績を誇る「ハウスプロテクト」では、メール・電話相談をはじめ、現地調査や見積もり作成もすべて無料で承っておりますのでぜひお気軽にお問い合わせください。
\最短即日対応!相談のみOK/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
フンを片付ける際の3つのNG行動

家の中や近くでフンを見かけた場合、早めに片付けてしまいたいですよね。
ですが、フンを処理する場合、3つのNG行動があります。
あらかじめ把握しておくことで、安全にフンを片付けることができますのでぜひご参考ください。
直接触れる
「手を洗えばいいし、特に抵抗がないから」とフンに直接触れるのはNGです。
なぜなら、動物のフンは病原体を媒介している可能性があるため、感染症の原因になるからです。
衣服もそのまま捨てても良いものを着用するとより安心です。
掃除機で吸う
「掃除機で吸えば、フンに直接触れないから問題ない?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、掃除機でフンを吸うことはやめてください。
そのため動物のフンを処理する際は、ホウキやちりとりでフンを集め、そのまま破棄する方法が最も安全となります。
ホウキやちりとりは、100円ショップなどで安いものを購入すると経済的な負担も少なくなります。
消毒・消臭をしない
フンを片付けるだけでは、清掃が完了したとは言えません。
なぜなら、染みついたニオイや残った病原体を処理する必要があるからです。
消毒には、以下2つを含んだ消毒液をフンがあった箇所に散布しましょう。
- 次亜塩素酸ナトリウム
- アルコール
このとき、台所用洗剤など酸性の液体と混ざると有毒ガスが発生するので注意してください。
参考:DUSKIN「何故混ぜてはダメなのか。“まぜるな危険”を理解しよう」
染みついたニオイを消臭する場合は、ペット用の消臭スプレーを使用します。
ニオイが残っていると不快なのはもちろんのこと、マーキング効果があるため動物が頻繁に訪れる恐れもあるのでしっかり消臭しましょう。
「感染症のリスクが怖い」「自力でフンを処理できそうにない」といった場合は、ぜひ一度プロの害獣駆除業者へご相談ください。
累計10,000件以上の駆除実績を誇る「ハウスプロテクト」では、独自開発の人体に無害な薬剤を使い、消臭をはじめ、残った菌やウイルスをしっかり除菌いたします。
\最短即日対応!相談のみOK/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
フンを放置することで起きる被害
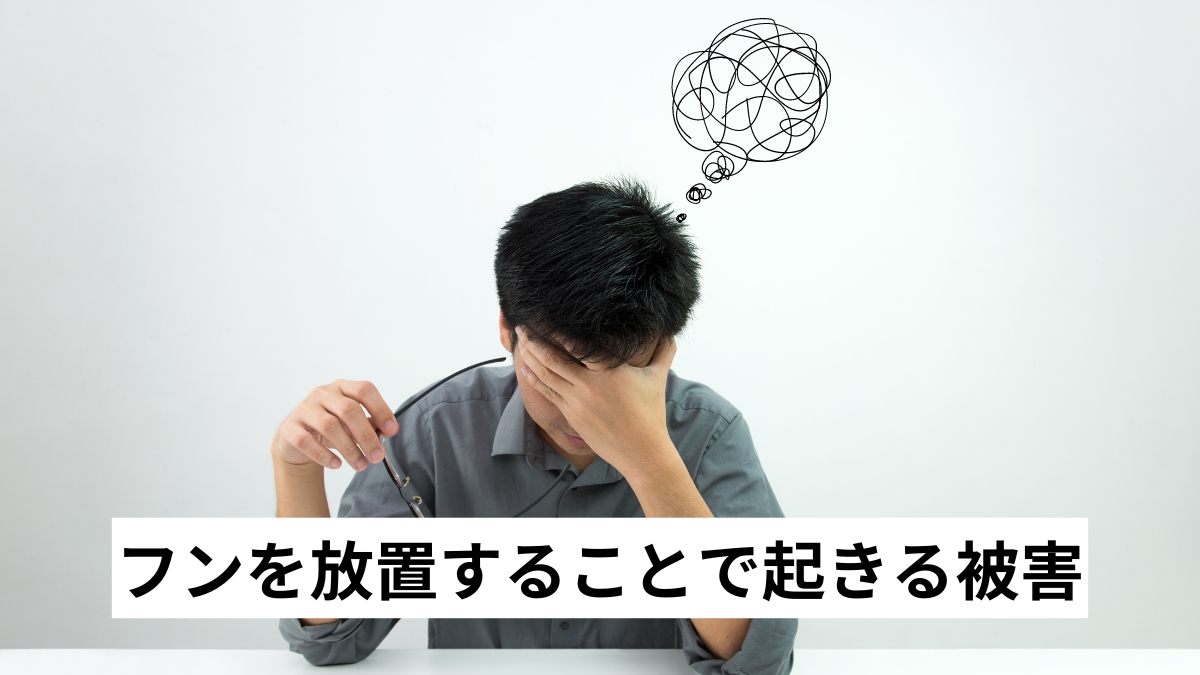
「多少、嫌なニオイがするくらいなら我慢できる」とフンを放置するのは危険です。
動物のフンを放置すると、健康面や家屋の状態に深刻な影響を与える可能性があります。
以下でそれぞれ解説しますので、フンの危険性を把握して速やかに対処しましょう。
健康被害
動物のフンは病原体の媒介となり、人間やペットが感染症にかかることもあります。
また動物のフンには、ノミやダニが多く集まるためアレルギー症状も引き起こしかねません。
動物の種類ごとにフンが引き起こす健康被害を以下にまとめましたのでぜひご確認ください。
| 動物の種類 | 引き起こす健康被害 |
| ネズミ | ・ハンタウイルス肺症候群 ・レプトスピラ症 ・サルモネラ症 |
| コウモリ | ・真菌感染 ・肺炎 ・狂犬病 ・悪臭 ・ヒストプラズマ症 ・狂犬病 |
| イタチ | ・サルモネラ菌 ・寄生虫 ・発熱 ・胃腸炎 ・皮膚炎 |
| ハクビシン | ・トキソプラズマ症 ・レプトスピラ症 |
| アライグマ | ・アライグマ回虫症 ・サルモネラ症 |
参考:
日本獣医学会 ハンタウイルス感染症
厚生労働省検疫所FORTH レプトスピラ症(ワイル病)
厚生労働省 動物由来感染症
アライグマ・ハクビシンが媒介する主な感染症
これらの二次被害が発生する可能性があるため、決して放置してはいけません。
特に小さなお子さまや高齢者、ペットがいるご家庭では、早めにフンを清掃し、消臭・除菌を行いましょう。
ご自身で対処できそうにない場合は、まずは一度、プロの害獣駆除業者へ相談することも検討してみてください。
家屋の劣化
動物のフンを放置すると、家屋に大きなダメージを与える可能性があります。
特に、屋根裏や床下に棲みついた動物は同じ場所で排泄を繰り返すため、フンが蓄積しやすくなります。
「ただの動物のフンだから」と放置してしまうと、高額な修繕費用が発生する可能性があるので、早期に清掃・消毒・除菌を行うことが重要です。
ただし、動物がすでに棲みついていたり、頻繁に出入りしている場合は、フンを片付けるだけでは根本的な解決にはなりません。
また、屋根裏や床下といった場所は清掃が難しく、ご自身での対処が困難なケースも多いでしょう。
もし、ご自身での清掃や対処が難しいと感じたら、まずはプロの害獣駆除業者に相談することをおすすめします。
早めに相談することで、被害を最小限に抑えられ、結果的に費用を抑えつつ、迅速に解決できます。
フンの清掃・消臭・除菌・再発対策はプロの害獣駆除業者へご相談!
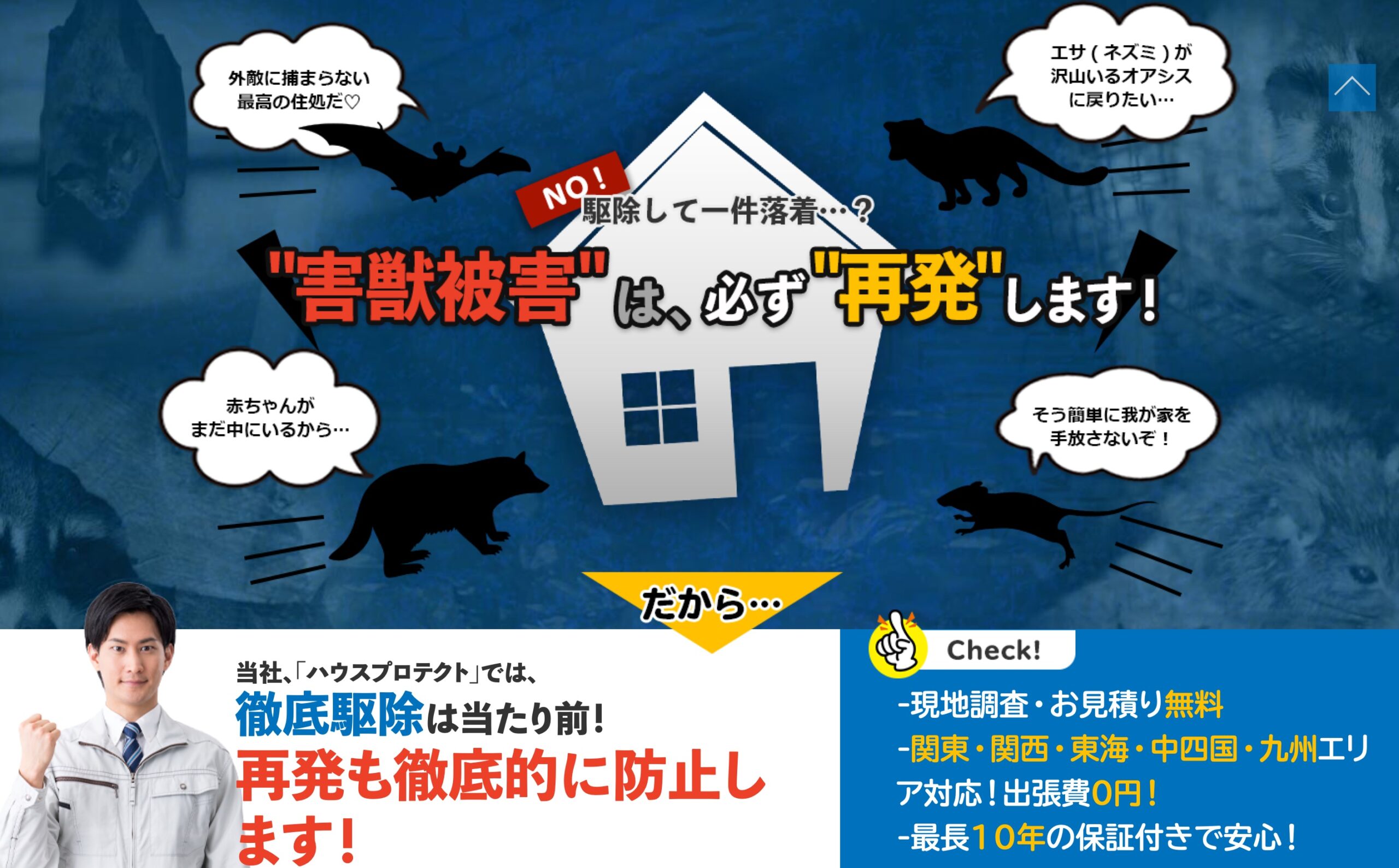
「自力でフンの清掃・消臭・除菌ができそうにない」
「何度もフン被害に悩まされている」
もし、このような問題を根本から解決したいとお考えなら、プロの害獣駆除専門業者「ハウスプロテクト」へご相談ください。
以下、ハウスプロテクトに依頼するメリットとなります。
- 24時間・年中無休で受付中
- 現地調査や見積もりが無料
- 病原菌やウイルスの飛散を防いでくれる
- フンで傷んだ建築材を清掃・消臭・除菌してくれる
- 侵入経路を特定し、しっかり塞いでくれる
- 屋根の上や天井裏、床下など手の届かない場所も作業可能
- 回収したフンなども処理してくれる
さらにハウスプロテクトでは、「最長10年の再発保証」を用意しています。
フンを放置することは大きなリスクを伴いますが、ご自身で清掃を行うのは大変な手間がかかる作業です。
また、単に清掃するだけでなく、今後同じ被害に遭わないよう、原因となっている害獣の駆除も欠かせません。
「ハウスプロテクト」なら、プロ仕様の薬剤で動物を安全に追い出し、侵入経路となる隙間を徹底的に塞ぎます。
メール・電話相談をはじめ、現地調査や見積もり作成もすべて無料で承っております。
「自分で対処できそうにない」「フンの正体がわからない」といったお悩みがある場合は、ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。
\最短即日対応!相談のみOK/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
細長いフン・なんのフンによくある質問【Q&A】
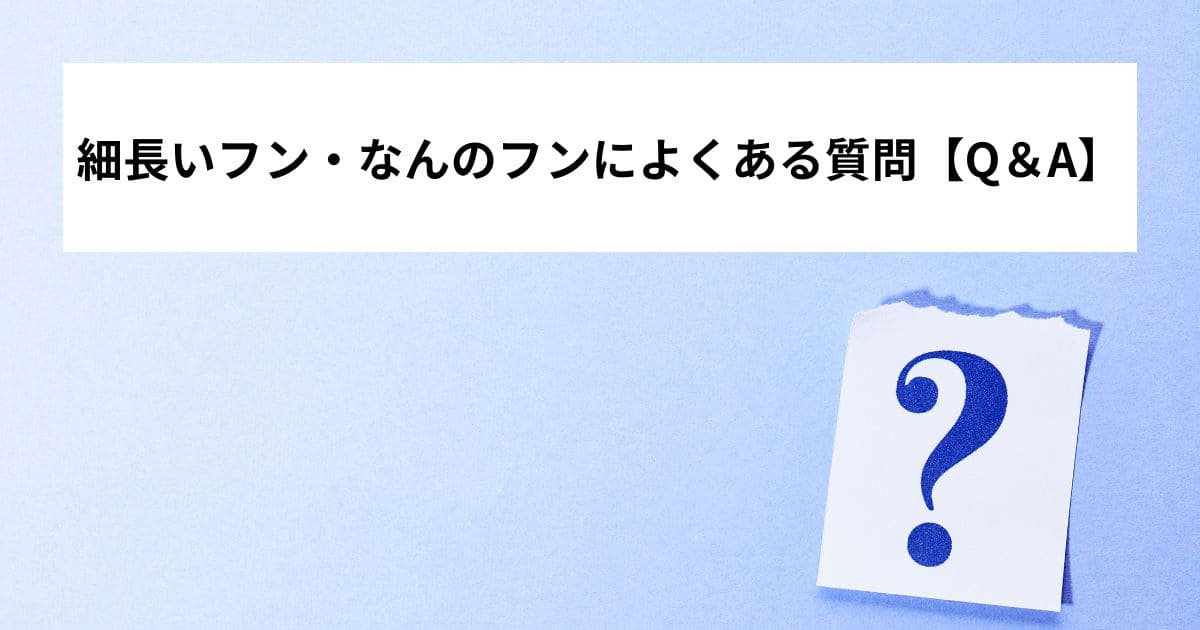
こちらでは、細長いフン・なんのフンに関するよくある質問にそれぞれ回答します。
- 細長いウンチの正体は?
- 細長いフンをする虫は何ですか?
- 1センチくらいの細長いフンはどんな動物が考えられる?
同じ質問をお持ちの方はもちろん、似ている疑問をお持ちの方はぜひご確認ください。
細長いウンチの正体は?
屋内や庭で見つかる“細長い黒っぽい塊”は、多くの場合、害獣のウンチの可能性が高いです。
特に以下の害獣のウンチは形状がよく似て判別が難しいため、間違えやすいです。
- ネズミ
- コウモリ
- イタチ
- ハクビシン
またイヌ・ネコの 回虫・条虫 など寄生虫も「白く細長い糸状」や「米粒状の片節」として便に現れるため注意しましょう。
これらの特徴を以下の表にまとめました。
| 細長いウンチの正体 | サイズ・形状 | フンの特徴 |
|---|---|---|
| ネズミ | 4〜10 mm・米粒状・両端が尖る | 散らばって落ちやすい |
| コウモリ | 5〜10 mm・米粒状だが握ると粉々・キラッと光る | 昆虫の殻が混じり、1 か所に堆積 |
| イタチ | 5〜6 mm・ねじれた細長さ・強烈な悪臭 | 毛が混ざり水分多め |
| ハクビシン | 5〜15 cm・バナナ形で太め | 種子が混ざり臭い弱い/溜めフン習性 |
| 回虫類 | 白い麺状(数 cm〜) | 便や嘔吐物に“白いヒモ” |
| 瓜実条虫 | 白い米粒状の片節 | 乾いた便に粒が付着 |
| コクヌストモドキ(穀物害虫)幼虫 | 3〜4 mm・淡黄〜茶色で細長い | 穀類保管容器内を移動 |
ネズミとコウモリはサイズが似ていますが、指でつまんで崩れるかどうかで判別できます。
崩れて粉状になるならコウモリの可能性大です。
フンを処理する場合は、必ずゴム手袋やマスクを着用し、万全を期すのであればゴーグルも装着しましょう。
細長いフンをする虫は何ですか?
フンの長さが、約6 mm〜1 cm、濃い茶〜黒く細長い場合は、イタチやクマネズミ、ドブネズミの成獣の可能性が高いです。
一方、ネズミのフンはイタチより乾いており、散乱しているケースが目立ちます。
1センチくらいの細長いフンはどんな動物が考えられる?
虫が細長いフンをしていると感じる場合、実際にはコウモリのフンか、犬猫の体内から排出された 寄生虫(回虫・条虫)であることが多いです。
| 生物(由来) | 形状・サイズ | 見分けポイント | 主な健康リスク / 注意点 |
|---|---|---|---|
| コウモリのフン | 5–10 mm の黒い粒 | ・指で潰すと粉状になり、昆虫の翅が混ざってキラキラ光る ・屋根裏、外壁の隙間など同じ場所に堆積しやすい | ヒストプラズマ症など呼吸器感染のリスク |
| 回虫 | 白〜淡黄のヒモ状 | 子犬・子猫の便や嘔吐物に混ざりやすい | 人獣共通感染症「トキソカラ症」を引き起こすことがある |
| 瓜実条虫 | 乾燥すると 米粒状(2 mm前後) の片節が便や肛門周囲に付着 | ノミを介して感染;片節が動き回るのが特徴 | まれに人にも感染し軽い腹部症状や皮膚炎を起こす |
病原菌や寄生虫リスクを避けるため、マスク・手袋・使い捨て袋を用意し、消毒剤で作業後の床面を拭き取りましょう。
「大量のフンが積み重なっている」「なんのフンかわからない」そんな場合は、ぜひハウスプロテクトの無料現地調査をご利用いただくことをおすすめします。
まとめ
細長いフンを見つけたら、まず1cm程度か5cm程度なのか確認してみましょう。
そこから形状や色、ニオイなどに注目し特定していきます。
フンを清掃する際は3つのNG行動に注意して慎重に行いましょう。
特にフンは病原体の媒介となる可能性があるので、直接触れてはいけません。
「病原体がこわい」「家族やペットのためにも早くなんとかしたい」そういった場合は、まずは一度、プロの害獣駆除業者へ相談してみてください。
Google口コミ評価業界トップクラスの「ハウスプロテクト」では、メール・電話相談をはじめ、現地調査や見積もり作成もすべて無料で承っておりますのでぜひお気軽にお問い合わせください。
\最短即日対応!相談のみOK/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。