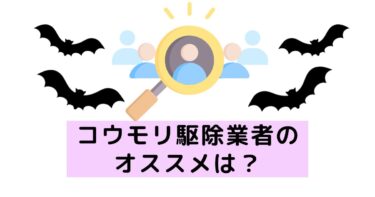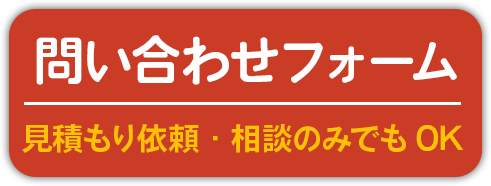「家にコウモリの巣らしきものを発見したという方」「家の中でコウモリの鳴き声が聞こえる」とお困りではないですか?
この記事ではコウモリの巣の特徴や見分け方、コウモリによる被害について詳しく解説しています。
コウモリが身近にいる方はぜひ読んでみてください。
巣の特徴:作られやすい場所について

まずは、コウモリの巣が作られやすい場所から見ていきましょう。
最初に結論をお話しすると、コウモリの巣が作られやすいのは、以下のような特徴の場所になります。
①雨風を防げて暖かい
②侵入するための隙間がある
③虫が集まりやすい
④ぶら下がる場所がある
①雨風を防げて暖かい
コウモリは人間と同じ恒温動物です。つまり、体温がをいつも一定に保たなければ死んでしまう動物です。そのため、これも人間と同じくですが、コウモリは、「雨風を防げて暖かい、体温を一定に保ちやすい環境」を好みます。
そんなコウモリが定住する巣を作る条件として、同じく恒温動物である人間が建てた人家は最適です。
具体的に人家の中でどういった場所に作られるかというと、人家の中でも特に熱がこもりやすい場所である「断熱材の入った壁の中」「太陽の熱で気温が上がる屋根裏」「エアコンの室外機の裏」などが多いです。
②侵入するための隙間がある
コウモリは、2cmほどの隙間があればそこから侵入できてしまいます。
2cm程の隙間がある場所を家の中で考えると、例えば、下記のような場所が当てはまります。
換気口・通風口
エアコンや室外機の配管の隙間
屋根と壁の隙間
シャッターの隙間
雨戸や戸袋の隙間
経年劣化などで壁にできたヒビ
特に、築年数の古い家にお住まいの方は、老朽化が進んで多くのヒビや隙間ができていることがありますので、注意してください。
③虫が集まりやすい
コウモリは、虫を食料にしています。そのため、虫が集まりやすい場所に巣を作るのも大きな特徴です。
例えば、「自然環境が豊かである」場合や「近くに川が流れている」「電灯が立っている」などのケースが、これに当てはまります。
このように近所に虫が多く集まりやすい場所があると、コウモリに巣を作られやすくなってしまいます。
④ぶら下がれる場所がある
周囲にコウモリがぶら下がれる場所がある場合も、注意したいところです。
こういった場所にいることで、コウモリは、陸上に住むヘビなどの天敵から身を守ることができます。安心できる場所を巣にするのは、動物としては当たり前ですよね。
では、どういった場所が「ぶら下がれる場所」に当てはまるかというと、「軒下や屋根裏など、家の柱や梁が多い場所」になります。こういった場所は、エサを探しに行くコウモリの休息場にされることも多く、それが転じて巣を作られるといったケースもあります。
巣の特徴:見た目について

コウモリの巣は、一般的に考えられるような「木材やおが屑を集めて、周囲を囲んていく」タイプのものではありません。巣を自分でつくるのではなく、巣になりそうな場所を間借りして生活するのがコウモリです。
見た目ではわからないので、巣であると予想される周辺で、羽音や糞の確認を取ることをお勧めします。
巣の特徴:実際の映像を紹介

下記の映像が、実際のコウモリの巣になります。この映像は、軒下の隙間にできたコウモリの巣の映像です。
わずかな隙間から続々と這い出てくるコウモリの姿には驚愕してしまいます。このケースの場合だと、30匹以上も潜んでいたとのことです。
引用元:「無限列車」ならぬ「無限コウモリ」軒下に住み着くコウモリを追い出す様子|ハウスプロテクトの害獣VLOG
この映像のような形で巣を作ることもありますので、ぜひ、参考にしてみてください。
巣の特徴:まとめ

ではここで、今まで解説した巣の特徴を、「①場所」と「②よく起こること」に分けて、下記にまとめてみました。
・断熱材の入った壁の中
・エアコンの室外機の裏
・窓やドアの隙間
・換気口・通風口
・エアコンや室外機の配管の隙間
・屋根と壁の隙間
・シャッターの隙間
・雨戸や戸袋の隙間
・経年劣化などで壁にできたヒビ
・自然環境が豊かである
・近くに川が流れている
・電灯が立っている
・軒下、屋根裏
コウモリの巣やその周辺でよく起こること
・羽音が聞こえる
・糞が落ちている
もしもコウモリの巣があるおそれが少しでも考えられるなら、お気軽にご相談ください!
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる屋内害獣に対応。
まずは被害状況をお聞かせください。
コウモリによる被害について

ここまでの文では、コウモリの巣の特徴について説明してきました。ここからは「もし巣を作られてしまっていたら」という前提で、想定されうるコウモリの被害について解説します。
騒音被害
まず、コウモリの羽音による騒音被害が予想されます。コウモリは夜行性ですので、夜になってから、飛び回る羽音が聞こえてくることが多いです。
コウモリの出す騒音によってイライラさせられるだけなら、まだ良い方かもしれません。騒音によって不眠になった結果、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病を引き起こしてしまう可能性もあるのです。
衛生的な被害
コウモリによる衛生的な被害も考えられます。
野生のコウモリは「ウイルスの貯水池」と呼ばれることがあるほど、さまざまなウイルスを保有するおそれがあります。
新型コロナウイルスのような、新しいウイルスを媒介する可能性もあるので、身近にいるのは不安になりやすいです。
また、コウモリに寄生しているダニが家に入り込んでしまうと、布団に入ってきて寝ている間に吸血することもあります。
刺された箇所の腫れやかゆみはもちろん、刺された後にアレルギーになってしまうこともあるので、たかがダニだと侮ってはいけません。
参考:
ダニアレルギーの症状や対策、治療法は? 咳やくしゃみの原因とは | バルサン | レック株式会社
例えコウモリに直接触れなかったとしても、コウモリの出す大量の糞尿は乾燥して崩れることで空気中に飛散します。
「コウモリが住み着いている」というだけでかなり不衛生だということが分かりますよね。
異臭被害
コウモリの排泄する糞尿によって起きる異臭被害も困りものです。
コウモリの糞尿から漂う「ドブのような臭い」に耐えられず、本来ならリラックスして過ごせるはずの自宅が、苦痛極まりない場所になってしまうというケースもあります。
コウモリ駆除専門業者に一刻も早い相談を
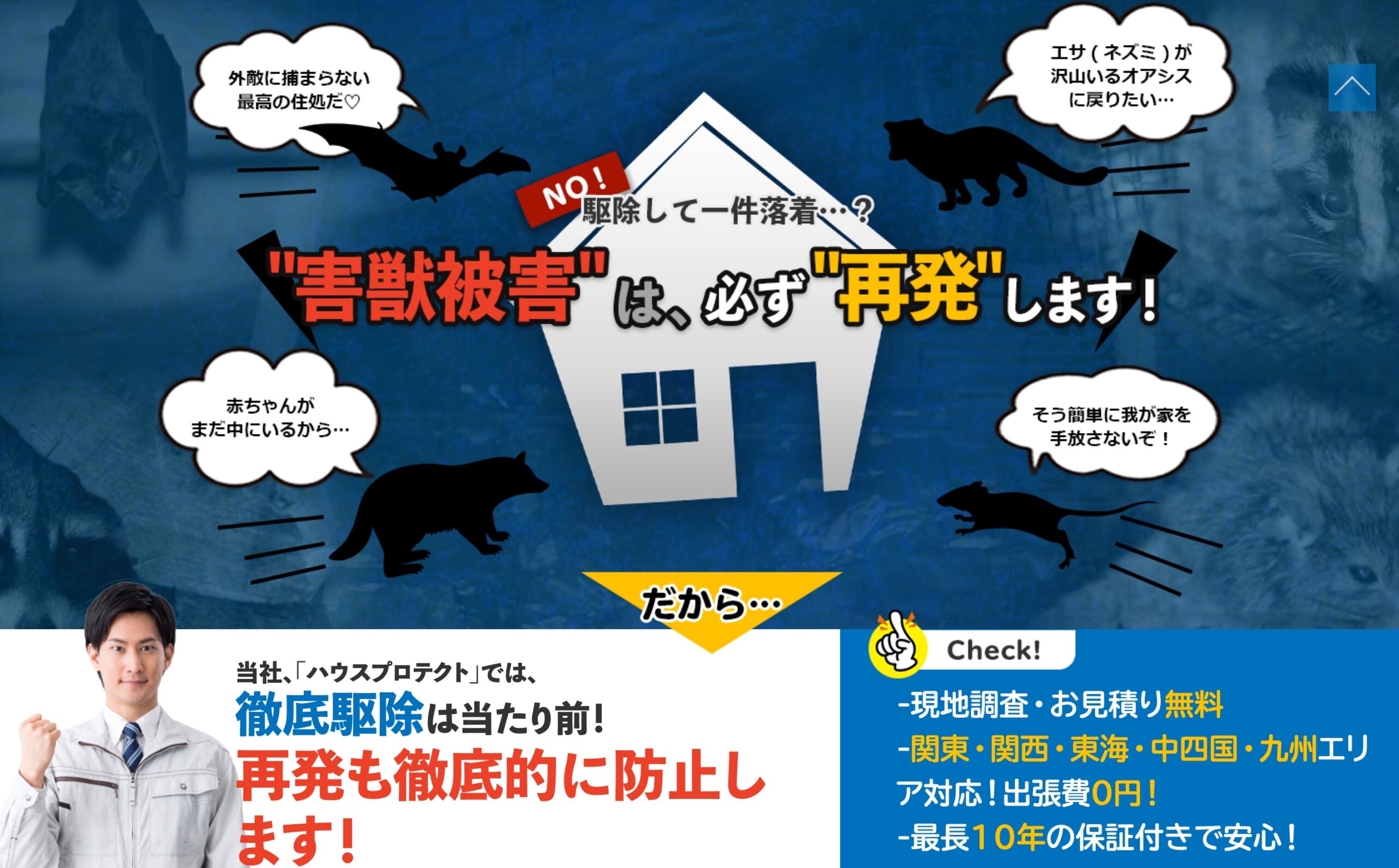
この記事を読んで、「ご自宅にコウモリの巣がある」と確信を持った方も、「もしかしたらあるかもしれない…」と疑惑止まりの方も、被害が拡大すれば、前項のような事態を引き起こしてしまいます。
かといって、コウモリ駆除を自力でしてみようとすると、最も大きな問題として降りかかるのが「コウモリの侵入可能な隙間を全て埋めることができるのか」という問題です。先ほど解説した通り、2cmの隙間ならば、コウモリはすり抜けてしまいます。衛生面の問題なども鑑みても、コウモリの駆除は専門家でなければ難易度が高いです。
コウモリがいる可能性が少しでもあるのなら、まずは一度、コウモリ駆除専門業者に問い合わせてみることをおすすめします。
「いきなり駆除依頼までするのは腰が重い」という方は、まずは相談だけでもしてみてください。コウモリ駆除専門業者のハウスプロテクトでは、無料で電話・メール相談を行っております。懇切丁寧にヒアリング、被害状況に応じて適切な提案を致しますので、まずはご相談ください。
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる屋内害獣に対応。
まずは被害状況をお聞かせください。