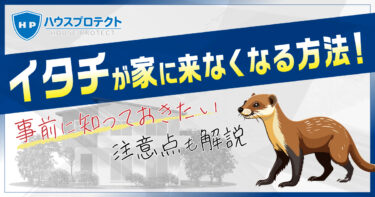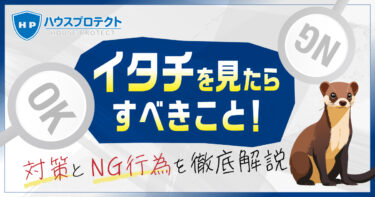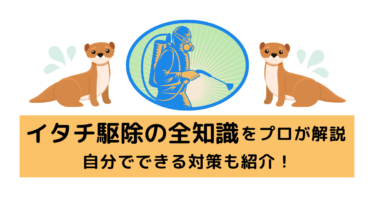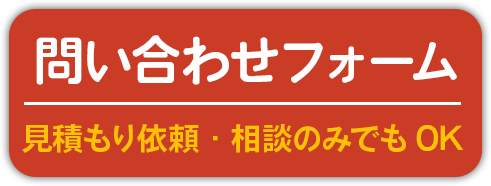イタチは、庭や畑、キャンプ場、人間の住家など、身近なところに現れ、人間の手を噛むこともあります。
突然のことにどうしたら良いか分からず、インターネットで対処方法を調べているうちに、このページに行き着いた方もいるかもしれません。
そこで今回は、イタチに噛まれたり引っ掛かれたりした場合の応急処置法や、イタチによる感染症について説明していきます。
イタチに噛まれた!引っかれた! 応急処置をすぐにするのが重要

イタチに噛まれた際にまず、確認したいのは傷口の大きさと深さです。傷口が大きく深ければ、骨や神経まで傷つき、傷跡が残ってしまうこともあります。
さらには、傷口から菌が入ってしまい、ひどくなることも。
もしイタチに噛まれたり引っ掛かれてしまったら、すぐに応急処置をしましょう。
まず、血を止めるために圧迫したり、心臓より高い位置に持ち上げたりして止血します。
次に、他のケガをした場合と同じように、傷口を水で洗ってください。イタチに噛まれた場所を清潔な水で洗い流しましょう。
そして、傷がどんなに浅くても病院に行ってください。基本的には皮膚科で良いですが、傷が大きければ外科のある病院に行きましょう。
参考:
外傷 – 25. 外傷と中毒 – MSDマニュアル家庭版
特に、噛まれた部分が動かせない場合や、血が止まらない場合には、急いで病院を受診してください。また、化膿したり熱が出たりして症状が悪化してから病院に行くのだと、治療がより大変になりやすいです。とにかく早めに病院に向かいましょう。
治療内容や処置の方法

イタチに噛まれて通院した場合、次の5つの治療(処置)を受けることになります。
②熱が出ている場合は血液検査と尿検査で炎症があるかを確認
③抗生物質の点滴 ・筋肉注射(化膿止めなど)の注射
④傷口を開いて雑菌がないかを確認・消毒(麻酔の有無は病院による)
⑤縫合(傷口の大きさによって行うかどうかが決まる)
傷口が何か所くらいあって、どのくらいの大きさと深さで、腫れの程度がどのくらいかにもよりますが、上記のような治療が一般的です。傷の状態によっては、敢えてしばらく傷口を開けたままにするケースもあります。
参考:
動物およびヒトの咬傷:傷口への対処方法は?病院受診のタイミングは?|お医者さんオンライン
イタチに噛まれた場合には、以上のような流れで治療を進めていきましょう。
身近にイタチがいると今後も危険なので、もしも不安ならお気軽にお問い合わせください!
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる屋内害獣に対応。
まずは被害状況をお聞かせください。
イタチから感染する感染症や病気
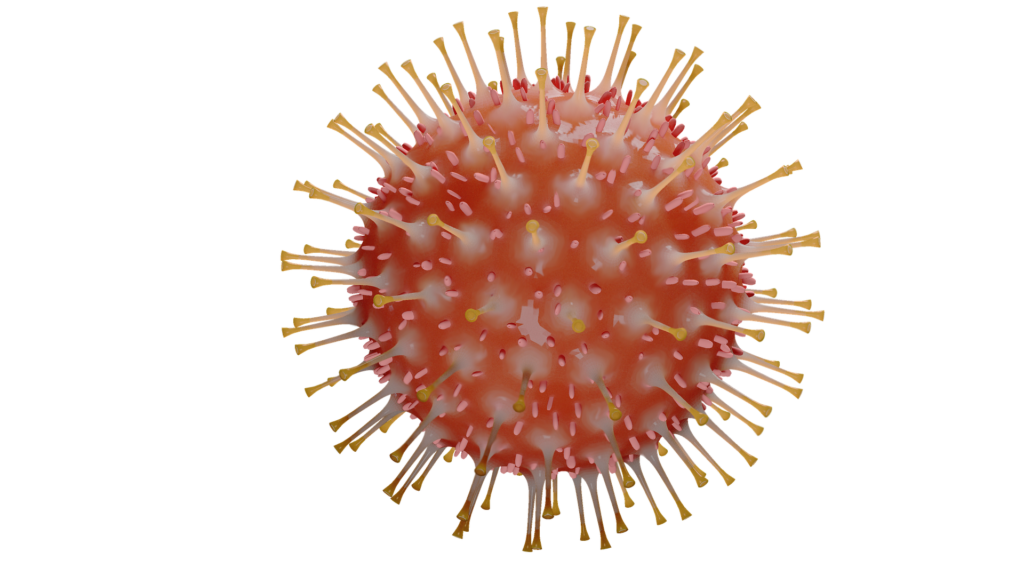
イタチに噛まれると出血したり傷口が残ったりするだけでも厄介なのですが、感染症や病気に罹ってしまうケースも多いです。
ここでは、イタチに噛まれた結果として罹る可能性のある3つの病気を紹介します。
鼠咬症(そこうしょう)
鼠咬症は、ネズミなどに噛まれて罹る感染症で、「ストレプトバチルス・モニリフォルミス」または「スピリルム・マイナス」の2種類の細菌が原因で発症する病気です。イタチは、ネズミやリスなどを捕食することから、そのイタチに噛まれると鼠咬症が発症してしまうケースが考えられるのです。
まず、「ストレプトバチルス・モニリフォルミス」によって感染すると、咬み傷が治癒して1日から3週間以内に発症することが多く、悪寒や発熱、筋肉痛、頭痛、嘔吐などのような症状が出ます。
麻疹ましんのような発疹が現れたり、痛みを伴う多発性関節炎を起こしたりします。心内膜炎、腎炎、肺炎、肝炎、髄膜炎膿瘍などに同時に罹ることもあります。
また、「スピリルム・マイナス」に感染すると、数日から約4週間後に発症し、悪寒、39℃前後の発熱、頭痛などの症状が出ます。噛まれた傷は、2週間の潜伏期間の間にいったん治癒するものの、発症するとリンパ節が腫れることもあります。
参考;
鼠咬症 – 16. 感染症 – MSDマニュアル家庭版
狂犬病
狂犬病は日本では罹るおそれが薄いですが、海外でイタチに咬まれた場合には注意が必要な病気です。
狂犬病に罹ると、以下のような症状が起きます。
- 発熱
- 頭痛
- 倦怠感
- 筋肉痛
- 疲労感
風邪のような症状からスタートするものの、かまれた部位の痛みや知覚異常も出てきます。
さらには脳炎の症状として水を怖がったり興奮したりといったことが起き、最後は昏睡からの呼吸停止となるおそろしい病気です。
参考:
狂犬病 – 厚生労働省 検疫所
蜂窩織炎(ほうかしきえん)
蜂窩織炎は、噛まれた傷口から細菌が侵入し、皮膚の表面や皮下組織にまで入ることで罹る感染症です。症状としては、皮膚が赤く腫れて炎症になったり、高熱や関節痛が出たりします。
抗生物質により治療されますが、再発を繰り返して症状が悪化すれば死亡するケースもあります。
実際、大分県大分市の公園において、男性警部補がイタチ科のフェレットにかまれて感染症になり、17年後に亡くなった事例があります。公園にいたフェレットを捕獲中に手を噛まれ、病院で感染症の蜂窩織炎と診断され、入退院を繰り返した末に亡くなっています。
参考:
蜂窩織炎(ほうかしきえん) – 巣鴨千石皮ふ科
17年前フェレットにかまれる 感染症で今年死亡、警部補公務災害に
いずれも必ずかかるわけではありませんし、すぐに病院に行けば過度に心配する必要はありませんが、そのような病気もあることを理解しておきましょう。
イタチの住処やイタチに遭遇しないために

昔はイタチの住処は山地や河川敷だけでしたが、現在では日本全土に広がっており、家の近所やゴミ捨て場、キャンプ場や山、川などどこでも見かけます。非常にすばしこく動き回れる害獣で、木や壁も垂直に上れます。
また、イタチは警戒心が強いため、人目の付くところに出て来るのを嫌うのですが、都市部でも人家の周りにも生息しており、餌や寝処を得るためには人家に入り込み、天井裏、床下、軒下や天井裏、物置などに棲み着きます。
頭が入るだけで侵入出来てしまうので、たった3cm四方の隙間があれば人家に入り込めてしまうのです。イタチに遭遇しないためには、そうした小さな穴も侵入経路となり得るので、徹底的に塞ぐことが重要です。
そして、イタチは獰猛な性格であり、人家に棲み着いたイタチを退治しようとすると、逆に噛みつかれる場合もあります。そのため、見た目が可愛くて近づきたくなる気持ちも分かりますが、絶対に近づいたり触ったりしてはいけません。
もし家屋内に入られてしまったら、一刻も早く屋外に追い出す必要があります。
イタチ駆除はプロにおまかせ

以上のように、イタチには噛まれると大怪我を負うだけでなく、病気に罹るケースもあり、イタチに遭遇しないための対処を行うことが大切です。
ですが、鳥獣保護法によって、イタチは保護されるべき対象となっており、一般の方が手を出すのは難しくなっています。また、狩猟法によってイタチをむやみに捕獲することは禁止されており、狩猟免許が必要になってきます。
そこで、イタチを駆除したいなら、イタチの駆除業者であるハウスプロテクトにお任せください。現地調査やお見積りは無料で行い、関東・関西・中国・四国・九州エリアに出張費なしで対応します。
イタチに噛まれて被害に遭った経験のある方や、自分で対応しようとして感染症に罹るのが怖い方は、是非ともハウスプロテクトにお任せください。
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる屋内害獣に対応。
まずは被害状況をお聞かせください。