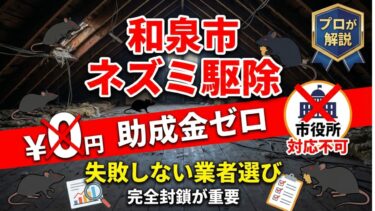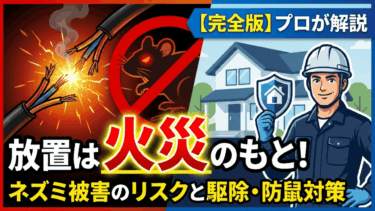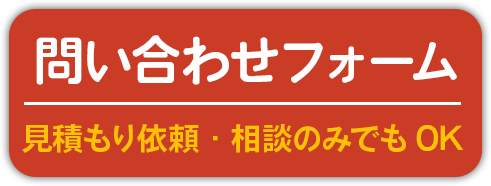「プラスチックや袋にかじられた跡がある…もしかして、これってネズミの仕業?」
見覚えのない噛み跡やかじられた跡がある場合、それはネズミの仕業かもしれません。
ネズミは、食べ物をはじめ、ビニール袋や電気コードなど、さまざまなものをかじります。また、ネズミがかじったものを介して、危険な病原菌やウイルスに感染するリスクがあるため、早急に対処しなければなりません。
そこで本記事では、ネズミが物をかじる理由をはじめ、「かじるもの4選」や「5つの対策」をハウスプロテクト監修のもとプロの目線で解説します。
この記事を参考に、これ以上ネズミ被害を拡大させないよう対策しましょう!
「もし自力でネズミ対策できそうにない…」といった場合は、まずは一度、プロの駆除業者に相談してみることをおすすめします。
\24時間365日受付中!相談のみOK/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
ネズミが物をかじる理由

「そもそも、なぜネズミは物をかじるの?」と疑問に感じますよね。
結論からお伝えしますと、ネズミが物をかじるのは歯を研ぐためです。
そのため、伸び続けたままでいると、口の開閉ができなくなり、餌が食べられなくなってしまいます。
こうした事態を避けるため、ネズミは一生涯にわたり、物をかじり続けます。
ネズミがかじるもの4選

ネズミは、主に次のようなものをかじります。
- 食べ物
- プラスチック
- 家の柱・壁・家具
- 電気コード
以下にて、それぞれ詳しく見ていきましょう。
食べ物
ネズミは雑食性の動物です。
そのため、キッチンやテーブルに置きっぱなしになっている食べ物、食べかけのものがあれば、なんでも齧ってしまいます。
家に住み着くネズミのうち、クマネズミの好物は、お米や小麦粉などの穀類やりんご、バナナなどの果物、サツマイモなどのイモ類です。
ハツカネズミの好物は、穀類と植物の種やニンジンなどの野菜、ドブネズミの好物は肉や魚などです。
つまり、穀物と果物、イモ類、野菜、肉、魚と人間が食べるものほぼすべてがネズミの餌になってしまいます。
プラスチック
食べ物の保管によく使われるプラスチック製の柔らかい袋やビニール袋も注意しなければなりません。
ジップロックなどは、スペースを有効活用できて、かつチャックも付いていて食べ物の保存に便利ですよね。
しかし、こういったプラスチック製の柔らかい袋は、ネズミにかじられてしまうことがあります。
したがって、食べ物の保存には、ガラス製のものなど硬い素材の容器を使うようにしましょう。
家の柱・壁・家具
ネズミは家の柱や出っ張り、壁、家具などをかじります。
そのほか、コンクリート製や木製の住宅、家具もかじるため、大事な住まいをボロボロにされかねません。
ネズミは金属製のもの以外は、ほとんどかじってしまうため、決して放置してはいけません。
電気コード
何でもかじるネズミは、電気コードもかじってしまいます。
ネズミが電気ケーブルをかじることで電気の供給が止まったり、機械が使えなくなる被害があります。
かじられた電気ケーブルは、保護されていたケーブル内の導線部分がむき出しになってしまいます。
そして、導線がむき出しになったケーブルに気づかず、そのまま電気を流そうとすると漏電を起こし、火災に繋がってしまうのです。
参考:宮城・栗原市10数軒焼失の火事 ネズミが電気配線をかじったことによる漏電が原因か
ちなみにネズミにとって、電気コードくらいの硬さは「歯を削るのにちょうどいい硬さ」ですので、電気コードをかじられる可能性はかなり高いと言えます。
漏電ブレーカーがあれば安心なのか?
築年数の浅い家にお住いの方は、「我が家には、漏電ブレーカーがあるから電気ケーブルをかじられても大丈夫」と思ったかもしれません。
しかし、漏電ブレーカーにネズミが入り込んで火災が起きるケースもあります。
参考:消防防災博物館「動物が原因 で出火した火災事例について」)
以上のように、ネズミは、大切な家や財産、さらには家族の健康や命まで脅かす存在です。
「家の中にネズミがかじったような跡がある」「うちも火事になったらどうしよう…」と不安に感じる場合、まずはプロの害獣駆除業者へ相談することをおすすめします。
累計10,000件以上の駆除実績がある「ハウスプロテクト」では、出張費をはじめ、現地調査や見積もり作成も全て無料で承っております。
「あの時、相談していたら…」と後悔しないよう、ぜひこれを機に問い合わせてみることをおすすめします。
\24時間365日受付中!相談のみOK/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
ネズミにかじられたものは二次被害を引き起こす
ネズミの唾液には、菌が含まれています。
具体的には、「鼠咬症(そこうしょう)」と呼ばれる病原菌をドブネズミで98%、クマネズミで58%の確率で口腔内に常在していると言われています。
ちなみに、ネズミがかじった跡に残る唾液からも菌やウイルスが拡散されます。
そのため、ネズミにかじられたものをはじめ、それ以外にも菌やウイルスが付着していないか注意しなければなりません。
参考文献:
谷川 力、家ネズミ類の生態・被害と防除、環境と病気、2009、18巻、1‐2号、 p. 1-6、環境と病気学会、ISSN 13409476 (参照2024-1-18)
MSDマニュアル(鼠咬症)
ネズミが保有している病原菌やウイルス【一覧表】
下記3つのネズミは総称して「家ネズミ」と呼ばれ、家屋に住みつきます。
- ドブネズミ
- クマネズミ
- ハツカネズミ
そんな家ネズミがもたらす被害の中でも、最も注意すべきなのが『人獣共通感染症(ズーノーシス)』への感染リスクです。
ネズミが持つ病原菌、ウイルス、細菌は多岐にわたり、感染症を含めた多くの病気を引き起こします。
以下、ネズミが保有している病原菌やウイルスの一覧表となります。
| 病名 | 感染源 | 感染経路 |
| 鼠咬症(そこうしょう) | ネズミの唾液 | ネズミに咬まれたり、汚染された食べ物や飲み物を摂取した場合 |
| レプトスピラ症 | ネズミの尿 | 尿で汚染された水が皮膚や傷口、口に入った場合 |
| サルモネラ症(食中毒) | ネズミの糞尿 | 糞尿で汚染された食品を摂取した場合 |
| ペスト | 感染ネズミに寄生していたノミ | 感染したネズミに付着しているノミに刺された場合 |
| 腎症候性出血熱(じんしょうこうせいしゅっけつねつ) | ネズミの糞尿、血液、死骸 | 感染源を吸ったり、口に入った場合 |
| 広東住血線虫(かんとんじゅうけつせんちゅう) | ネズミのフン | 生野菜に付着していたナメクジやカタツムリなどを誤飲 ※1. |
上記の病原菌やウイルス以外にも、ネズミは多くの健康被害をもたらします。
参考文献:
厚生労働省(動物由来感染症)
「東京都ねずみ防除指針」被害の実態(平成17年2月発行)- 東京都福祉保健局
実際に、ネズミを原因とする感染症の発生例は多数報告されており、その脅威は決して軽視できません。
特に小さなお子さんや高齢者の方、ペットのいるご家庭では、これらの健康被害に遭う可能性が高いため、早急に対策しましょう。
もし「子どもやペットが被害に遭ったらどうしよう…」と不安に感じる方は、まずは一度、プロの専門業者に相談することをおすすめします。
クチコミ・実績業界トップクラスを誇る「ハウスプロテクト」では、出張費をはじめ、現地調査も無料で対応してくれるので被害が拡大する前に、ぜひ一度ご相談ください。
\24時間365日受付中!相談のみOK/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
ネズミがかじった跡のものはどうする?
ネズミは様々な病原体を持っている可能性があり、不衛生な環境にいることが多い動物です。
食べ物をそのまま放置しておくと、袋に入れていてもネズミの鋭い前歯で簡単に破られ、かじられる可能性があります。
そのため、ネズミがかじった跡は廃棄、もしくは徹底的に殺菌・消毒しましょう。
ネズミがかじった跡のある食品の扱い
ネズミにかじられた食品は、健康被害に遭わないよう全て廃棄してください。
なぜなら、ネズミの唾液や糞尿が付着している恐れがあるからです。
たとえ、かじられた箇所が少なくても、万が一、ネズミがかじったことに気づかずに口に入れてしまった場合は、食べるのを中断し、全て廃棄しましょう。
また、かじられた食品の近くにあった他の食品も、念のため汚染されていないかを確認し、少しでも異変や汚れが見られる場合は安全を優先し、廃棄することをおすすめします。
体調不良時の対応
もしネズミがかじった食品を食べてしまった後に、発熱、吐き気、下痢などの体調不良があれば、すぐに病院で診察を受けてください。
心配な場合は、体調に変化がなくても医師に相談することをおすすめします。
ネズミの種類別の好物と保管の注意点
ネズミは種類によって好物が異なります。
特に被害に遭いやすい食品は、保管方法に注意が必要です。
| ネズミの種類 | 好物(特に注意が必要な食品) |
| クマネズミ | 米、小麦粉などの穀類、りんご、バナナなどの果物類、サツマイモなどのイモ類 |
| ハツカネズミ | 穀類、植物の種、ニンジンなどの野菜類 |
| ドブネズミ | 肉、魚 |
これらの食品は特に狙われやすいため、密閉容器に入れるなど、徹底した保管対策を講じましょう。
食品以外の物品の扱い
ネズミがかじった食品以外の物品についても、適切に対処しましょう。
食べ物やゴミ袋、洋服など日頃から口や手に触れる機会が多いものは、病原体の付着リスクを考え、廃棄することをおすすめします。
また、すぐに廃棄できないものや口や手に触れる頻度が低い物品については、徹底的に殺菌・消毒を行いましょう。
ネズミの被害は健康被害につながる可能性があるため、「もったいない」という気持ちよりも「安全第一」の判断を心がけることが大切です。
ネズミにかじられないための5つの対策

ネズミにかじられないためには、次の5つの方法があります。
- 頑丈な容器で保管する
- 冷蔵庫に入れる
- 布製品・紙・ダンボールを放置しない
- ネズミを追い出す
- 侵入経路を特定し塞ぐ
以下でそれぞれ詳しく説明しますのでぜひ参考にしてみてください。
頑丈な容器で保管する
ネズミの歯の硬度は、モース硬度で5.5と非常に硬く、かじる対象は硬度3.5以下のものがほとんどです。
かじる際は、上の歯で物を抑え、下の歯で削るようにするため、でこぼこしたコンクリートや劣化してひび割れた箇所くらいだと、簡単にかじられてしまいます。
これを防ぐには、以下の容器を使用しましょう。
| 容器 | 詳細 |
| ツルツルした曲面のガラス容器 | ネズミが歯を引っ掛けにくく、しっかり蓋をすることでかじられる被害を防げます。 |
| 金属製のケース | 湿気に弱いカップラーメンやインスタント袋麺などは、結露による品質低下の恐れがあるため、金属製のケースで密閉保存するのがおすすめです。 |
冷蔵庫に入れる
ネズミは、非常に優れた嗅覚でわずかな食べ物のニオイも察知します。
特に下記のような家庭によくある食べ物は、かじって荒らされる傾向があります。
- 未開封の袋
- 仏間のお供え物
- ペットフード
- 切り餅
- パン
- カップラーメンやインスタント袋麺
食べ物への執着が強いネズミの被害を防ぐには、その侵入を防ぐだけでなく、「かじられない」「ニオイを漏らさない」ための保管対策が不可欠です。
布製品・紙・ダンボールを放置しない
ネズミは身体が小さいため、暖かい場所を好む習性があります。
ちなみに気温が10度以下になると、動けなくなって冬眠してしまうと言われています。
そのため、保温性のある布製品や紙、段ボールはネズミの巣の材料となる可能性が高いです。
これらは放置せずに、不用なものは処分して、使うものは収納するように心がけましょう。
ネズミを追い出す
ネズミの被害対策として、忌避剤(きひざい)は、特定の場所への侵入や食害を一時的に防ぐのに役立ちます。
そんなネズミの鋭い感覚を利用し、「味覚」と「嗅覚」に訴える製品が市販されています。
味覚忌避剤(防鼠テープ・スプレー)の活用
ネズミが嫌う成分を配合することで、かじらせない効果が期待できます。
| 項目 | 詳細 |
| 使用製品と効果 | ネズミが苦手とする唐辛子(カプサイシン)成分を配合した防鼠テープや忌避スプレーなどがあります。 |
| 適切な使用箇所 | 袋、配線ケーブル、配管など、ネズミにかじられやすい部分に吹きかけたり、巻き付けたりすることで、その箇所に触れるのを嫌がらせ、部分的な忌避効果が期待できます。 |
嗅覚忌避剤(置き型・スプレー)の活用
ネズミが嫌がる特有のニオイを利用して、その空間全体を守る方法です。
| 項目 | 詳細 |
| 使用製品と効果 | ミントやハッカなどの天然ハーブ系成分を使用した、置き型タイプ、袋タイプ、スプレータイプなどがあります。 |
| 適切な使用箇所 | ネズミにかじられた跡がある場所だけでなく、ネズミの通り道や侵入口付近に設置・噴霧することで、ネズミをその場所に近づけさせない空間忌避剤として機能します。 |
忌避剤は便利な対策グッズですが、その効果は一時的です。
また忌避剤のニオイや成分は、時間の経過とともに薄れていくため、被害のレベルが高い場合や、すでにネズミが住み着いている場合は、忌避剤だけでは追い出せない場合があります。
したがって、忌避剤はあくまでも補助的な対策とし、ネズミの侵入口を塞ぐ、清掃を徹底するなど、他のネズミ対策と組み合わせて使用することが重要です。
ネズミの嫌いな匂いをより詳しく知りたい方は、以下の記事よりご覧ください。
侵入経路を特定し塞ぐ
ネズミにかじられた場合、家のどこかに侵入経路があるため、すべて特定し、徹底的に塞ぐ必要があります。
そんなネズミは、約1.5cm~2cm程度のわずかな隙間があれば、どこからでも侵入できるため、侵入経路は多岐にわたります。
以下にネズミの主な侵入口をまとめましたのでぜひご参考ください。
| ネズミの主な侵入口 | 詳細 |
| 配管・配線周り | ・水道管 ・排水管 ・ガス管 ・電線 ・エアコンの配管を通す穴の隙間 |
| 建物の隙間 | ・床下の通気口 ・屋根、壁の隙間、ひび割れ ・増築部分のつなぎ目 |
| 換気設備 | ・換気扇 ・通気口の格子 |
| その他 | ・雨戸の戸袋 ・玄関の戸袋や鴨居など ・ブレーカーボックス ・排水口や通気口 |
ネズミの侵入口が特定できたら、下記を使い、隙間をふさぎましょう。
- セメント
- 金網
- 防鼠ブラシ
- ふさぎ用粘土
- 防鼠パテ
- 金像板
特に金網は、ネズミが噛み破れないように5mm以下の目の細かいものを選ぶことが重要です。
「自力で侵入経路を特定し封鎖できそうにない…」と感じた方は、プロの専門業者に相談することをおすすめします。
リフォーム会社が母体となっている「ハウスプロテクト」では、建築の知識も駆使し、ネズミの侵入経路を特定してくれます。
ちなみに出張費や現地調査は全て無料ですので、ネズミの侵入経路を特定したい方はぜひ活用しましょう!
\24時間365日受付中!相談のみOK/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
ネズミに二度とかじられたくない場合は駆除業者へ相談しよう!
ここまで紹介した対策を実践すれば、ある程度、ネズミ被害は防げるかもしれません。
しかし、ネズミは非常に賢く、警戒心も強いため、ご自身での対策だけでは、根本的な解決に至らないケースがほとんどです。
なぜなら、ネズミ駆除は、その種類や習性を正確に把握し、侵入経路をすべて見つけ出し塞ぐ必要があるため、専門知識と経験が不可欠だからです。
また素人判断で侵入口を塞いでも、思いもよらない、わずかな隙間から再び侵入されてしまうことも珍しくありません。
一方、プロの駆除業者の場合、ネズミを追い出すだけでなく、再発防止策を徹底的に行います。
ネズミのフンや尿が残っていると、そのニオイが他のネズミを引き寄せる原因となりますが、業者であれば、専用の薬剤で徹底的に清掃・消毒・消臭まで行い、衛生的な環境を取り戻してくれます。
このように、一時的な対策ではなく、二度とネズミに悩まされない生活を取り戻すためには、専門の駆除業者に相談することが根本的に解決できる方法と言えるでしょう。
ネズミのかじった跡を見つけたら「ハウスプロテクト」へ無料相談しよう!
家のどこかでネズミがかじった跡を見つけてしまうと、「被害はこれだけ?」「病原菌やウイルスから感染したらどうしよう…」と、不安な気持ちになりますよね。
そんな場合は、まずは一度、害獣駆除専門の「ハウスプロテクト」に相談してみてください。
経験豊富なプロが、ネズミの種類や行動パターンを特定し、わずかな隙間も見逃さず、すべての侵入経路を確実に封鎖します。
また、不衛生なフンや尿の清掃・消毒まで徹底的に行ってくれるため、ネズミが住み着く前の衛生的な環境を取り戻したい方におすすめの業者です。
「とりあえず被害状況だけでも知りたい」「料金がいくらかかるか見積りを作ってほしい」といった場合でもかまいません。
「ハウスプロテクト」では、出張費をはじめ、現地調査や見積もりの作成まで、すべて無料で対応してくれるので、ぜひこれを機にお問い合わせしてみることをおすすめします。
「あの時、相談していれば良かった…」と後悔する前に、まずはプロによる無料相談を活用してみませんか?
\24時間365日受付中!相談のみOK/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
「実際にハウスプロテクトを利用した方々の口コミ・評判を知りたい」「ハウスプロテクトを依頼するメリットを知りたい」といった方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
ネズミがかじった跡に関するよくある質問【FAQ】
こちらでは、ネズミがかじった跡によくある質問をまとめました。
- ネズミがかじった跡に菌は存在する?
- ネズミにかじられた後はどうしたらいい?
- 米や米袋をネズミにかじらせない対策はある?
- ネズミがかじれないものは?
同じ疑問を抱えている方はもちろん、似た質問をお持ちの方もぜひご参考ください
以下で詳しく見ていきましょう。
ネズミがかじった跡に菌は存在する?
はい、存在する可能性が非常に高いです。
ネズミは下水やゴミ捨て場といった不衛生な場所を移動しており、その体や唾液、糞尿にはサルモネラ菌やレプトスピラ菌など、さまざまな病原菌やウイルスが付着しています。
そのため、ネズミがかじった跡にはこれらの菌が存在すると考えるべきです。
したがって、かじられた食べ物は絶対に口にせず、すぐに廃棄してください。
食べ物以外の場合でも、清掃・消毒を徹底するか、安全を最優先に考えて処分を検討しましょう。
ネズミにかじられた後はどうしたらいい?
ネズミがかじった跡は、健康被害のリスクがあるため、食品はすべて廃棄し、かじられた場所は徹底的に消毒する必要があります。
もし、家電のコードがかじられている場合は、漏電による火災の原因となる可能性があるため、すぐに家電の使用を中止しましょう。
また、ネズミに噛まれた場合は、病原菌やウイルス、感染症(鼠咬症、レプトスピラ症、腎症候性出血熱など)のリスクがあるため、すぐに医療機関を受診してください。
米や米袋をネズミにかじらせない対策はある?
最も効果的な対策は、購入後すぐに硬い密閉容器に移し替えることです。
米袋のまま保管していると、ネズミは簡単に食い破ってしまいます。
ガラス製や金属製、硬質のプラスチック製など、ネズミの歯が通らない頑丈なフタ付きの容器で保管しましょう。
また、米びつを置いている場所の周辺を常に清潔に保ち、米ぬかなどが落ちていない状態を維持することもネズミを寄せ付けないために重要です。
ネズミがかじれないものは?
ネズミは非常に強力な歯を持っていますが、かじれないものも存在します。
具体的には、ステンレスや鉄などの硬い金属、ガラス、陶器などが挙げられます。
ネズミの歯は硬いものの、鉄やステンレスには歯が立ちません。また、ガラスや陶器は表面が滑らかで硬いため、歯を引っ掛けてかじることが困難です。
まとめ
ネズミが物をかじる理由は、伸び続ける歯を削るための本能的なものですが、それによって引き起こされる被害は深刻です。
食べ物への汚染による健康被害はもちろん、電気コードをかじられることによる火災のリスクは、私たちの安全な生活を根底から揺るがしかねません。
ご自宅でネズミがかじった跡を見つけた場合は、まず身の回りの安全を確保することから始めてください。
かじられた食べ物は迷わず廃棄し、周辺の清掃・消毒を徹底してください。そのうえで、食品を頑丈な容器で保管したり、侵入経路となりそうな隙間を塞ぐといった対策を講じましょう。
しかし、ネズミは非常に賢く、繁殖力も高いため、ご自身での対策だけでは根本的な解決が難しいのが実情です。
「ネズミがかじったものを口や手に触れていたらどうしよう…」「これ以上、被害を拡げたくない」といった場合は、ぜひ一度プロの駆除業者に相談してみることをおすすめします。
本記事で紹介した「ハウスプロテクト」では、相談をはじめ、現地調査も無料で行っていますのでぜひお気軽にお問い合わせください。
ネズミ被害を根本的に解決し、衛生的な暮らしを取り戻しましょう!
\24時間365日受付中!相談のみOK/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
「ハウスプロテクト以外のネズミ駆除業者も知りたい!」といった方は、以下の記事もあわせてご覧ください。