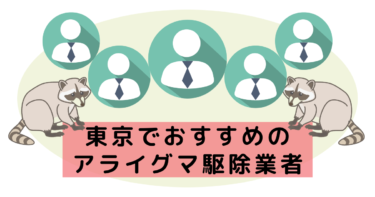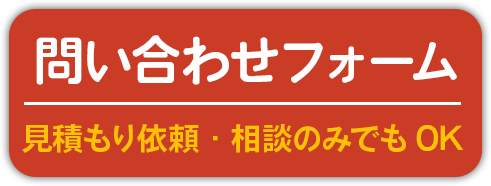「家の中でクルルルという動物の鳴き声が聞こえる」
「近所でアライグマの目撃情報があった」
これらにあてはまる場合、アライグマ、もしくは他の動物がお住まいに棲み着いている可能性があります。
近年、市街地や住宅街でアライグマの目撃情報や被害報告が増えています。
そこで本記事では、アライグマの鳴き声をはじめ、他の害獣や害鳥との鳴き声の違いをプロの目線で解説します。
さらに、放置すると起こりえる危険性や対処法についても紹介!
この記事を参考に、鳴き声の正体を特定し、被害が拡大しないよう対処してまいりましょう!
アライグマの鳴き声について

アライグマの鳴き声は、通常時と威嚇・喧嘩時で異なります。
以下で、それぞれの鳴き声の特徴を確認してまいりましょう!
通常時の鳴き声
アライグマは基本的に「クルルル」「クックッ」「キュッキュッ」と、小刻みに鳴きます。
赤ちゃんアライグマの場合、大人のアライグマよりも高く、「クルクル」と鳥の鳴き声のようにも聞こえるのが特徴的です。
特に親を探しているときや、空腹を知らせるときなどに鳴く傾向があります。
威嚇・喧嘩時の鳴き声
威嚇・喧嘩時のアライグマは、「ギューッギューッ」「シャーシャー」「ウゥゥ」と低く唸るような声や鋭い音で鳴きます。
主に繁殖期のオスのアライグマが、身の危険を感じたときに発することが多い鳴き声です。
またアライグマは、かわいらしい見た目に反して気性が荒く攻撃的な性格をしています。
これらの鳴き声が、屋根裏や床下など身近な場所から聞こえる場合、アライグマに棲みつかれている可能性が高いです。
後ほど改めて紹介しますが、「狂犬病」にかかったアライグマに嚙まれ、感染し発症した場合、ほぼ100%死に至ります。
また2025年6月現在も治療法はありませんので、自力での対策は避けるべきでしょう。
プロの駆除業者「ハウスプロテクト」では、通話料をはじめ、現地調査も無料で行っております。
相談のみでもかまいませんので、不安な方はぜひお気軽にお問い合わせください。
\無料!ハウスプロテクトへ相談/
アライグマと間違えやすい害獣の鳴き声

アライグマ以外ですと、次の害獣や害鳥の鳴き声かもしれません。
- タヌキ
- イタチ
- ハクビシン
- テン
- ネズミ
- コウモリ
- ムクドリ
このようにアライグマ以外にも、さまざまな害獣や害鳥が考えられます。
これらの害獣や害鳥が棲み着いていた場合、それぞれに合わせた対処法があるため、まずは鳴き声の正体を特定する必要があります。
害獣や害鳥の被害に遭わないためにも、それぞれの鳴き声を確認してまいりましょう!
タヌキの鳴き声
タヌキはイヌ科の動物であるため、鳴き声もイヌに似ており、「キューン」「ヴー」「キャン」のような鳴き声を発します。
子どものタヌキも「キュンキュン」「クゥーン」と子犬のような鳴き声を発します。
またタヌキはアライグマと外見が似ていて間違えやすいので、鳴き声以外の痕跡も探したうえで判断したほうが良いでしょう。
鳴き声以外でのアライグマとの見分け方をお伝えしておくと、下記のとおりになります。
②顔の違い:タヌキは目の周りから、首にかけて黒い毛に覆われている。耳のふちは黒く、ひげも黒い。それに対して、アライグマは、眉間から鼻にかけて黒い線がある。耳のふちは白く、ひげも白い。
ちなみにタヌキが棲み着いた場合、悪臭やカビ、騒音、農作物を食い荒らす可能性がありますので放置は厳禁です。
イタチの鳴き声
イタチの鳴き声は、「キッキー」「クククク」「キャッキャッ」といった鋭く高い音が特徴的です。
威嚇や喧嘩の際には「キッキッキー!」といった、さらに大きく激しい鳴き声をあげることもあります。
また、子どものイタチも同様に甲高い声で「ピキュピキュ」「キュイ」といった鳴き声を発します。
そんなイタチが家屋に侵入すると、糞尿による悪臭や天井裏の汚損、配線のかじりによる火災リスクなどの深刻な被害を引き起こす可能性もあるため、早めの対処が重要です。
ハクビシンの鳴き声
ハクビシンは、「キーキー」「ギャアギャア」といった鋭く響く声で鳴くことがあります。
また威嚇やケンカの際には「ウゥゥ…」「キャアア」といった唸り声や、「ガゥ」と低くうなるような声を発するのが特徴的です。
また、子どものハクビシンも甲高い声で「クルル」「ピィーィィ」「キュキュキュ」と鳴きます。
さらに、寄生するダニやノミが室内に広がるリスクもあり、放置するほど被害は深刻化します。
テンの鳴き声
イタチと姿がよく似たテンですが、その鳴き声には明確な違いがあります。
テンは「フィヤフィヤー」「ギュッギュッ」「キャッキャ」といった、やや甲高く独特な声で鳴くのが特徴的です。
威嚇する際には「ギューウー」と低く唸るような声を上げ、警戒心の強さがうかがえます。
また、テンの赤ちゃんは「ヂィー、ヂィー」といった高い音で鳴き、こちらも他の害獣とは異なる鳴き声です。
さらに、気性が荒く捕獲も難しいため、早期の発見と専門業者による対処が重要です。
ネズミの鳴き声
ネズミの鳴き声といえば「チューチュー」を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし実際には、「キューキュー」「キュッキュッ」「ピーピー」「キーキー」といった、高音でかすれたような鳴き声を発します。
ネズミは状況によって鳴き方が変わるのが特徴的です。
嬉しいときにはやや高めの声、威嚇や警戒時には低めの鳴き声を出すなど感情に応じて音のトーンが変化します。
また糞尿による悪臭や病原菌の拡散を引き起こすなど、健康面・生活面に深刻な被害を及ぼします。
そのため、小さな音でも異変を感じたら早めに確認し対処すべきです。
コウモリの鳴き声
コウモリの鳴き声は、「チチチチ」「チュチュチュ」「ブツブツブツ」といった、まるで夏に鳴く虫のような音が特徴的です。
その音は非常に小さく、気付かないうちに屋根裏などに棲みついてしまうこともあります。
コウモリは視力が弱く、超音波を発して周囲の状況を把握しながら飛び回るため、人間の耳に届くほどの大きな鳴き声を出すことは稀です。
また、コウモリは「鳥獣保護法」の対象で勝手な駆除ができないため、被害が疑われる場合は専門業者へ相談することをおすすめします。
ムクドリの鳴き声
ムクドリは、「ギャーギャー」「ギュルギュル」といった甲高く騒がしい鳴き声が特徴的な害鳥です。
その他、糞害や巣作りによる被害、農作物への被害も引き起こしかねないため、自力での対策が難しい場合は、専門の駆除業者に相談することをおすすめします。
アライグマの鳴き声を放置したら起こりえる被害

騒音
アライグマは成体で4〜10kgと、人間の赤ちゃんと同じくらいの重さです。
家に侵入する害獣の中でも重い部類のアライグマは、足音が大きくなりがちです。
また、アライグマは夜行性の動物ですので、人が寝静まる時間になると、天井裏をドタバタと走り回り睡眠を阻害します。
屋根裏に住み着いたアライグマが1匹とは限りません。
ちなみに数匹単位の家族で住んでいた場合、かなりの騒音になります。
糞尿被害

アライグマが人家に侵入し、屋根裏などにそのまま住み着いてしまうことはよくあります。
家に住み着いたアライグマは「ためフン」といって、同じ場所に糞をするのですが、その結果、糞の下にある天井板はどんどん脆くなっていきます。
そんなボロボロの建材に糞やアライグマの重さがのしかかることによって、その部分だけ天井が抜けてしまうこともよくあります。
また糞尿を放置しておくと「虫が湧く」「悪臭を放つ」など、かなり不衛生な環境になります。
屋根裏という場所は、糞尿自体を見つけにくく、仮に見つけられたとしても簡単に掃除ができない場所ですので、アライグマがいなくならない限り改善は難しいです。
そのため、アライグマに住み着かれた場合、高い確率で異臭に悩まされることになります。
農作物や生ゴミへの被害
感染症のリスク
先ほども触れましたが、野生生物であるアライグマやアライグマの糞は病原菌やウイルスの温床です。
アライグマ由来の主な病原菌・感染症は以下のとおりです。
| 病原菌・感染症 | 説明 |
| 狂犬病 | ウイルス性疾患で、アライグマに噛まれることで感染。発症すればほぼ100%死亡する極めて危険な感染症。 |
| アライグマ回虫症 | アライグマの糞に含まれる回虫卵が経口感染し、幼虫が人の脳や神経に侵入して重篤な脳炎や神経障害、死亡例も報告されている。 |
| 重症熱性血小板減少症候群(SFTS) | アライグマに付着したマダニから感染。発熱や消化器症状を伴い、致死率が6~30%と高い。 |
| レプトスピラ症 | アライグマの尿や糞で汚染された水や土壌を介して感染。頭痛、発熱、悪感、筋肉痛、吐き気、下痢や腹痛、発疹などを引き起こす。重症化するとワイル病となり、死亡例もある。 |
| 日本脳炎ウイルス | アライグマの血を吸った蚊を介して感染。成人での致死率が20~40%と高く、重篤な後遺症を残すこともある。 |
| サルモネラ症 | アライグマの糞などを介してサルモネラ菌に感染。発熱・下痢・嘔吐などを引き起こし、子どもや高齢者では重症化の恐れ。 |
| カンピロバクター食中毒 | アライグマの体や糞からカンピロバクター菌が感染し、下痢・腹痛・発熱などの症状を引き起こす。 |
| 疥癬(かいせん) | アライグマの体表にいるヒゼンダニが皮膚に寄生し、強いかゆみや発疹を引き起こす。 |
| エキノコックス症 | アライグマが保有するエキノコックス(寄生虫)による感染症。肝臓などに寄生し重篤化する場合がある。 |
| プロビデンシア属細菌感染症 | アライグマの糞から検出されることがあり、集団食中毒の原因となることがある。 |
参考:
外来種対策マニュアル 参考資料 ① アライグマ・ハクビシンに関する主な人獣共通感染症 – 東京都環境局
これらの感染症は、アライグマとの直接接触や糞尿、寄生虫、アライグマに付着したマダニや蚊などを介して感染する可能性があります。
「鳴き声だけだし、まぁいいか」とアライグマを放置していると、取り返しのつかないことになりかねません。
奈良県の公式ホームページによると、奈良県内では過去、レプトスピラ菌に感染したアライグマが確認されています。
もし身近にアライグマがいる場合は、早急にプロの駆除業者へ相談しましょう。
「ハウスプロテクト」では、相談をはじめ、現地調査や見積もり作成も無料で行っております。
「どう対処したらいいかわからない…」「鳴き声の正体がアライグマか確信がもてない…」そんな場合でも構いません。
24時間365日、ご相談を承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
\相談のみOK/
アライグマを見かけたらどう対処すべき?

もし家の近所や家の中でアライグマを見かけた場合、自力で捕獲してはいけません。
なぜなら、アライグマの捕獲については「鳥獣保護法」という法律に沿って行う必要があるからです。
「鳥獣保護法」では、行政の許可がない場合の捕獲を禁じており、勝手にアライグマを駆除・捕獲した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられるためご注意ください。
またアライグマは「特定外来生物」に指定されております。
捕獲や駆除には、外来生物法に基づく防除計画や自治体の許可が必要です。
ちなみにアライグマを駆除するために捕獲した後、無許可で野外に放つ行為も禁止されております。
違反すると3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されるため注意しましょう(第9条、第32条)。
参考:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
環境省「防除に関するQ&A」
環境省「日本の外来種対策 罰則について」
アライグマの凶暴性や病気への危険性もさることながら、このような法律上の縛りや侵入口の封鎖の難易度などを考慮すると、やはり自力で駆除すべきでないといえるでしょう。
また、「忌避剤」「燻煙剤」など使用して追い出すことで対処する方も多くいらっしゃいますが、これだけではほぼ100%被害が再発します。
アライグマは賢く、1回の妊娠で5匹産むほど繁殖力が高いため、被害も深刻になりやすいです。
そのため、もし見かけたら一刻も早く、プロの駆除業者へ相談しましょう。
アライグマ駆除は専門業者「ハウスプロテクト」へ相談
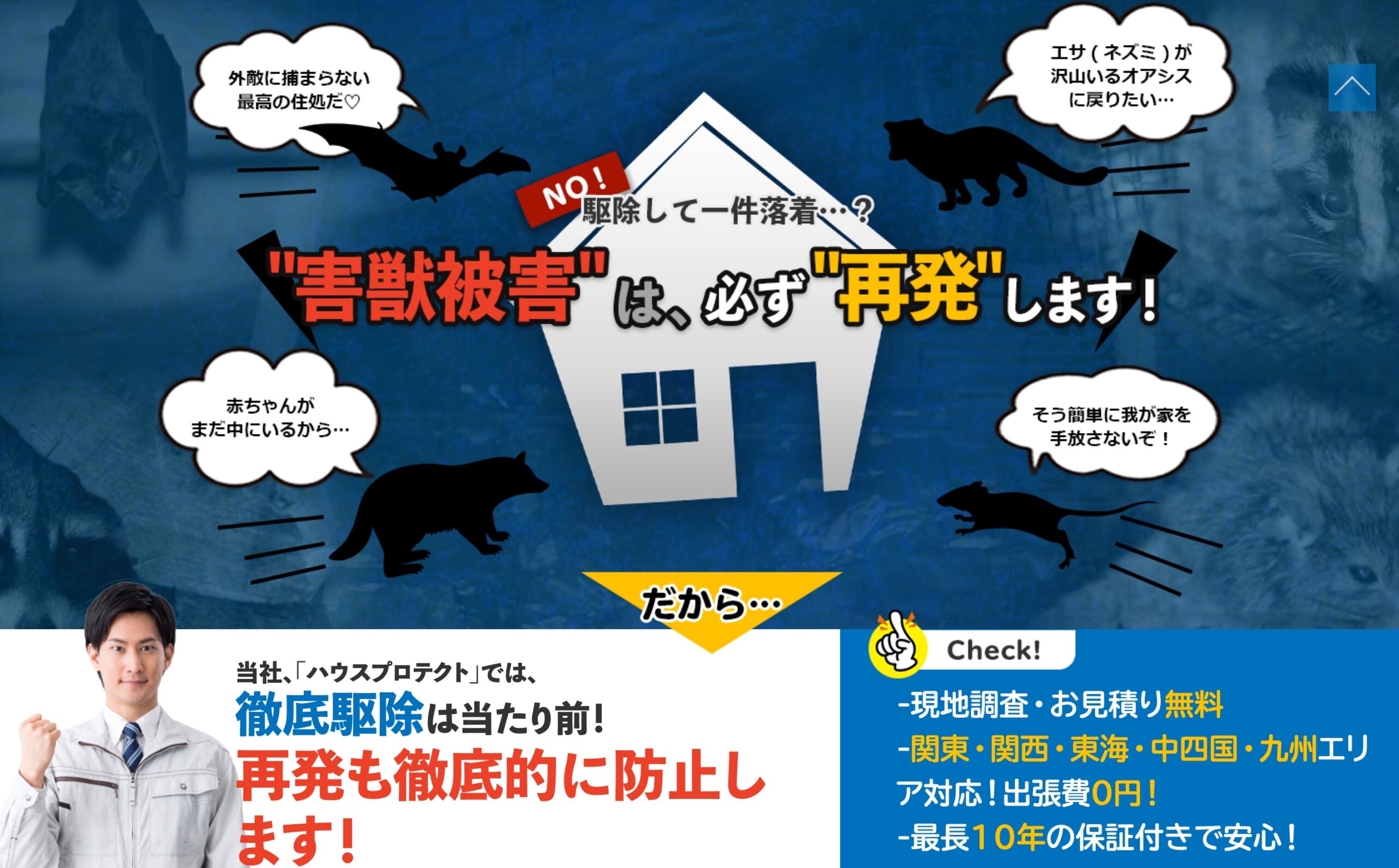
アライグマの鳴き声や姿を確認したら、「様子見」ではなく、専門業者に相談すべきです。
なぜなら、アライグマを放置してしまうと、以下のような被害が起こりかねいからです。
鳴き声や足音による睡眠妨害
糞尿による建物の損傷や健康リスク
配線かじりによる火災リスク
家全体にダニやウイルスが拡散
また最悪の場合、狂犬病やアライグマ回虫といった死に至るような病原菌・感染症のリスクもあります。
アライグマ駆除専門業者の「ハウスプロテクト」では、通話料をはじめ、現地調査やお見積りまで無料で行っております。
24時間365日、受け付けておりますので、夜間に鳴き声が聞こえた場合でもご対応させていただきます。
アライグマの被害に遭う前に、まずは一度、ご相談ください!
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる屋内害獣に対応。
まずは被害状況をお聞かせください。