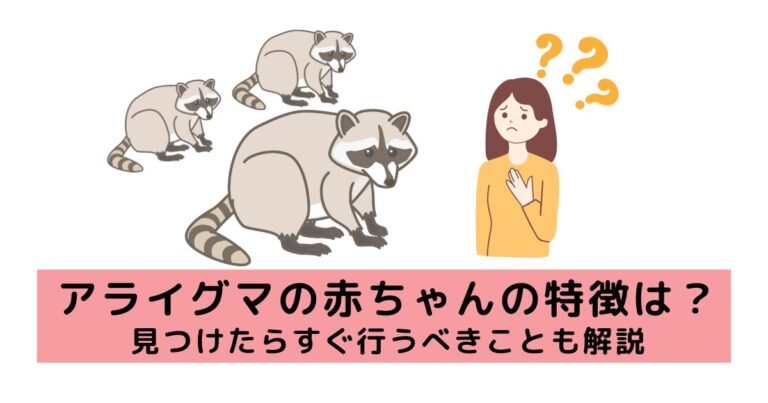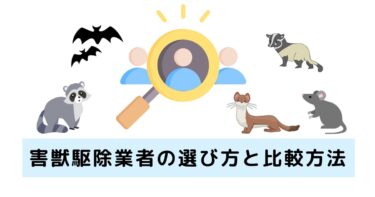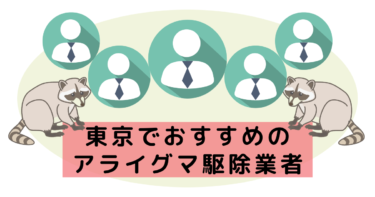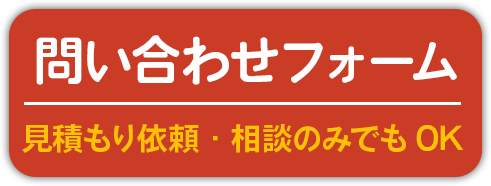「アライグマの赤ちゃんを見つけたけど、どうしたらいいか分からない」と困っていませんか。
近年、アライグマは日本全国で急速に繁殖数を伸ばしており、都市部や住宅街でも目撃情報が増加しています。
具体的には、騒音や悪臭、建物の損壊、農作物を食い荒らすといった被害を引き起こしかねません。さらにアライグマは、アライグマ回虫、狂犬病、レプトスピラ症などの病原菌を保有している可能性があります。
こうした被害に遭わないためにも、早急に対処する必要があります。

ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
アライグマとはどんな動物?成体と赤ちゃんで特徴を比較!
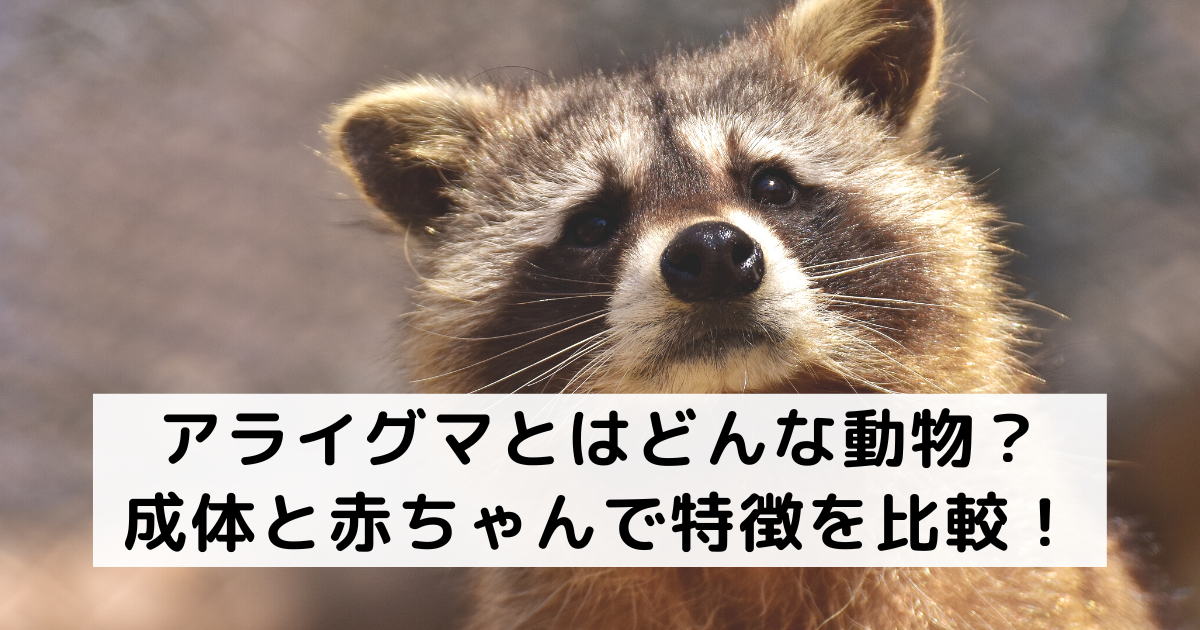
赤ちゃんのアライグマの特徴を正しく知るために、そもそもアライグマとはいったいどんな動物なのか、特徴を以下にまとめました。
- 頭胴長:41~60センチ(尾:20~41cm)
- 体重:2キロ~10キロ(稀に20キロ超える個体も)
- 毛の色:灰白色の場合が多い(稀にほとんど黒色の個体も)
- 指:人の手に似た5本指
- 性質:夜行性
見た目については、次の特徴があります。
- 目のまわりから頬にかけて黒いマスクのような模様
- ふさふさとした毛が生え長い尾
- 黒いリングのような模様
- 白く目立つヒゲ
- 大きい耳には白い縁取り
次に赤ちゃんアライグマの特徴についても見ていきましょう。
赤ちゃんアライグマの特徴
生まれたてのアライグマの赤ちゃんの特徴を以下にまとめました。
- 頭胴長:12センチ
- 体重:70g
- 毛の色:茶色だが目のまわりの黒いマスク模様がある
赤ちゃんアライグマは親とは毛の色が少し違い、尻尾の模様も生まれたての頃はハッキリしていません。
1ヶ月程度経てば、親と似た毛色になり、生後1年ほどは母親のアライグマと暮らす傾向があります。
赤ちゃんアライグマを見つけたらペットにしても良い?
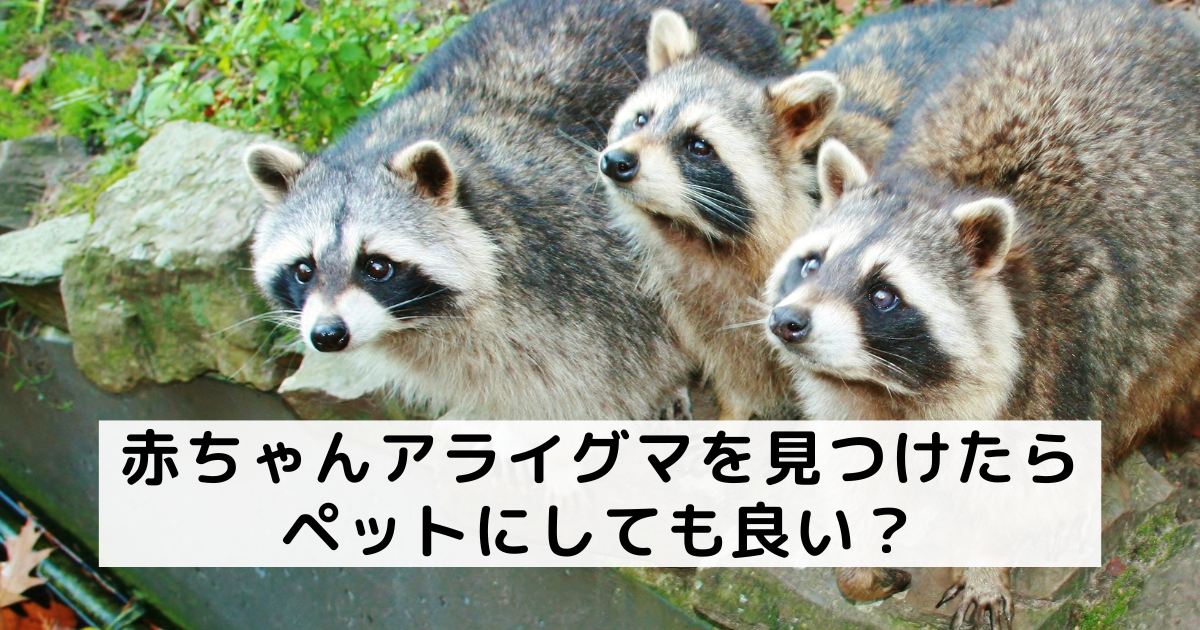
実際に赤ちゃんアライグマを見かけたときに「可愛いからペットにしたい!」と感じるかもしれませんが、ペットにするのはやめておきましょう。
赤ちゃんアライグマをペットにしないほうがいい理由は以下のとおりです。
- アライグマは「特定外来生物法」に指定されている
- アライグマの赤ちゃんに直接触れてはいけない
それぞれの理由について、以下で順番に解説します。
アライグマは「特定外来生物法」に指定されている
アライグマは、もともと北米〜中米に生息していた外来種です。日本にはペット目的などで持ち込まれた経緯があります。
しかし現在では、「外来生物法」により「特定外来生物法」に指定されています。
参考:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
環境省「防除に関するQ&A」
環境省「日本の外来種対策 罰則について」
「可愛いからペットにしたい」「かわいそうだから助けてあげたい」という思うかもしれませんが、エサを与えたり、触ったりするだけでも法律違反となる可能性があります。

アライグマの赤ちゃんに直接触れてはいけない
アライグマの赤ちゃんは見た目がかわいくても、体の内外にさまざまな病原体や寄生虫を持っている可能性が高いです。
具体的には、次のような感染症や寄生虫のリスクがあります。
| 病名 | 病原体 | 感染経路・特徴 | 主な症状・リスク |
| アライグマ回虫症 | アライグマ回虫 | 手や土を介して糞中の虫卵を経口摂取 | 幼虫移行症。中枢神経障害・臓器障害。死亡例もあり |
| エキノコックス症 | エキノコックス属条虫 | 土壌や食物を介して虫卵の経口摂取 | 肝臓などに腫瘤形成。10年以上潜伏し、重症化のおそれ |
| SFTS(重症熱性血小板減少症候群) | SFTSウイルス | アライグマの体表に付いたマダニに刺されることで感染 | 発熱、嘔吐、血小板減少。重症化すると死亡リスクあり |
| 日本紅斑熱 | 日本紅斑熱リケッチア | アライグマの体表に付いたマダニに刺されることで感染 | 発熱、発疹、重症化で死亡するケースも |
| レプトスピラ症 | レプトスピラ菌 | アライグマの尿や体液、またはそれらに汚染された土壌と接触 | 発熱、筋肉痛、腎障害や黄疸など重症化の可能性あり |
| 狂犬病 | 狂犬病ウイルス | アライグマに噛まれることで感染 | 神経症状を伴い、発症後はほぼ致死性 |
| 外部寄生虫 | ダニ、ノミ、シラミ | 体表に付着しており、接触・環境汚染により感染 | 痒み・皮膚炎、さまざまな病原体を媒介する可能性あり |
参考:
アライグマ回虫による幼虫移行症
①エキノコックス症とは|国立感染症研究所
②エキノコックス症について|厚生労働省
SHTS
千葉県における日本紅斑熱 – 国立感染症研究所
アライグマ狂犬病による初の死亡例、2003年-米国・バージニア州
そのため、アライグマの赤ちゃんを飼育することはもちろん、絶対に触ってはいけません。
屋根裏や床下、空き家などで赤ちゃんを見つけた場合、自力で対処するか、プロの専門業者に相談することをおすすめします。

「ハウスプロテクト」では、相談をはじめ、現地調査も無料で承っておりますのでぜひお気軽にお問い合わせください。
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
赤ちゃんアライグマはどうやって駆除したらいい?

アライグマは、赤ちゃんであろうと「特定外来生物」かつ「鳥獣保護管理法」で保護されています。
そのため、国や地方自治体の許可なく、捕獲したり危害を加えたりすると法律違反になります。
したがって、追い出しグッズを活用して家から出て行ってもらうことになります。
アライグマを駆除するための追い出しグッズとは?
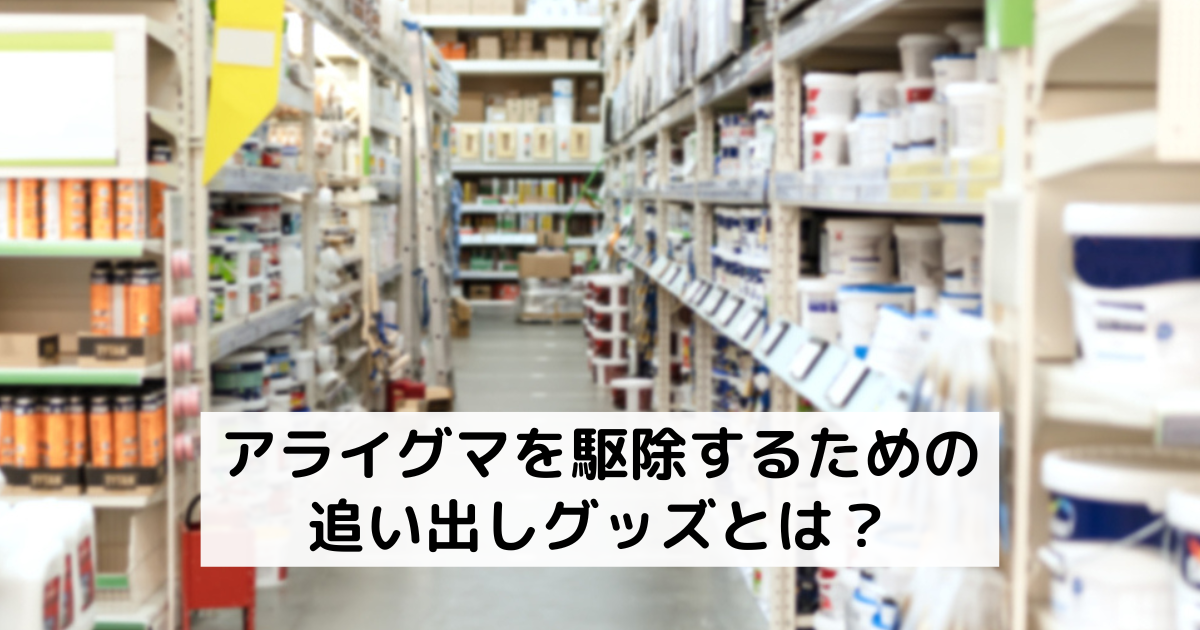
以下、アライグマを駆除する際に使える、代表的な追い出しグッズです。
- 忌避剤
- くん煙剤
- 超音波発生装置
これらのグッズは、ホームセンターやインターネットで購入することができます。
しかし、ご自身でアライグマを追い出す場合、以下3つのリスクがあるので注意しましょう。
- 法律違反のリスク
- アライグマに襲われる
- 感染症のリスク
また、生後間もないアライグマの赤ちゃんに追い出しグッズを使った場合、親とはぐれて死んでしまうトラブルにもなりかねません。

そのため、「自力で対処できそうにないし、とりあえず様子を見てみよう」と放置してしまう方も少なくないと思います。
しかし、アライグマを放置してしまうと、以下の被害が発生する可能性があります。
- 騒音
- 悪臭
- 建物の損壊
- 感染症
- 農作物の食い荒らし
以上のようにアライグマは、赤ちゃんであっても法律違反のリスクがあり、駆除が難しく、さらに放置すると被害が拡大する可能性があります。

クチコミ評価業界トップクラスを誇る「ハウスプロテクト」では、通話料をはじめ、現地調査や見積もり作成もすべて無料で承っております。
アライグマの被害が発生する前にぜひお気軽にお問い合わせください。
\24時間365日受付中!相談のみ/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
赤ちゃんアライグマが家にいるかわからないときは?
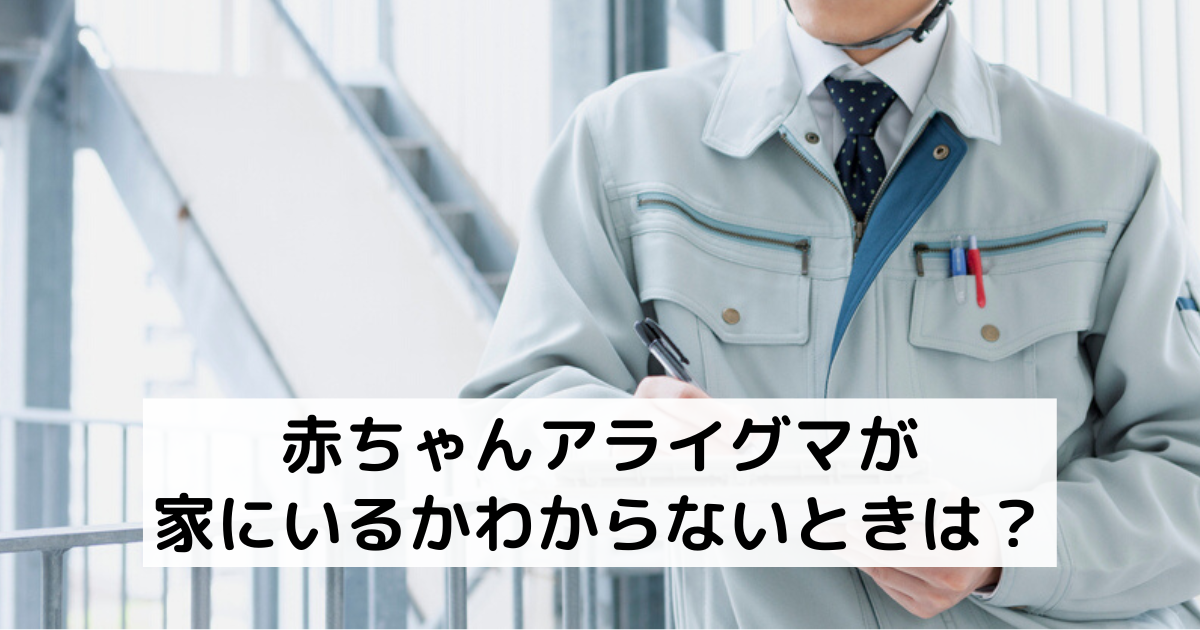
「なんとなく、赤ちゃんアライグマがいるような気がするけど、確信がもてない…」そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。
以下に赤ちゃんアライグマが住居内・庭にいるチェックリストをまとめました。
1つでもあてはまる場合、被害が発生する可能性が高いためプロの害獣駆除業者へのご相談をおすすめします。
☐屋根裏・壁内から小さな鳴き声が聞こえる
☐屋根裏・壁内から足音やガサガサ音がする
☐屋根裏・壁内から弱々しい鳴き声が続く
☐屋根裏・床下・壁内に巣材や動物の毛がある
☐柱・壁・屋根瓦に泥や爪痕、足跡がある
☐庭の果樹・畑・池の魚・ペットのエサが荒らされている
☐尾に縞模様のあるタヌキに似た動物を見た
☐屋根や塀の上で中型犬くらいの動物を見た
☐巣の近くに小さな排泄物や赤ちゃんの姿がある
上記1つでもあてはまる場合、まずは一度、プロの害獣駆除業者に相談してみてください。
プロの害獣駆除業者「ハウスプロテクト」の場合、アライグマの生態や習性を熟知しているため、的確な判断と迅速な対応により被害の発生や拡大を防いでくれます。
\24時間365日受付中!相談のみ/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
アライグマ駆除は早期対策がカギ!一匹でも見つけたら専門業者に!!
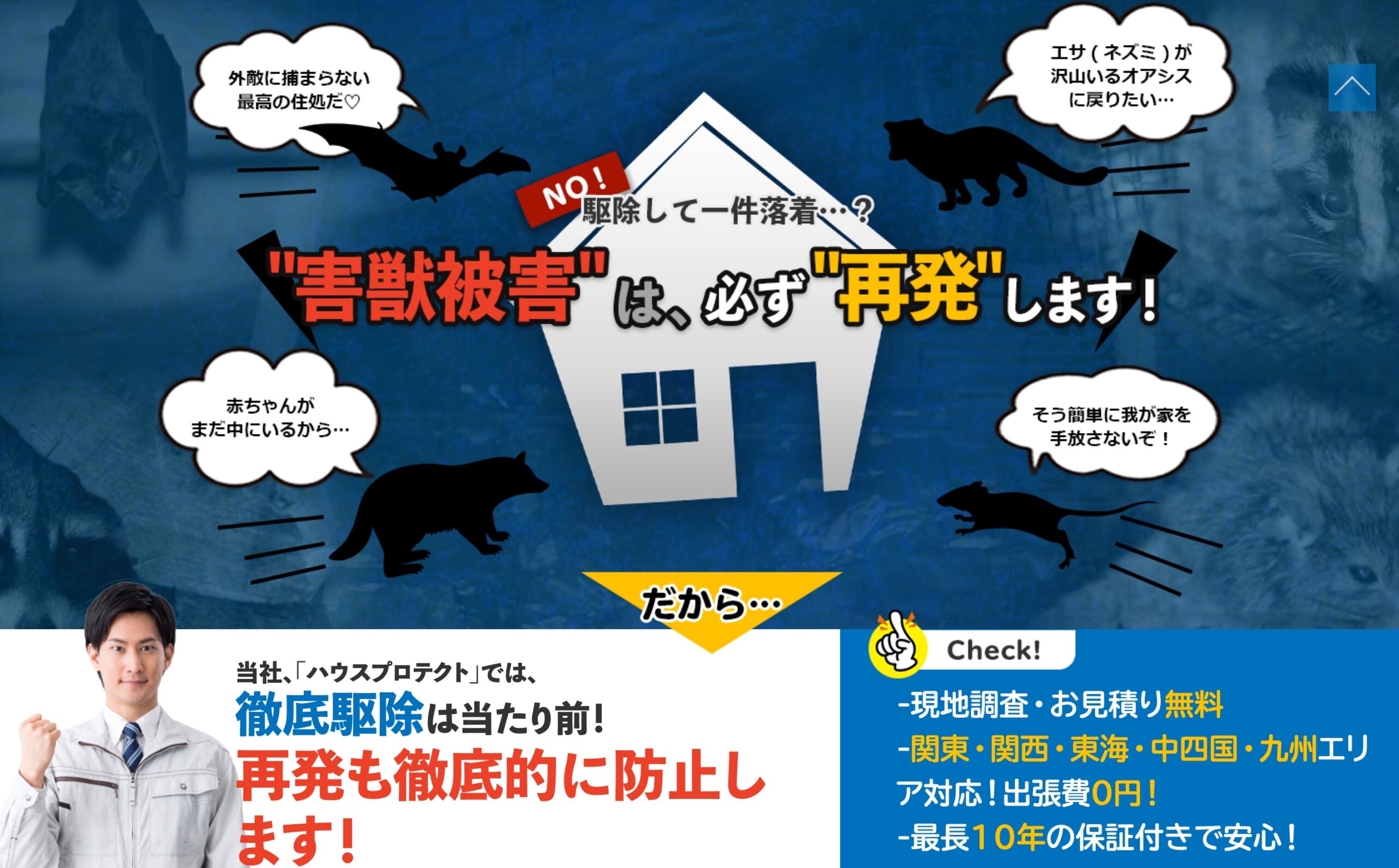
「まだ被害が出ていないし業者に相談するのは大袈裟?」
「そもそも赤ちゃんアライグマが家にいるかわからない…」

しかし、アライグマの被害は、時間とともに拡大してしまうため早期対策が重要となります。
もしアライグマを放置してしまうと、騒音や悪臭、建物の損壊などの被害に発展しかねません。
以上のように、赤ちゃんであってもアライグマは放置してはいけません。
しかし、アライグマは「特定外来生物法」や「鳥獣保護法」により、保護されているため、一般の方が許可なく捕獲、駆除すると法律違反になります。
そのため、まずは一度、プロの害獣駆除業者へ相談しアドバイスを受けることをおすすめします。
アライグマ駆除についてお気軽にご相談ください!
累計10,000件以上の実績がある「ハウスプロテクト」では、アライグマの捕獲、駆除のノウハウを使い、徹底的に駆除工事します。
追い出しはもちろん、侵入経路の封鎖までプロが徹底的に行います。

また「最長10年の再発保証」を用意しているので、万が一アライグマの被害が再発した場合は無償で対応いたします。
そんな「ハウスプロテクト」では、通話料をはじめ、現地調査や見積もり作成も無料で行っております。
アライグマの被害に遭う前に、ぜひお気軽にお問い合わせください。
\24時間365日受付中!相談のみ/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
まとめ
赤ちゃんのアライグマは、小柄で愛らしい見た目をしています。
しかし、赤ちゃんとはいえ、アライグマは感染症のリスクをはじめ、騒音や悪臭、建物の損壊などの被害を引き起こしかねません。
また、一匹でもアライグマの赤ちゃんを見かけた場合は、身近に大人のアライグマがいる可能性が高く、ご自宅がアライグマの住処になっている可能性もあります。
もしお住まいがアライグマの住処になってしまうと、より一層、被害が発生し深刻化するリスクがあります。
さらに、ご自身で駆除する場合、「特定外来生物法」や「鳥獣保護法」といった法律に違反する恐れがあるため、自力で対処するのはおすすめできません。
そのため、身近に赤ちゃんアライグマがいるかもしれない場合は、早めにプロの駆除業者に相談し、対処してもらうことをおすすめします。
「自分で対処できそうにない…」「子どもやペットに危害があったらどうしよう…」そんな方は、ぜひご相談ください。
プロの害獣駆除業者「ハウスプロテクト」が的確な判断と迅速な対応により、アライグマの被害からあなたを守ります!
\24時間365日受付中!相談のみ/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。