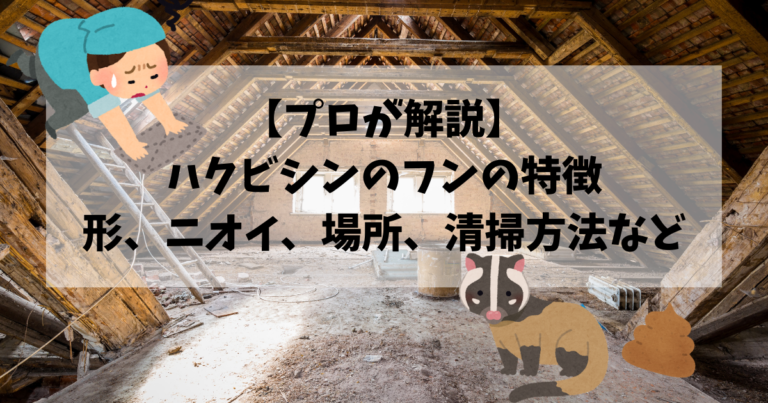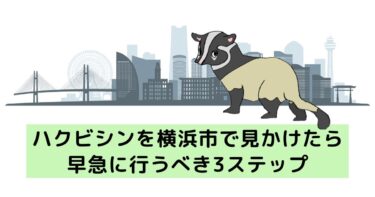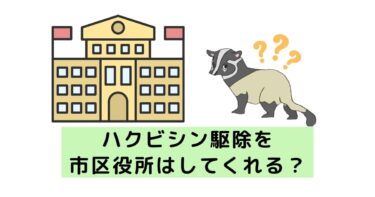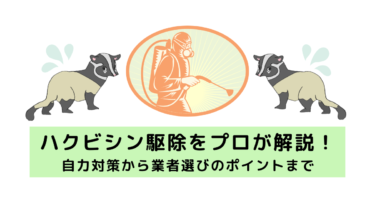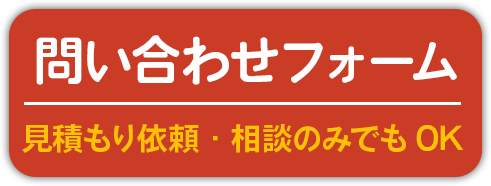ハクビシンのフンを見つけた場合、決して素手で触ってはいけません。
また放置していると、人体や住まいにも被害が及ぶため正しく対処する必要があります。
そこで本記事では、ハクビシンのフンの特徴から危険性、そして安全な処理方法と再発防止策までプロの視点から詳しく解説します。
ハクビシンによる被害を最小限に抑え、安心して暮らせる生活を取り戻したい方はぜひご参考ください。
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
ハクビシンのフンの特徴【形・大きさ・ニオイ・量・色】

上の写真は、ハクビシンのフンです。
ハクビシンのフンを見つけるポイントは、次の4つが挙げられます。
- 形・大きさ
- ニオイ
- 量
- 色
以下にてそれぞれについて詳しく見ていきましょう。
形・大きさ
ハクビシンのフンは、丸みを帯びた細長い形をしており、大きさは5~15センチ程度です。
見た目の特徴としては、種子が混じっていることが多いです。
これは、ハクビシンが野菜や果実を好んで食べることが起因しています。
ニオイ
ハクビシンのフンは、特にニオイがキツくないことが多いのが特徴です。
むしろ、果実をたくさん食べるため、甘い香りになることもあります。
ただし、ニオイで見分けるうえで厄介なのが、ハクビシンはフンと同じ場所に尿もすることがあり、尿は強烈なアンモニア臭を放っていることです。
したがって、尿があればアンモニア臭、尿がなければ無臭というのが、ハクビシンのフンをニオイで見分けるポイントとなります。
量
ハクビシンは、決まった1か所に大量のフンをする性質があります。
ちなみに、屋根裏の1か所に集中してフンをされることで、そこにシミが出来やすくなったりします。
色
ハクビシンのフンの色は、こげ茶色や黄土色です。
ただし、人間のフンの色がその時々で少しずつ違うのと同じで、ハクビシンのフンの色も状況毎に異なります。
それは、ハクビシンが雑食で、野菜や果実、小動物や昆虫など様々なものを食べるため、食べたものによって色が変化するからです。
【ハクビシン以外】他の動物のフンとの違いを比較

ハクビシンと他の動物のフンの特徴との違いを以下にまとめました。
| 動物 | サイズ・形状 | 色 | 混入物・臭いなどの特徴 | ハクビシンのフンとの主な違い |
|---|---|---|---|---|
| ネズミ | 米粒大 (5‑10 mm)・楕円/紡錘形 | 黒っぽい | 特徴的な混入物は少なく、数が非常に多い | 圧倒的に小さい・数が多い |
| タヌキ | 棒状・直径2‑3 cmと太い | 黒褐色 | 木の実・被毛など未消化物が目立つ | ハクビシンより太く、種子以外の繊維質が多い |
| イタチ | 細長・数 cm | 黒褐色 | 強い臭気 | ハクビシンより細長く短い・種子がほぼ含まれない |
| アライグマ | 棒状だが太さ・長さが不規則 | 黒褐色 | 未消化物が混ざる | ハクビシンより太めで形が不揃い・排泄場所が広範囲 |
ハクビシンのフンと間違えやすい動物のフンを比較し、見分け方のポイントを以下で詳しく解説します。
ネズミのフン
ネズミのフンは、米粒(5〜10mm程度)くらいの小ささで、黒っぽい色をしています。
形状は楕円形または紡錘形です。
ハクビシンのフンに比べて明らかに小さく、数も多く見られることが多いです。
タヌキのフン
タヌキのフンも棒状ですが、ハクビシンよりも太く、直径2〜3cmほどになることもあります。
色は黒褐色で、消化されにくい食べ物(木の実や毛など)が混ざっていることが多いです。
ハクビシンのフンはタヌキに比べて細く、果実の種が目立つ傾向があります。
イタチのフン
イタチのフンは、小さく細長い形状で、黒褐色をしています。
数センチ程度の長さで、独特の強い臭いを放つことがあります。
ハクビシンのフンは、より太く、果実の種が含まれる点で異なります。
アライグマのフン
アライグマのフンも棒状で、黒褐色をしており、消化されにくいものが混ざることがあります。
ハクビシンのフンと似ている場合もありますが、アライグマの方がより太く、やや不規則な形状をすることが多いです。
ハクビシンは特定の場所に溜めフンをする習性がありますが、アライグマは比較的広範囲に排泄することがあります。
「どの動物のフンか見分けられない」そんな場合は、まずはプロの害獣駆除業者に相談するのも良いでしょう。
プロの害獣駆除業者「ハウスプロテクト」では、メール・電話相談をはじめ、現地調査や見積もり作成もすべて無料で行っているので、気軽にお問い合わせできます。
\最短即日対応!相談のみOK/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
ハクビシンのフンが溜まりやすい場所

ハクビシンには、決まった場所で排泄を繰り返す「溜めフン」という習性があります。
この習性は、「ハクビシンがどこにいるのか」「どこを通っているのか」を推測する手がかりになります。
屋根裏・天井裏
最もハクビシンのフンが溜まりやすい場所が屋根裏や天井裏です。
屋根裏や天井裏は、静かで暗く、外敵に襲われにくい環境であるため、ハクビシンの繁殖や休息の場として選ばれることが多いです。
また日本の多くの家屋は構造上どうしても隙間が生じやすいため、ハクビシンに侵入されやすい特徴があります。
具体的には、通風口や換気口、屋根と壁の接続部、基礎部分などが挙げられます。
雨どい・ベランダ・庭
屋根裏だけでなく、雨どいやベランダ、庭などもハクビシンの通り道や休息場所となり得ます。
特に、植物や果実が多く生えている庭は、餌場としても利用されるため、フンが残されていることがあります。
そのほか、ベランダの隅や室外機の下などもハクビシンの隠れ場所に使われやすいです。
ハクビシンのフンが引き起こす被害

ハクビシンのフンを放置すると健康被害や家屋への被害を引き起こす可能性があります。
家の周りにハクビシンのフンがあると、見た目が悪く、強烈な悪臭で不快に感じるでしょう。
しかし、それ以上に危険なのは、放置することで人体や住宅に深刻な被害をもたらす可能性があります。
では、ハクビシンのフンをそのままにしておくと、具体的にどのような被害が起こるのでしょうか?
特に注意すべき2つの被害を詳しく見ていきましょう。
健康被害
ハクビシンのフンや尿は、以下の健康被害を引き起こす可能性があります。
| 健康被害 | 主な原因・病原体例 | 主な症状 |
|---|---|---|
| 食中毒・感染症 | サルモネラ菌、エルシニア菌、カンピロバクター、E型肝炎、トキソプラズマ | 下痢、嘔吐、腹痛、発熱、筋肉痛、黄疸など |
| 皮膚疾患・寄生虫症 | ノミ、ダニ、回虫 | かゆみ、発疹、アレルギー、皮膚炎、感染症 |
| アレルギー反応 | フンのアレルゲンやダニ・ノミ | 鼻炎、喘息、アトピー性皮膚炎 |
| 悪臭・衛生被害 | フン・尿の腐敗、カビの発生 | 呼吸器系への悪影響、不快感 |
また一部の報告では、SARS(重症急性呼吸器症候群)の感染源である可能性も指摘されています。
特に幼児や高齢者、免疫力の弱い方は重症化しやすいため、フンを発見した場合は早急に対処しましょう。
「これらの健康被害に遭いたくない」「もし感染したらどうしよう…」といった場合は、プロの害獣駆除業者への相談も検討しましょう
家屋への被害
ハクビシンのフンは家屋にも被害を及ぼします。
またハクビシンのフンを長期間放置すると、断熱材を傷めたり、悪臭やカビを発生させるため、決して放置してはいけません。
ちなみにハクビシンが屋根裏に住み着いた場合、断熱材が剥がされる、配線がかじられるといった被害が進行し、大規模な修繕が必要となった場合、高額な修繕費が発生します。
ハクビシンのフンを安全に処理する方法

ハクビシンのフンを見つけたら、健康被害や家屋への被害を発生させないためにも早く処理しましょう。
以下ではハクビシンのフンを安全に処理する方法を解説します。
手順①必要な道具を用意する
ハクビシンのフンには、多くの病原菌が含まれています。
そのため、処理する際は、菌が体に付着しないよう、さまざまなアイテムを準備しておく必要があります。
少し多く感じるかもしれませんが、以下のアイテムを揃えてからフンを処分しましょう。
| アイテム名 | 概要 | 価格の目安 |
| 肌の露出が少ない服装 | フンが直接肌に触れるのを防ぐため、不要な長袖・長ズボンを用意しましょう。 | 購入するなら2,000~3,000円 |
| マスク・手袋・防護メガネ | フンに付着した菌が体内に入らないよう、必ず着用してください。 | 3,000円 |
| ダニやノミの殺虫剤 | フンがあった場所の周辺に潜むダニやノミを駆除するために必要です。 | 1,000円/本 |
| ホウキ・ちりとり | フンを集めて処分するために使います。後で捨てるので、安価なものがおすすめです。 | ~500円 |
| 消毒液(次亜塩素酸ナトリウム) | 病原菌を確実に消毒するため、殺菌効果の高い次亜塩素酸ナトリウムを主成分とする消毒液を使用しましょう。 | 1,000~2,000円 |
| ペット用消臭剤 | ハクビシン特有の獣臭や、ためフンの悪臭を取り除くために用意します。 | 1,000円/本 |
| 雑巾 | 清掃後、住宅を拭くのに使います。念のため3~4枚程度あると安心です。 | 300円 |
これらすべてを揃えると、おおよそ1万円程度の費用がかかります。
またハクビシンのフンの処分時に使った衣類、マスク、手袋、ホウキ、ちりとり、雑巾などは再利用できませんので、安価なもので揃えたほうがよいでしょう。
手順②フンを集めて処分する
必要な道具が揃ったら、ホウキとちりとりを使ってフンを集め、密封できる袋に入れて廃棄します。
使用後のアイテムは再利用できないため、その場で廃棄が必要です。
したがって、ホウキやちりとりは安価なものを選び、使い捨てを前提とすることをお勧めします。
また、素手で触る、ほうきで掃くといった行為も危険です。
手順③消毒・殺菌し、侵入経路を塞ぐ
フンを処理した後、その場所を以下の手順でしっかり消毒・殺菌しましょう。
- 消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム※などをスプレーボトルに入れ、フンがあった場所や周辺に散布する
- しばらく時間をおいてから、清潔な布やペーパータオルで拭き取る
- 使用した掃除用具や布類は、すぐにビニール袋に入れて密閉し、可燃ごみとして適切に処分する。
※家庭用塩素系漂白剤を薄めたもの
参考:
次亜塩素酸とは?(種類・アルコールとの違い) | 次亜塩素酸ラボ | Panasonic
消毒液を使用する際は、必ず換気を行い、他の洗剤、特に酸性タイプのものと混ぜないように注意してください。
フンに含まれる病原体は、免疫力が低下している人や動物にとっては、より危険な場合があります。
そのため、プロの害獣駆除業者に処理してもらうことをおすすめします。
どうしてもご自身で行う場合は、手順①と②をより一層厳守し、作業後は手洗いやうがい、シャワーを徹底してください。
ハクビシンにフンをさせない対策

ハクビシンのフンを処理した後は、もう二度とフンをされないようにハクビシンが寄り付かない環境を作りましょう。
以下でハクビシンにフンをさせない対策を解説します。
ハクビシンが寄り付かない環境を作りたい方はぜひご参考ください。
害獣対策グッズを使う
ハクビシンにフンをさせないためには、害獣対策グッズを使うのが一番手軽でおすすめです
そんなハクビシンに効果的な対策グッズは以下のとおりです。
| 対策グッズ | 特徴 | 価格の目安 |
| 木酢液(もくさくえき) | 木炭や竹炭を製造する際の煙成分から作られた液体で、ハクビシンが嫌がるニオイを放ちます。 | 500~1,000円 |
| 忌避剤(きひざい) | ハクビシンが嫌うニオイを発し、侵入を防ぎます。スプレータイプや設置タイプがあります。 | 1,000~5,000円 |
| くん煙剤(くんえんざい) | 煙とニオイを発生させて、ハクビシンを追い出します。 | 1,000~1,500円 |
| 害獣撃退ライト | 光でハクビシンを驚かせ、追い払います。 | 1,000~2,000円 |
| 超音波発生装置 | ハクビシンが嫌がる音を発生させて追い払います。 | 2,000~5,000円 |
これらのアイテムは一定の予防効果がありますが、すでにハクビシンがそこをエサ場や巣として認識している場合は、効果が弱まるので注意しましょう。
また、以下3つの対策グッズはお子さんやペットがいる場所での使用には注意が必要です。
- 木酢液
- 忌避剤
- くん煙剤
手の届かない場所に置いたり、成分を吸い込まないようにしたりするなど安全に配慮しながら使用しましょう。
エサとなるものを置かない
ハクビシンが家に住み着くのを防ぐためにも、家の外に生ゴミやペットのエサなどを置かないようにしましょう。
どうしてもゴミを外に置く必要がある場合は、フタ付きのゴミ箱に必ず入れてください。
また農作物や家庭菜園もハクビシンのエサになるため、落ちた実や収穫物は放置しないよう気をつけてください。
侵入経路を遮断する
ハクビシンは頭が入る程度の隙間があればどこからでも侵入できます。
そのため、住宅に隙間や穴がないかをしっかりチェックしておきましょう。
特に注意したいのは、以下の場所です。
- 通気口
- 壁の穴
- 縁の下
- 軒天井の換気口
もしも住宅や屋根裏への侵入経路になりそうな場所があれば、強度の高い金網とネジなどを使ってしっかりと塞いでください。
なお、侵入経路を塞ぐ際は、ハクビシンの死骸が残って腐敗するのを防ぐためにも、中にハクビシンがいないことを必ず確認しましょう。
ベランダや屋根に接する木の枝を切っておく
ハクビシンは木登りをして屋根裏に侵入することがあります。
そのため、屋根裏やベランダに届いている木の枝は切っておきましょう。
ベランダや屋根周りの枝をきちんと剪定しておくことで、ハクビシンが人間を警戒し、木に登らなくなります。
また、雨どいや壁の高い部分などに、ハクビシンが登れないように有刺鉄板や鳥よけスパイクなどを設置することも有効な対策です。
これにより、屋根裏や天井裏などへの侵入を防ぐことができます。
ハクビシンを駆除する際の注意点

もしご自宅にハクビシンが住み着いてしまい、ご自身で駆除したいとお考えの場合は、2つの注意点を押さえておく必要があります。
以下でそれぞれ解説します。
ご自身でハクビシンを駆除する方はぜひご参考ください。
許可なく駆除・捕獲してはいけない
ハクビシンは「鳥獣保護管理法」によって保護されている動物のため、許可なく捕獲することはできません。
まずは、お住まいの市役所などで必要な手続きについて問い合わせてみましょう。
申請方法は自治体によって異なりますが、一般的な手順は以下の通りです。
- 「捕獲許可申請書類」「捕獲場所がわかる図面」など、必要書類を提出する
- 許可証を交付してもらう
- 捕獲する
- 許可証や罠を返却する
多くの場合、捕獲の実施には30日程度の期限が設けられています。
そのため、申請後は、速やかにハクビシンを駆除しましょう。
参考:
環境省 鳥獣保護管理法の概要
捕獲したハクビシンは自分で処分しなければならない
駆除の際に捕獲したハクビシンは、捕獲者が責任を持って処分する必要がある点にも注意してください。
「害獣とはいえ、自分の手で生き物を処分することに抵抗がある」という方も多いと思います。
「自分で処分できそうにない」そんな場合は申請の際に自治体へ相談する、またはプロの害獣駆除業者へ依頼することをおすすめします。
ハクビシン駆除はプロの害獣駆除業者に依頼するのがおすすめ
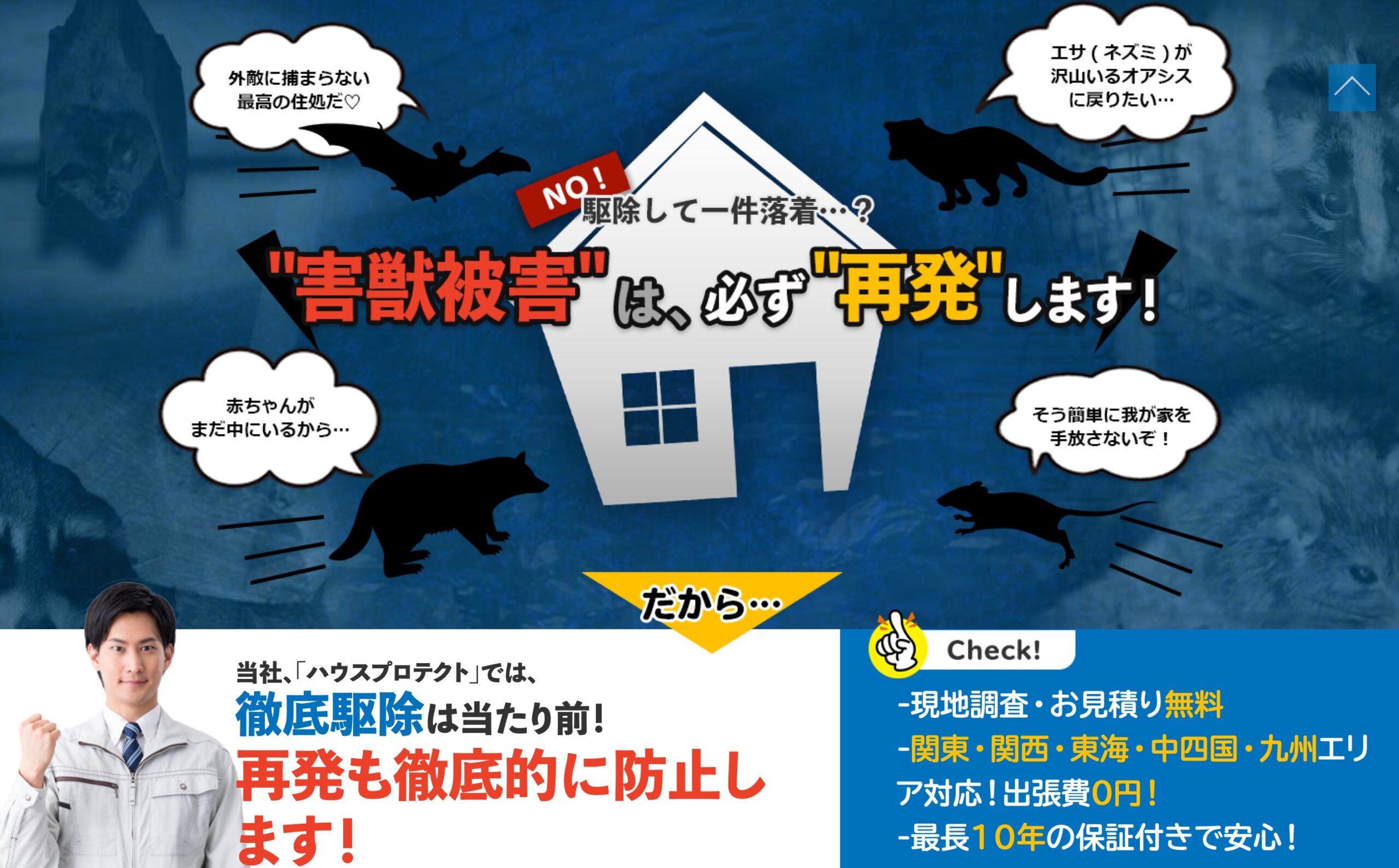
「捕獲したハクビシンは自分で処分しなければならない」と聞いて、「それはちょっと…」と感じた方も多いのではないでしょうか。
個人でハクビシンのフンの清掃や予防策を行うとなると、想像以上に手間がかかりリスクも伴います。
これらを総合的に考えると、ハクビシンの駆除は、やはりプロの害獣駆除業者に依頼するのが賢明な選択と言えるでしょう。
プロの業者に依頼する最大のメリットは、安全で確実な駆除が期待できる点です。
専門知識と経験を持ったスタッフが、ハクビシンの生態や行動パターンを熟知しているため、効果的な方法で迅速に対応してくれます。
また、フンの清掃や消毒作業もプロが徹底して行ってくれるため、感染症のリスクや悪臭の悩みから解放されます。
さらに、プロの業者は、単にハクビシンを駆除するだけでなく、再侵入を防ぐための対策も講じてくれます。
侵入経路の特定と封鎖、予防策の提案など根本的な解決を目指してくれるため、長期的に安心して暮らせる環境を取り戻すことができます。
業界トップクラスのGoogleクチコミ評価をいただいている「ハウスプロテクト」では、メール・電話相談をはじめ、現地調査や見積もり作成もすべて無料で行っております。
「どこに相談すればいいかわからない」といった方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
\最短即日対応!相談のみOK/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。
ハクビシン駆除でハウスプロテクトを選ぶべき5つの理由はこちら>>
【Q&A】ハクビシンのフンによくある質問

ハクビシンのフンに関するよくある質問をまとめました。
- ハクビシンのフンを放置するとどうなる?
- ハクビシンのフンはいつ頃まで臭いますか?
- ハクビシンがフンをするのはどんな時ですか?
- ハクビシンが家にいるときの特徴は?
気になる項目がある方はぜひご確認ください。
以下にて、Q&A形式で回答します。
ハクビシンのフンを放置するとどうなる?
ハクビシンのフンには、病気を媒介する寄生虫や食中毒の原因菌が発生している場合があります。
過去の調査結果では、人間への感染は見られなかったものの、フンの中からサルモネラ菌やエルシニア菌も発見されています。
また、フンを放置しているとダニやノミも集まります。
ハクビシンのフンはいつ頃まで臭いますか?
フン自体の臭いは次第に薄れますが、尿や死骸、繁殖活動による臭いは、清掃・消毒・消臭をしっかり行わないと長期間残ることがあります。
徹底的に清掃・消臭を行ってほしい場合は、プロの駆除業者へ相談しましょう。
ハクビシンがフンをするのはどんな時ですか?
ハクビシンは、主に夜間に活動し、決まった場所で排泄する習性があります。
特に安全で隠れやすい屋根裏や物陰などを利用します。
ハクビシンが家にいるときの特徴は?
ハクビシンが家の中にいると、壁や天井から物音が聞こえることがあります。
またハクビシンは夜行性なので、特に夜間に聞こえる傾向があります。
物音の種類は歩く音や走る音、引っ掻く音やかじる音、落ちる音やぶつかる音などさまざまです。
まとめ
ハクビシンのフンは、単なる糞害にとどまらず、健康リスクや家屋へのダメージ、さらには法律上の問題まで引き起こす可能性があります。
そのため、ハクビシンのフンを見つけたら、まずは落ち着いて状況を確認し、ご家族の安全を最優先に適切な処理を行いましょう。
その後、二度とハクビシンが寄り付かないように、侵入経路の封鎖や環境整備といった再発防止策を講じることが極めて重要です。
ご自身での対処が難しい場合は、迷わずプロの害獣駆除業者に相談し、早く解決してもらうことをおすすめします。
プロの害獣駆除業者「ハウスプロテクト」では、通話料をはじめ、現地調査や見積もり作成もすべて無料で行っております。
「最長10年の再発保証」も用意しているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
\最短即日対応!相談のみOK/
ネズミ、イタチ、ハクビシン、アライグマ、コウモリなど、あらゆる害獣に対応!まずは被害状況をお聞かせください。